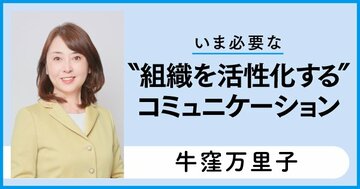「なぜ、この人はそう考えるのか?」――自分と異なる意見や価値観に触れたとき、相手の言葉の背景を想像する力があれば、対立は対話へと変わる。自然人類学者・長谷川眞理子さんは、霊長類のフィールド研究を出発点に、大学教育現場での人材育成や文化行政に携わりながら、人間社会の進化と可能性を探求してきた。「“違い”を面白がることが、相手を理解する第一歩」――異なる価値観と向き合い続けてきた長谷川さんの語りには、職場での多様性の受け入れ方や議論の深め方、新人の挑戦を支える環境づくりについての貴重なヒントが詰まっている。新卒社員(2026年4月入社予定者)向け媒体「フレッシャーズ・コース2026(*)」にも出演している長谷川さんの言葉に耳をすまそう。(ダイヤモンド社 人材開発編集部、撮影/菅沢健治)
*1 「フレッシャーズ・コース2026」(ダイヤモンド社)は、全7巻ワンセットの新卒内定者フォローツール。長谷川眞理子さんは、第6巻の「The Life」(著名人インタビュー)に出演している。
それぞれの視点の違いを理解すれば、議論は面白くなる
行動生態学の研究者として、人間の社会性や進化の背景を探り続けてきた長谷川眞理子さんは、これまで、教育機関や研究組織の運営にも幅広く関わってきた。特に、理系と文系の研究分野が融合する「総合研究大学院大学」で学長を務めた経験は、学問領域ごとに、その考え方や議論の進め方が異なることを深く実感する機会となった。多様な専門領域の教員や研究者と向き合うなかで、長谷川さんが直面したのは、文系と理系、それぞれの学問に根づく“思考の前提”の根本的な違いだった。
長谷川 チンパンジーを追いかける日々から始まった私の研究生活は、仮説を立ててデータを集め、検証し、再構築する――その繰り返しのなかで、自然科学の思考法が身体に染みつくものでした。データを集めて、検証していくスタイルなので、“理系”の研究者同士の議論は明快です。理系の教授会では共通のロジックに基づいて、ある仮説がデータ的に無理だとわかれば、“それなら、次に進もう”と、すぐに結論が出せる。この潔さと合理性が、理系ならではの議論の進め方です。けれども、文系の教授会に参加すると、話の進め方がまったく違っていて驚きます。“この立場からは、こうも考えられる"“こういった視点もある"と、話がどんどん広がっていくのです。文系では、異なる立場を認め合いながら深めていくことが重視されていて、ひとつの結論にまとめること自体が目的ではないのです。
理系では仮説を淘汰し、合理的な方向性を選び取ることが求められる。一方、文系では、多様な視点そのものに価値があるとされる。それぞれのアプローチには、学問ごとの文化が色濃く反映されている。このような、“考え方や方向性の違い”は、研究の場だけでなく、さまざまな組織や職場でも起こり得る。そんなとき、意見の違いを「正しい・正しくない」で判断するのでなく、「背景に思いを巡らすことがカギになる」と長谷川さんは語る。
長谷川 私はいつも、自分とは異なる価値観の人と出会ったとき、“なぜ、この人はこう考えるんだろう?”と、その人の背景を想像するようにしています。どんな経験をしてきたのか、どういう教育を受けてきたのか――背景を見ることで、違う意見に対して否定的になるのではなく、むしろ、その人の価値観に興味を持つことができる。違いを面白がれるようになれば、対話がぐっと豊かになりますよ。

長谷川眞理子 Mariko HASEGAWA
自然人類学者/日本芸術文化振興会 理事長
1952年、東京都出身。東京大学大学院理学系研究科博士課程(人類学専攻)単位取得退学、理学博士。専修大学法学部教授、早稲田大学政治経済学部教授、総合研究大学院大学学長などを歴任し、2023年より日本芸術文化振興会理事長。専門は進化生物学・行動生態学で、霊長類のフィールド研究から人間社会の多様性理解にいたるまで幅広く研究・発信を行っている。ダーウィン研究の第一人者としても知られる。夫は、心理学者の長谷川寿一氏。著書に『進化的人間考』『ヒトの原点を考える』(いずれも東京大学出版会)など多数。26卒(2026年3月卒業予定者)向けのメディア「フレッシャーズ・コース2026」の「The Life」コーナーにもインタビュー出演している。