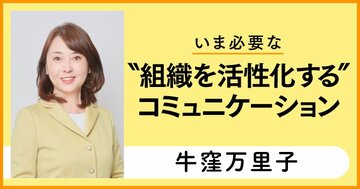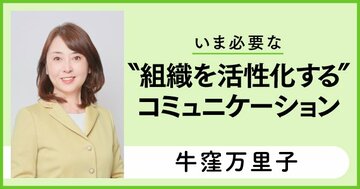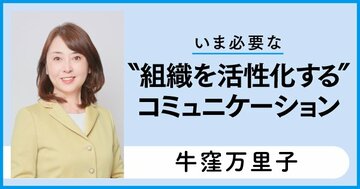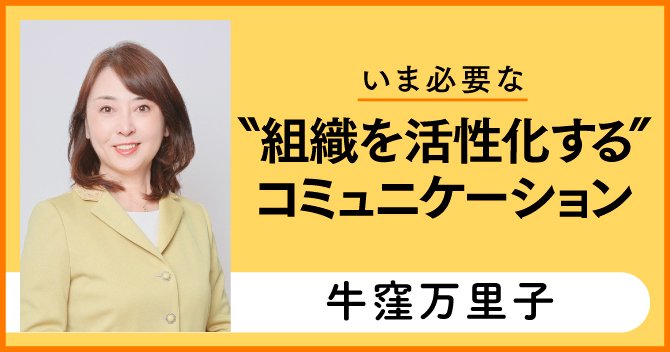
元NHKキャスターとして「おはよう日本」「首都圏ネットワーク」などに出演し、現在はフリーアナウンサーとして多方面で活躍する牛窪万里子さん(株式会社メリディアンプロモーション代表取締役)。牛窪さんは、『なぜか好かれる人の「言葉」と「表現」の選び方』など、多くのビジネス書も執筆するなど、言葉と表現によるコミュニケーションのプロフェッショナルだ。そんな牛窪さんによる連載「いま必要な“組織を活性化する”コミュニケーション」の第4回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
*連載第1回 報道現場から学ぶ、チーム活性化のための“3つのコミュニケーションスキル”
*連載第2回 人と人の信頼関係をつくる“フィードバック”――その6つのポイント
*連載第3回 世代間コミュニケーションのギャップをなくすために、私たちはどうすればよいか
質疑応答は、短い時間の“即興コミュニケーション”
講演やセミナーの終盤で必ず訪れる「質疑応答」の時間。参加者にとっては疑問を解消できる貴重な機会ですが、「みんなの前で質問するのが恥ずかしい」「意図が伝わるか不安」と感じる方も少なくありません。一方で、講師側にとっても「質問が出なかったらどうしよう」「的外れな質問にどう答えればよいか」といった悩みがあります。
質疑応答は、アドリブ的に短い時間で行う「即興のコミュニケーション」ともいえます。成功すれば、その場全体が活性化し、参加者の学びや満足感が格段に深まります。
では、お互いにとって「うまくいく質疑応答」とはどのようなものなのでしょうか。これまで多くの講演やセミナーで質疑応答の場を経験してきた立場から、質問する側・応える側それぞれに役立つポイントをお伝えします。
質問する側の不安を和らげる3つの工夫
まずは、「質問する側」の心構えからご紹介します。
多くの参加者は、質問自体は頭に浮かんでいても「場の空気」に圧倒され、結局、声に出せないまま終わってしまうでしょう。
実際、私が講演を終えると、終了後にそっと近づいてきて、「実はさっきの内容について質問したかったのですが、人前だと躊躇してしまいまして……」と小声で話しかけてこられることがよくあります。あるいは、質疑応答では誰も手が挙がらなかったのに、後で集めたアンケートに同じ質問が複数寄せられることもあります。
つまり、「質問がなかった」のではなく、「声に出せなかった」だけだということがよく分かります。
このように、人前で発言するのは多くの方にとってハードルが高いものです。
そこで、そのハードルを下げるための工夫について、ポイントを3つ挙げてみました。
(1)疑問点をメモしておく
講演中、「なるほど」と思った瞬間に浮かんだ疑問を一言でもいいのでメモに残しておきましょう。人前で発言する際、ゼロから考えようとすると緊張で言葉が出てきません。メモを頼りにすれば、質問の骨格が崩れずに伝えられます。
(2)完璧に言おうとしない
「うまく表現できないのですが……」という前置きをするだけで、謙虚な気持ちが伝わり、たとえ、質問が完璧な内容でなくても、その誠実な姿勢が場の共感を呼ぶこともあります。
(3)講師に語りかける気持ちで
「会場全員に向けて」発言しようとすると余計に緊張します。講師に話しかけるつもりで「私が気になったのは……」と切り出せば自然な流れになります。