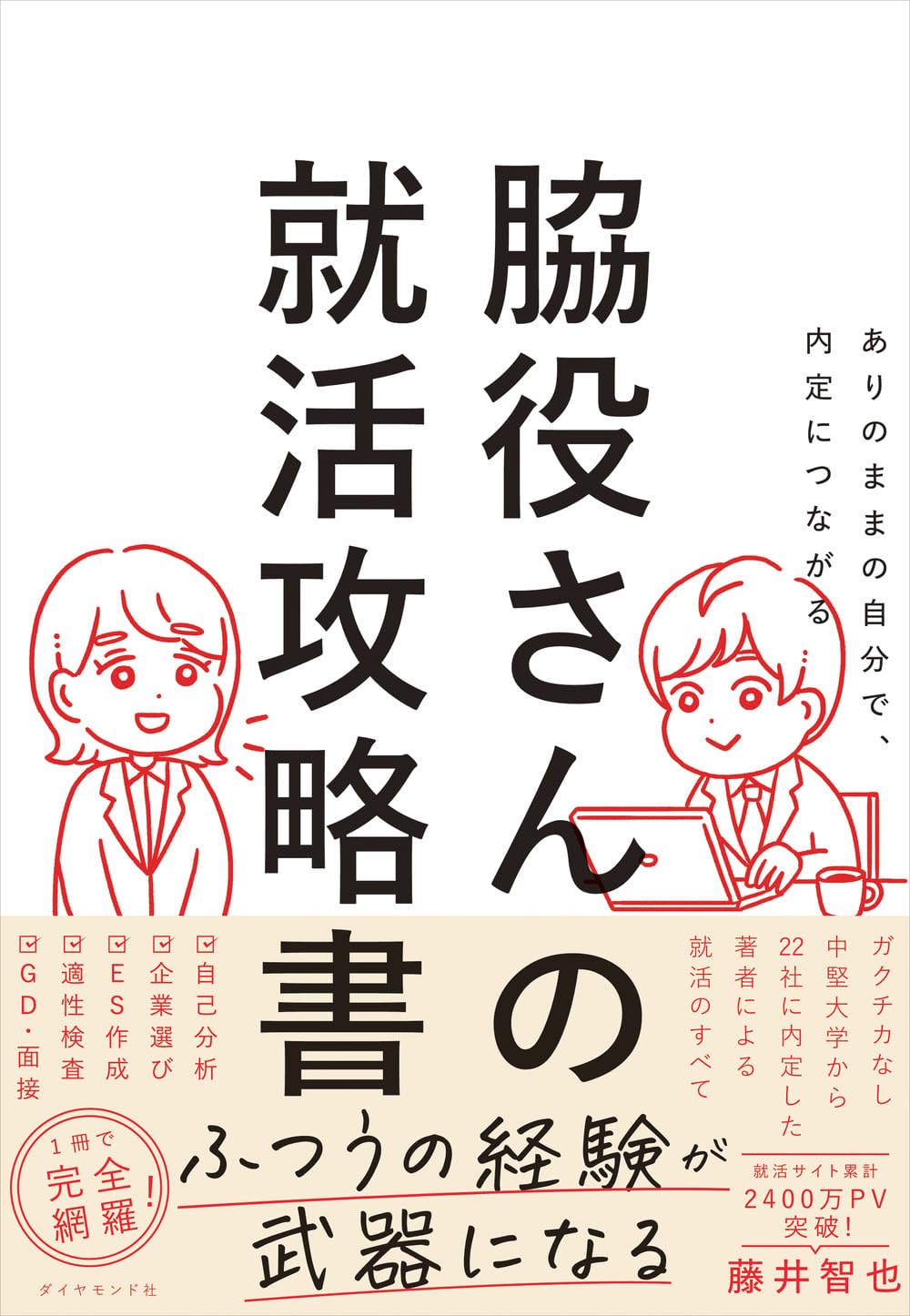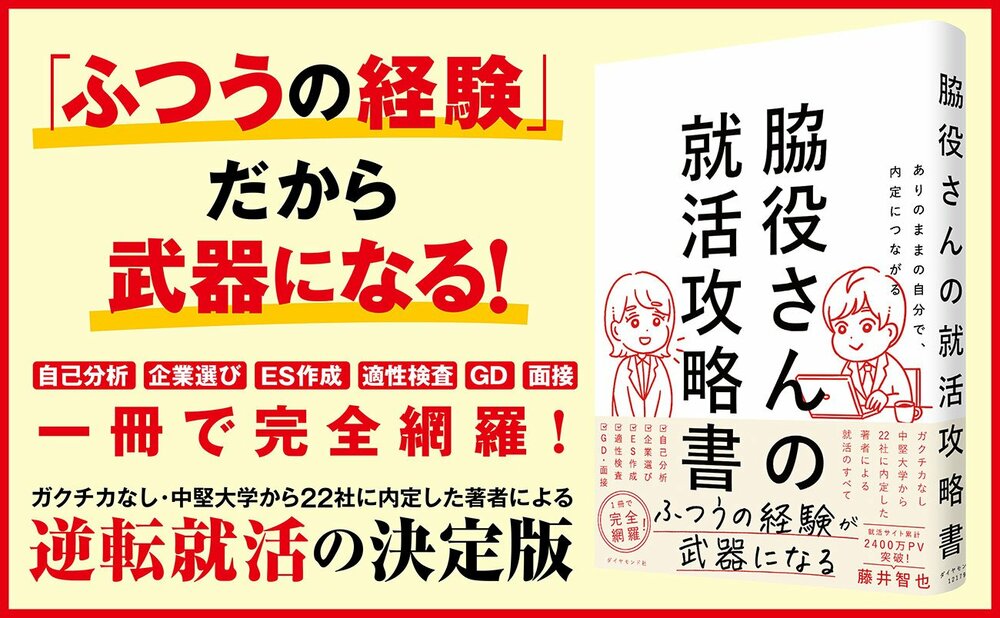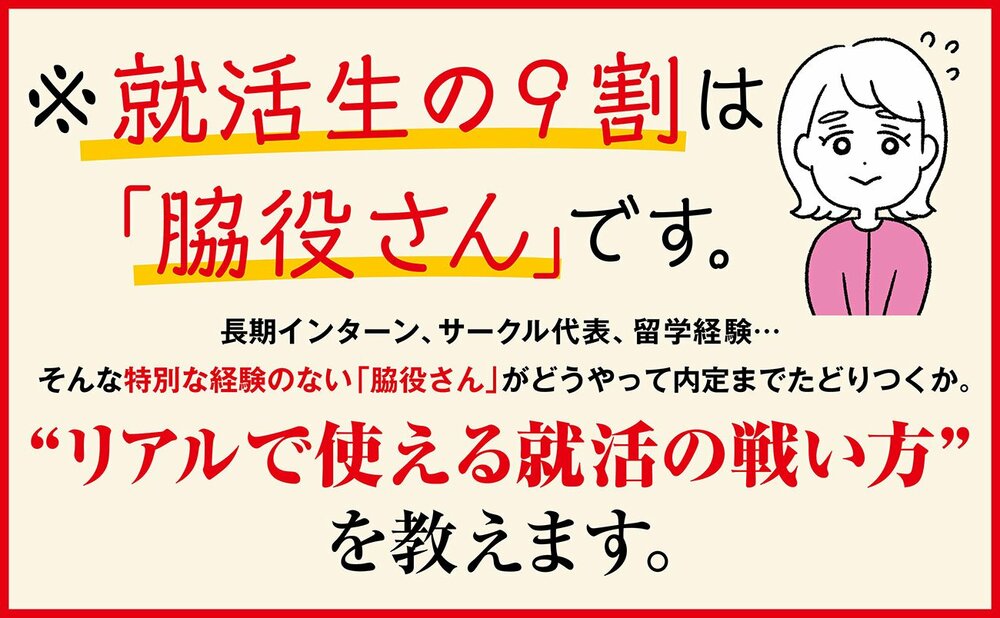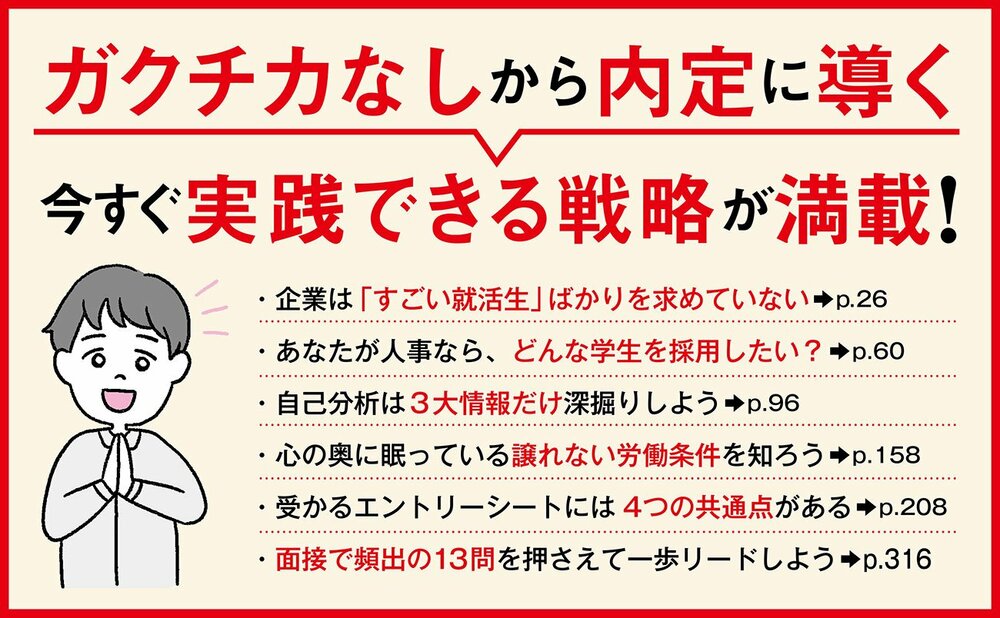二流の逆質問
ここまで逆質問の終わり方をマスターできたと思います。そのうえで逆質問で失敗しないためのポイントも紹介しますね。
就活では「うまくいく方法」から学ぶ以上に、「失敗する共通点」から学ぶ方が有効です。
なぜなら、評価される点は人の数だけ無数にあるのですが、マイナス評価される点はみな共通だからです。
では逆質問において、どんな失敗があるのでしょうか。
大きく3つの共通点があります。
・ネットで調べたらすぐに分かることを聞く
・「それを聞いてどうしたいの?」と思われる質問を聞く
・条件面に関する逆質問
失敗①ネットで調べたらすぐに分かることを聞く
最も多い逆質問の失敗が、ネットで調べたらすぐに分かることを聞くことです。
例えば「貴社の事業内容は?」「今後の注力事業は?」のような質問は、公式サイトや採用ページを少し見れば分かることが多いです。
こうした質問をしてしまうと、「調べる気がないのかな?」「志望度低そうだな」とマイナス評価につながります。
もちろん、調べたうえでどうしても気になることを深掘りするのはOK。
たとえば「◯◯という事業をホームページで拝見しましたが、実際に新卒が関われる可能性はありますか?」のように、自分で調べた痕跡があって、その先を知ろうとしている姿勢が見えると、逆に好印象になります。
失敗②「それを聞いてどうしたいの?」と思われる質問を聞く
次に逆質問でよくある失敗が、「で、なにが言いたいの?」と思われてしまう逆質問です。
これはつまり、意図が伝わらない質問。
たとえば「飲み会って多いですか?」と聞くと、「なんでそれ聞くの?行きたくないの?それとも行きたいの?」と、面接官がモヤッとしてしまいます。
聞くなら「仕事以外で社員の方と交流する機会があるかをお聞きしたいです。社内の雰囲気を知りたくて」といった具合に、ちゃんと意図を添えることが大切です。
他にも「お昼は皆さんどこで食べてるんですか?」「朝は何時くらいに出社する人が多いですか?」といった質問は、あまり目的がわからない質問ですよね。逆質問のために適当に用意してきたと思われてしまう可能性があります。
失敗③条件面に関する逆質問
そして最後に逆質問に多い失敗が、条件面に関する質問をすることです。
先に例を挙げると、「残業は長いですか?」「休みは多いですか?」「土日出勤はありますか?」「転勤は多いですか?」などの質問ですね。
これらの逆質問を避けるべき理由ですが、条件面ばかり気にしている人だと思われる可能性があるからです。
逆質問はやはり「入社への意欲」を伝えることが大切なので、これらの質問は事前に会社説明会で聞くか、OB訪問をして選考と関係ない場所で聞くのがおすすめです。
ーこれらを踏まえて評価される逆質問とは?
ここまで紹介してきた失敗パターンを避けたうえで、逆に「この人は本気で入社したいと思っているな」と評価されやすい逆質問には、明確な特徴があります。
それは、「目的が伝わる質問」であり、かつ「入社後を見据えている質問」であること。
以下に評価されやすい逆質問の例を紹介します。
→これは内定後を見据えた質問なので、面接官からすれば「もうこの会社に入りたい前提なんだな」と志望度の高さを感じられます。
→活躍している人の特徴を知ることで、自分もそこを目指そうという姿勢が伝わります。「ただ入りたい」だけでなく、「活躍したい」という気持ちが見えることも好印象です。
→会社の未来を知る=自分が長期的に貢献していきたいという意志の表れになります。「将来像」や「長期的視点」が伝わると、評価につながりやすいです。
逆質問で最も避けたいのは、「とりあえず何か聞いておこう」という、逆質問するための逆質問です。
それは、毎日何十人も面接している面接官にはすぐにバレてしまいます。
逆に、どんなにシンプルな質問でも「なぜその質問をするのか」が明確に伝われば、それだけで「考えている人」「真剣な人」という印象を与えられます。
ぜひこれらを踏まえて、入社への意欲の高さを示す、スマートな逆質問を心がけてくださいね。
1人でも多くの就活生が、ありのままの自分を活かして、自分にぴったりの企業に入社できることを祈っています。