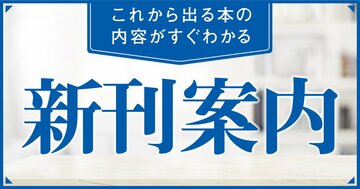シンガポール国立大学(NUS)リー・クアンユー公共政策大学院の「アジア地政学プログラム」は、日本や東南アジアで活躍するビジネスリーダーや官僚などが多数参加する超人気講座。同講座を主宰する田村耕太郎氏の最新刊、『君はなぜ学ばないのか?』(ダイヤモンド社)は、その人気講座のエッセンスと精神を凝縮した一冊。私たちは今、世界が大きく変わろうとする歴史的な大転換点に直面しています。激変の時代を生き抜くために不可欠な「学び」とは何か? 本連載では、この激変の時代を楽しく幸せにたくましく生き抜くためのマインドセットと、具体的な学びの内容について、同書から抜粋・編集してお届けします。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
サプライチェーンの分断がもたらす
大きなリスク
これまでは、遠い国で起こる戦争や紛争は、そこから離れた国々や地域では、さほど深刻な問題になることはなかった。
しかし、自由貿易の結果、サプライチェーン(供給網)が世界全体に分散したおかげで、特定の産品や製品が遠く離れた国に依存していることは珍しくない。
日本は、食糧やエネルギー、製造業に使われる希少金属などを世界中に依存している。
その地で何かが起こって、そこからの供給が途切れた場合、我々の食糧・エネルギー事情や日本の産業に支障をきたし、価格の高騰や企業の倒産などが生じる可能性もある。
ピンチをチャンスに変える
という発想ができるか?
しかし、学びを深めていれば、そのような一般的にはネガティブととらえられるイベントが起こっても、それをチャンスに変えるという発想がでてくる。
今後は、食糧生産は安全保障の一部とされ、日本政府も欧米並みの所得補償を行い、事業としての農業生産の魅力が増すかもしれない。
エネルギーも、日本が技術的に得意とする核融合関連に投資や支援が集まり、日本から技術革新が起こり、日本がエネルギーの一大生産国になるかもしれない。
製造業のサプライチェーンも、円安で価格競争力が増し、自動化技術やAIを活かして、日本での製造が進化するかもしれない。
そうして日本回帰が進んだり、紛争が起こらない場所での資源探索に世界の投資が集まり、資源保有国が多様化することも考えられる。
学んでいれば「ピンチはチャンス」にできるのだ。
未来は過去の延長線上にはないが、人間は過去しか見られない。だから、過去から一つのパターンや、変わらない本質を学ぶしかない。
それを学ぶ技法を本連載では紹介する。
(本稿は『君はなぜ学ばないのか?』の一部を抜粋・編集したものです)
シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授(2022~2026年)。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院(MBA)、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM&A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官(経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権)を務めた。
2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者(29名)を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース(事例)の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。
2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。
CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。