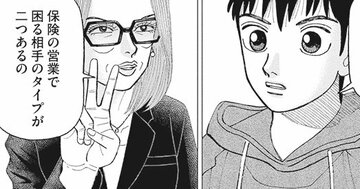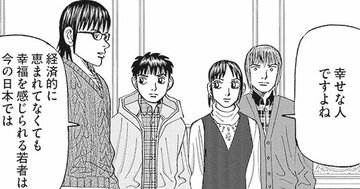ここで注意点もある。ほふりへの開示請求は、決して万能ではない。記載されている情報は口座の有無や加入者口座コードに限定される。銘柄を特定するためには、ほふりの開示請求結果を踏まえて取引のあった証券会社へ開示を求める必要がある。つまり、ほふりだけでは取引を完全には特定できないのだ。
また、開示請求の対象外となる取引も存在する。特に注意すべきは「非上場株式」だ。非上場株式を特定するためには、被相続人の自宅に保管されている株券や配当金計算書、会社からの株主総会招集通知などの書類を確認する必要がある。株主となっていた覚えのある会社に問い合わせを行い、株主名簿への記載の有無を確認する方法も考えられるが、いずれもほふりへの請求と並行して行う必要がある。
相続税申告には期限があるため、ご逝去後の慌ただしい中でも、すぐに相続財産の調査に着手すべきである。とにかく相続財産の調査には「時間と労力がかかる」からだ。開示請求の増加は相続実務に新しい課題も突き付けている。請求件数が増えれば増えるほど、開示に要する時間も相応に長くなり、1カ月以上の待機期間が生じる可能性もある。その間にも相続税申告期限は迫るため、相続人にとって大きなプレッシャーだ。
相続手続きではほふりへの開示請求だけで済むわけではなく、預貯金や不動産などの他の資産調査も同時に進める必要がある点にも注意が必要である。
今だから見直すべき
生前の相続準備とは
生前に相続準備を整えることは、大切な家族による相続手続きの円滑化に直結する。ほふりへの開示請求だけでなく、その他の資産も相続人が手続きを進めやすいように情報を整理・保管しておくことが望ましい。財産の存在を正確に把握できていないことは、相続人同士の不信や争いの火種ともなり得る。
生前準備は単に財産を整理・記録する作業ではない。家族への負担を減らし、余計なトラブルを回避するための「予防策」だと考えてほしい。法的なアドバイスを受けた上で遺言書を作り「見える化」しておくことが望ましいだろう。