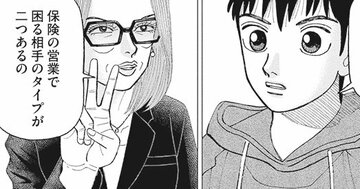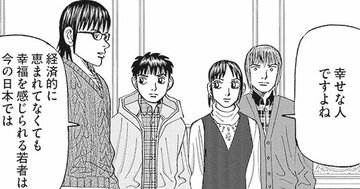資産の金額が大きかったり、種類が多かったりする場合は遺言執行者を指定しておくことも検討できる。遺言執行者とは、被相続人が生前に遺した遺言の内容を相続開始後に実現する役割を持つ人のことだ。相続人同士が揉めることなく分割手続きなどをスムーズに進めることができる。
遺言執行者は法的権限を持つため、相続人間で意見が衝突しそうな場面でも遺言書に沿って公平に手続きを進められる。遺言書は敷居が高いと感じる場合は、エンディングノートの活用もおすすめだ。
ほふりの開示請求の増加から考えるべきは、相続後に資産を探す時代から「生前に見える化する」時代への転換である。相続はいつ発生するかわからないため、準備は早ければ早いほど意味を持つ。
特にオンライン証券や暗号資産のように紙での記録が残りにくい資産については、パスワード管理や情報共有のルールを定めることが望ましい。相続の現場では「存在すら知られていなかった資産」が税務調査や後日の発見で明らかになることも少なくない。今こそ「家族に伝える」ことを前提にした資産管理に移行しよう。
上場株式でも
相続トラブルは起きる
上場株式は市場で流通しており非上場株式よりも評価が容易である。しかし、上場株式でも相続トラブルが発生している点にも注意が必要だ。複数の相続人がいる場合、株式の分割方法には現物分割、換価分割、代償分割といった複数の手法があり、相続人間で調整が必要となる。分割方法を巡って対立するケースは少なくない。
また、被相続人が亡くなった年度の株式譲渡益や配当金については相続開始後から4カ月以内に準確定申告で申告する必要がある。手続きに慣れていない場合は期限を過ぎてしまうおそれがあるため、こちらも注意してほしい。
株式取引や投資信託を楽しんでいる方が多いからこそ、今後は生前の相続準備がますます重要となる。金融資産や不動産を一覧化し、誰にどの情報を伝えるかを明確化することは、家族間のトラブルを防ぐための第一歩だ。
特に株式取引の増加はほふりへの開示請求の負担だけでなく、評価額の変動や相続人間の分割協議の不調など、多岐にわたる相続トラブルの原因となり得る。生前から税理士などの専門家に相談しながら対策を講じよう。