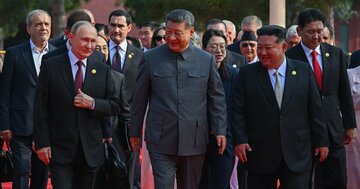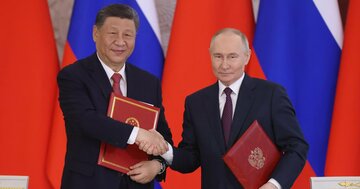だが、もし中央政府がこれまでの拡張主義と国内治安強化の方針を改め、一帯一路、軍拡、国内監視体制強化などを縮小し、そのぶんを地方政府の債務対策に回すのなら、この最大の懸念が払拭(ふっしょく)される可能性がある。
ただし、それはアメリカと並ぶ覇権国家を目指す中国が、その夢を大きく後退させるという代償を伴うものになる。「中国の夢」によって国内をまとめている習近平体制が、本当にそれを選択できるかどうかは疑問だ。
中国を「反面教師」として
日本が覚悟すべきこと
日本は中国から何を学ぶべきか。
第一に、「崩壊を防ぐ力」と「成長を生む力」は必ずしも一致しないという点である。統制によって短期的な安定を確保することは可能だが、その代償として市場のダイナミズムが奪われ、長期的な停滞が固定化される。
壊すべき時には適切に壊さないと、長期的には停滞につながる場合もあると考えられる。
第二に、債務問題は先送りするほど処理コストが膨らむという教訓だ。
日本がバブル崩壊後に不良債権処理を遅らせた結果、長期のデフレに陥ったことは記憶に新しい。中国もまた同じ問題を抱えており、延命策が将来の成長を食いつぶす危険性は大きい。
中国経済は、外貨準備の厚み、家計の高貯蓄、国家資本主義的な統制、製造業の底堅さ、金融資産の事実上の封鎖、さらに社会統制と体制安定という幾重もの防波堤を持っている。
ただし、その実態は、時間を買い続ける延命装置に過ぎない。地方政府債務の膨張、ゾンビ企業の温存、消費拡大の停滞が重なり、中国は「崩壊しないが成長しない」経済に変貌しつつある。
重要なのは、産業の「古さ」と「新しさ」を見極めて、「古さ」をある程度犠牲にしても、「新しさ」を育てることにある。
「中国経済崩壊論」が繰り返し外れてきたのは、中国が強権的な統制によって危機を先送りしてきたからに過ぎない。先送りの繰り返しの果てに待っているのは、日本型の長期停滞か、あるいはソ連型の制度疲労による国力低下のどちらかだろう。
日本は、中国の選択を「反面教師」とし、改革の痛みを受け入れる覚悟が試されている。
(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)