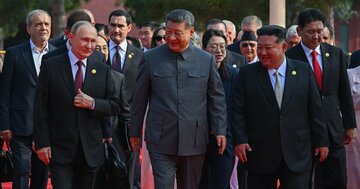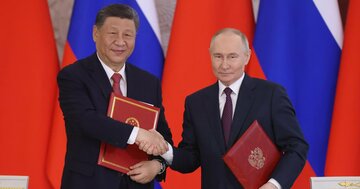第二に、輸出の強さがある。2024年の中国の輸出額は前年比で伸び悩んだとはいえ、なお世界全体のシェアで13%超を占めており、先進国では製造業が強いドイツや日本を大きく上回っている。
特に自動車やバッテリー、再エネ関連製品の分野では急速に存在感を増しており、「価格競争力×量産力」で世界市場を押さえ続けている。
第三に、雇用の受け皿としての役割だ。製造業は中国全体で約1億人の雇用を支えており、農村部から都市部への労働力移動を吸収してきた。たとえ、国内の賃金上昇やAIやロボットによる自動化が進んでも、製造業の雇用吸収力は依然として強い。これが大規模失業による社会不安を防いでいる。
https://www.bls.gov/fls/china.htm
第四に、技術発展の寄与も大きい。半導体における先端分野では制裁で遅れをとっているものの、電池、EV、通信機器など特定分野ではリードしつつある。過剰投資による不良在庫が課題になる一方で、その投資が裾野産業を維持し、国内の需要循環を生み出している面がある。
このように製造業は、債務や不動産の停滞を補い、実体経済をぎりぎりのところで支えている。
ただし、この強さは低価格競争と過剰生産に依存した脆弱な強さでもある。輸出依存が高止まりする限り、米国や欧州による保護主義的な関税措置に脆弱であり、「底堅さ」が一転して「リスク」に転じる可能性がつきまとう。
事実上の「預金封鎖」実施と
デジタル人民元による管理
金融統制の強さも中国経済の特徴である。
戦後の日本では1946年、ハイパーインフレ抑制と財産課税導入のために預金封鎖が行われ、国民の金融資産が強制的に動員された。
中国では同様の劇薬を明示的に発動する必要はない。すでに制度上、緩やかな預金封鎖に近い仕組みが存在しているからだ。
資本取引は厳格に規制され、外貨両替や海外送金には制約がある。銀行はほぼ国有であり、国家が入出金制限を強化するのは制度上容易である。さらにデジタル人民元(e-CNY)が導入されつつあり、資金移動は中央銀行によってリアルタイムで監視可能になっている。
預金封鎖を宣言せずとも、資金の流れを「常時管理」できる体制が整っており、資金移動を禁じることで、事実上の預金封鎖に近い効力を発揮させている。
人民元は国際化が限定的であるため、こうした統制の影響は主に国内にとどまる。