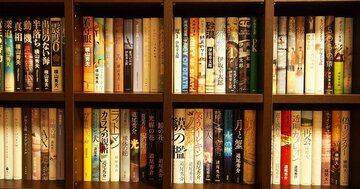「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか?
その名は――ピーター・ドラッカー。
彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。
『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
リーダーが「絶対に」やってはいけないこと
――リーダーになる人が「絶対にやってはいけないこと」はありますか?
吉田麻子(以下、吉田):ドラッカーは、成果をあげるリーダーは「私は」ではなく「われわれは」を考えるといいます。
裏を返せば、“自分中心”になることこそ、リーダーが最もやってはいけないことです。
リーダーが「自分はどう見えているだろう」「自分の手柄にしたい」などと、自分先行の意識になりそうだとしたらそれは危険信号です。
たとえば、「自分の魅力でメンバーの気持ちを惹きつけよう」という気持ちが混入してしまいそうなときは要注意です。
ドラッカーはリーダーシップにカリスマ性はいらないといっています。『プロフェッショナルの条件』にはこうあります。
ドラッカーによる「カリスマ否定」
「今世紀におけるスターリン、ヒトラー、毛沢東の三人組ほど、カリスマ的なリーダーはいなかった。だが彼らは、史上かつてない悪行と苦痛を人類にもたらした似非リーダーだった」
「リーダーシップは、カリスマ性に依存しない」
「カリスマ性はリーダーを破滅させる。柔軟性を奪い、不滅性を妄信させ、変化不能とする」
では、リーダーシップの本質とは何か
吉田:では、カリスマ性が不要だとしたら、リーダーシップの核心はどこにあるのでしょうか。
続く文章でドラッカーはリーダーシップの本質として三つの要件をあげています。
【1】リーダーたることの第一の要件:リーダーシップを仕事と見る
「効果的なリーダーシップの基礎とは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に定義し、確立することである。リーダーとは、
・目標を定め、
・優先順位を決め、
・基準を定め、
・それを維持する者である。
もちろん、妥協することもある」
・目標を定め、
・優先順位を決め、
・基準を定め、
・それを維持する者である。
もちろん、妥協することもある」
「リーダーと似非リーダーとの違いは目標にある。政治、経済、財政、人事など現実の制約によって妥協せざるをえなくなったとき、その妥協が使命と目標に沿っているか離れているかによって、リーダーであるか否かが決まる」
雰囲気や口先だけの演出だけでは立ち行かない部分に言及していますね。
そして、いざ妥協をしなければならなくなったとき、よりよい道を示せるかどうかで真のリーダーであるかどうかが問われます。
まるで、目的地を指さす荒波の中の船長のようですね。自分語りばかりで仕事が中途半端な船長だと、不安になってしまいますね!