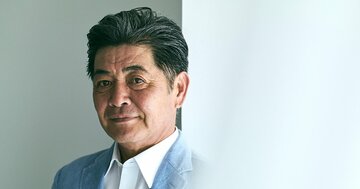ピッチャーのバント処理後のセカンドスロー、サードスロー、ホームへのグラブトスなど、投内連携プレーにもいろいろありますが、この一塁ベースカバーはピッチャーにとって基本中の基本の動きといっていいでしょう。
一塁ベースカバーにおいて、一番大切なのは、「ピッチャーは自分の左側に打球が飛んだら、すべてファーストに向かってスタートを切る」ということです。このひとつの動きを怠ることで内野安打が生まれ、エラーが生まれ、そこから失点につながり、最終的にチームは負けることになります。
「ピッチャーのエラーは点に結びつきやすい」と野球界ではよく言われます。それを防ぐためにも、単調な動きの連続でつまらないかもしれませんが、投内連携の練習は徹底して行わなければならないのです。
日々の反復練習が
スーパープレーを支える
私が西武ライオンズにいたときの春季キャンプでは、この投内連携プレーの練習を毎日2時間行っていました。広岡監督(編集部注/広岡達朗。1982、83年にライオンズを日本一に導く)から言われたのは、「一塁ベースカバーはベースを見ずに踏めるように」ということです。入団したばかりの私は「そんな曲芸みたいなこと、できるわけない」と思いました。
しかし、基本の動きを何度もこなしていくと、ベースを見なくても感覚だけでベースの近くにまで行けるようになりました。
そしてキャンプ終盤のある日、感覚で足を出すとそこにベースがありました。最初は曲芸のように思えた動きも、毎日数多く練習を繰り返すことでできるようになるのです。この一塁ベースカバーの技術が、シーズン中に訪れた危機を何度も救ってくれました。
野球を経験した人、ピッチャーをやったことのある人であれば、自分の左側に打球が飛んだら一塁に向かってスタートを切るということは誰でも知っています。プロのピッチャーもみんな「そんなことはわかっていますよ」と言います。