「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
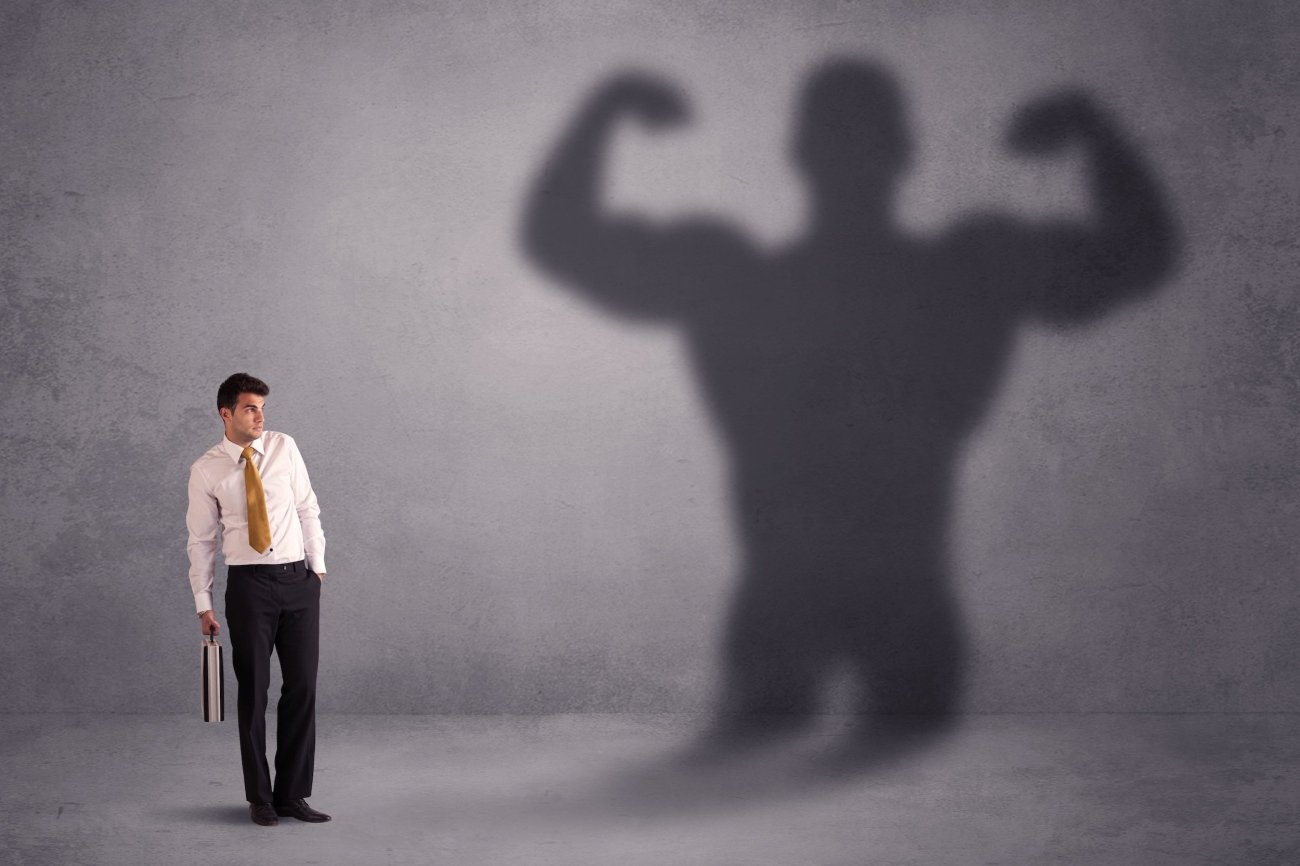 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
即戦力のつもりが「現場を混乱させる人」の特徴
「即戦力として期待しています」
採用の現場ではよく聞く言葉ですが、実際に現場で混乱を巻き起こすのは、まさに「即戦力っぽい人」であるケースが少なくありません。
本当に「使える人材」とは何か。
今回は、「即戦力」を自称しながら現場に悪影響を与えてしまう人の特徴を掘り下げます。
「前職でのやり方」にこだわりすぎる
こうした人は、新しい環境でも前職のやり方を持ち込み、「それ、以前の会社ではこうやってました」と主張しがちです。
一見、経験に基づく合理性があるように聞こえますが、現場の文脈やチームのバランスを無視して導入すれば、むしろ混乱の原因になります。
「成果を出していた自分」が忘れられず、適応よりも「矯正」を優先してしまうのです。
質問をせず、自分だけで突き進む
「すぐに結果を出さねば」というプレッシャーからか、周囲と対話することなく、勝手に進めてしまうタイプも危険です。
社内の意思決定フローや合意形成の文化を無視した動きは、信頼関係を壊し、周囲に「暴走している」と映ります。
短期的な成果を出しても、長期的には孤立するリスクが高まります。
自分の「即戦力ぶり」をアピールしすぎる
「これくらい、すぐできます」「私ならこうします」といった自己アピールを頻発する人も要注意です。
本人は「頼れる存在」を演じているつもりでも、周囲からは「自分勝手で協調性に欠ける」と見られることも多く、チームワークの崩壊につながります。
本当に即戦力な人は「まず聞く」
本当に優秀な人ほど、まず現場のやり方を丁寧にヒアリングし、「どこを改善できるか」「何を壊さずに貢献できるか」を慎重に見極めます。
即戦力とは、「いきなり走る人」ではなく、「まず状況を把握してから動ける人」なのです。
(本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです)
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。










