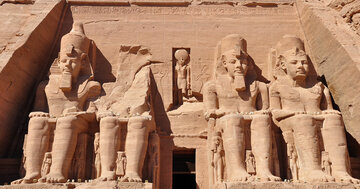古代エジプトと他の古代文明との差は、文化水準と庶民の教育に対する関心の高さにあった。古代エジプト人の教育に対する姿勢は、「ドゥアケティの教訓」のなかで象徴的に述べられていると言えよう。この文学作品は、ドゥアケティという名前の一庶民が、彼の息子ペピを書記の養成学校に入学させるために船で都へ向かう道中で語った話である。どれほど書記が良い職業であるのかを他の職業と比較しながら語るのだ。金属細工師も陶工も農夫という仕事も、どれほど過酷でつらく厳しいものであるかを語るのである。
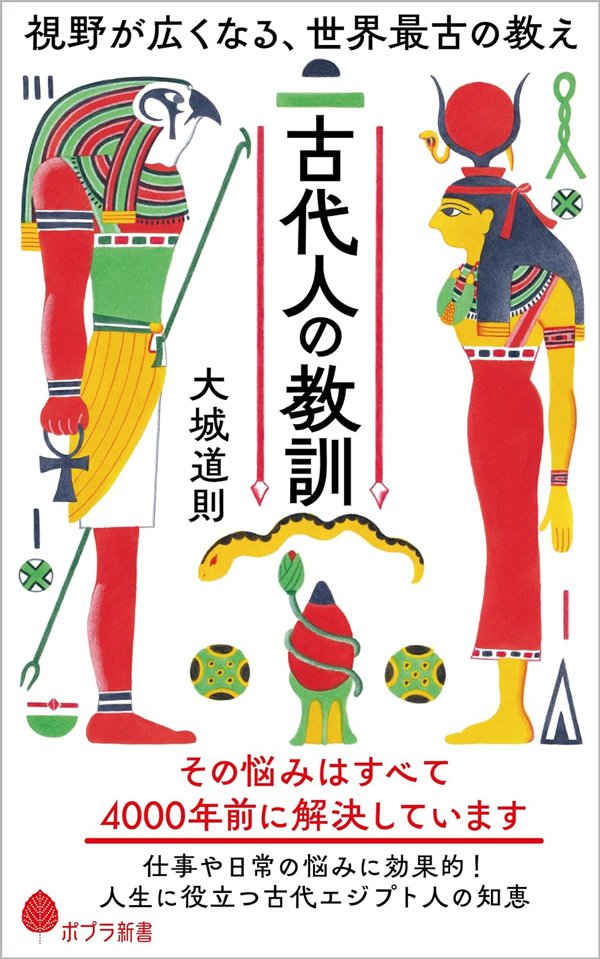 『古代人の教訓』(大城道則、ポプラ新書)
『古代人の教訓』(大城道則、ポプラ新書)
「ドゥアケティの教訓」は、風刺文学として興味深いのであるが、それ以上にここからは中王国時代の社会背景が読み取れる。当時のエジプトは、古王国時代から続く世襲の貴族たちが国の運営を担っていた。しかしながら、彼らの持つ既得権益は王権側を圧迫していたのである。そこで広く庶民からも優秀な人材を集め、官吏に登用する政策が取られ始めたのだ。確かに「ドゥアケティの教訓」は、書記養成学校の教科書であったが、国の生き残りをかけての政策の一環であり、また「成り上がり」を目指す者たちのバイブルでもあったのである。