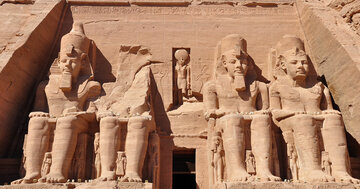古代エジプトにおける食事の内容は、大方社会的地位により決まっていた。ローマ時代には「ローマ帝国の穀倉庫」と呼ばれたほど、農作物に恵まれていたエジプトでは、ナイル川の水を利用した豊かな農業によって、豆類(エンドウ、サヤエンドウ、レンズマメなど)や果物(イチジク、ナツメヤシ、ブドウなど)も食されていた。またエジプトはナイル川と地中海・紅海に接することから、魚をはじめとした水産物も豊富に獲れた。そのため我々が想像する以上の豊かな食生活を送っていたようだ。
それ以外のタンパク質は、乳製品(ミルク、バター、チーズなど)や家禽(アヒルおよびガチョウとその卵)によって摂取された。食肉(豚肉、羊肉、牛肉)もあったが、庶民にとっては、祝祭・祭祀の際に食す機会があったくらいで、主に王族をはじめとしたエリートのための贅沢品であった。例外としてピラミッド建設に従事した労働者たちは(ピラミッド建設のために集められ、専用の区画に暮らしていた)、牛肉を食べるなど豊かな食生活を謳歌していたことが知られている。
しかしながら、その一方でビールの飲みすぎが問題視されていたことがこの格言からもよくわかる。「ビールを二杯飲んでも身体がさらにそれらを欲しがったら、その欲求と闘いなさい」からは、対象人物がアルコール依存症ではないかと疑うほどだ。
庶民が努力でエリート階級に
「成り上がり」ができる時代
「ドゥアケティの教訓」は、中王国時代第12王朝の作品と考えられており、それ以後の新王国時代にも影響を与えた。その内容からは、エジプトにおける教育が庶民たちにとって最重要課題のひとつであったことがわかるのだ。実際、古王国時代には王宮を除けば、学校の存在は明確ではなく、第一中間期から知られるようになるのである。第一中間期とは、ピラミッドを象徴とするような安定と繁栄を誇った古王国時代が終わり、社会的混乱期が到来した時代であった。その混沌とした時代の後にエジプトは官僚組織の復活を目指すのである。そこで重用されたのが教訓文学であり、なかでもその代表が書記養成学校の教科書となった「ドゥアケティの教訓」なのである。