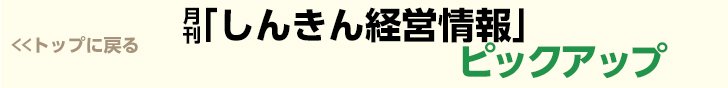──現在の事業内容をお聞かせください。
東海 20歳で漁師になり、今も現役で漁をしています。そこから発展する形で2018年に会社を設立。さまざまな事業を行っています。その一つが水産物の加工・販売です。中でも力を入れているのは、ノドグロやヤナギバチメ、スルメイカなどを干物にした「越(こし)のひもの」です。
ちまたで売られている干物の多くは冷凍保存した魚を原料に使っていますが、弊社はその日に水揚げされたばかりの、刺身でも食べられる鮮度の高い魚を原料にし、その魚本来の味をしっかり味わえるよう、塩分も控えめにしています。だから、焼いたときに、鮮度のよい焼き魚のような味わいが楽しめるのです。
──なぜ干物を作り始めたのですか?
 代表取締役社長・東海勝久(とうかい・かつひさ)氏。1975年富山県氷見市生まれ。95年より漁師として水産業に従事し、2004年に個人で東海水産を開業。18年IMATOを起業。水産加工、観光事業、さばき方教室など、多岐にわたる事業を展開する。
代表取締役社長・東海勝久(とうかい・かつひさ)氏。1975年富山県氷見市生まれ。95年より漁師として水産業に従事し、2004年に個人で東海水産を開業。18年IMATOを起業。水産加工、観光事業、さばき方教室など、多岐にわたる事業を展開する。
東海 きっかけは、主婦の方から依頼されて魚のさばき方教室を開いたときに、「日持ちして簡単に調理できるおいしい魚が欲しい」「魚嫌いの子どもが食べられる魚はないか」と言われたことです。
干物は日持ちしますが、魚臭く塩辛いので、苦手な子どもが少なくありません。そこで鮮度のよい魚を干物にして塩分を抑えれば食べてもらえるのではと考えたのです。子どもたちに試食してもらうと、取り合って食べていて、手応えを得ました。干物作りのノウハウを一から学び、研究を重ねたかいがありましたね。
──食育にもつながるというわけですね。
東海 さまざまな水産物を干物にしていたら、偶然、日本初の商品も生み出せました。富山湾産の紅ズワイガニを干物にした「越の干蟹(ほしがに)」です。実はカニの干物は世の中にありそうでなかったのです。富山県食品研究所と共同研究し、製法特許も取得。今年2月には県産品の中から30品目しか選ばれない「富山県推奨とやまブランド」に認定されました。そのまま食べてもよいですし、かに飯の具材やパスタのトッピングでも楽しめます。