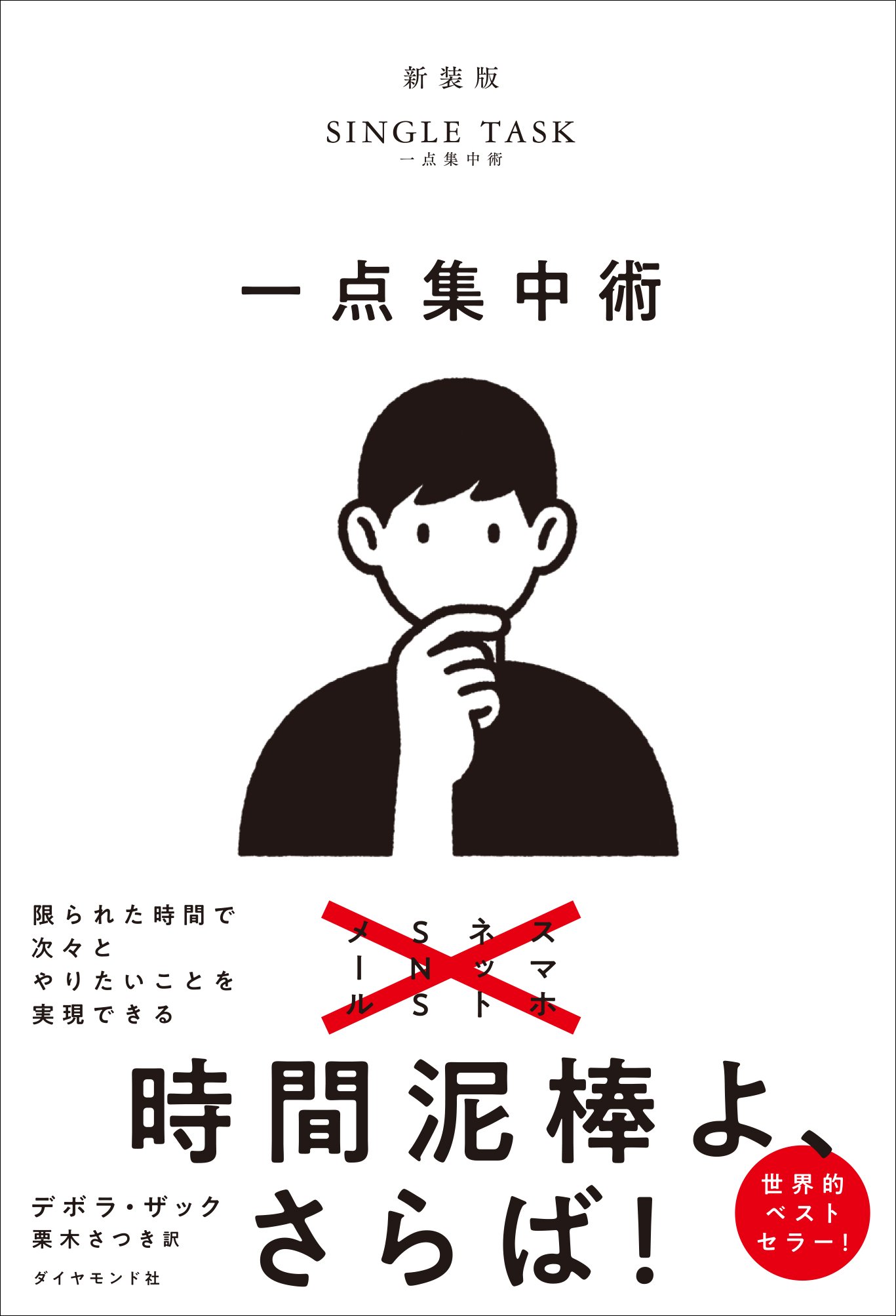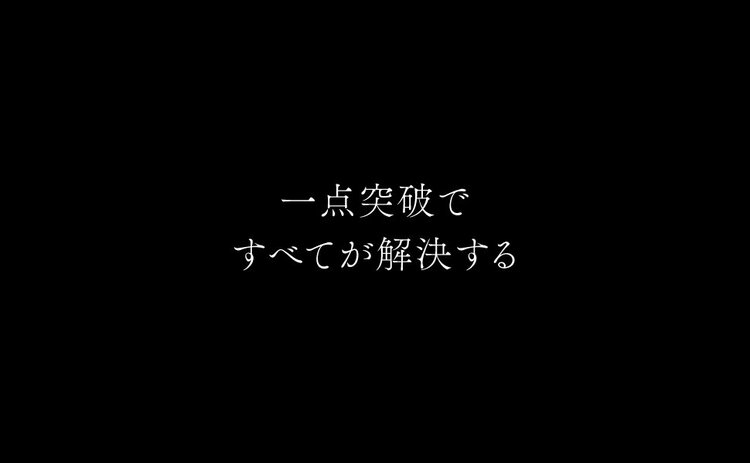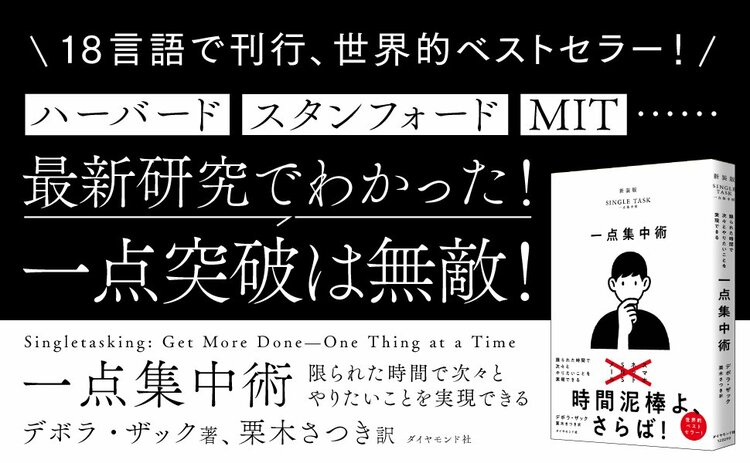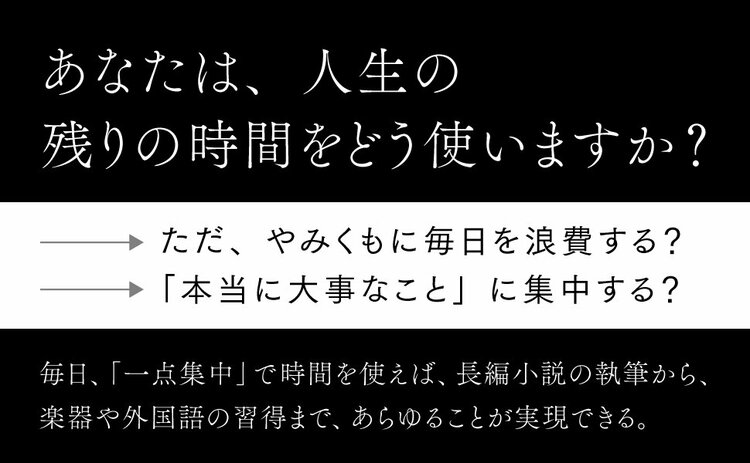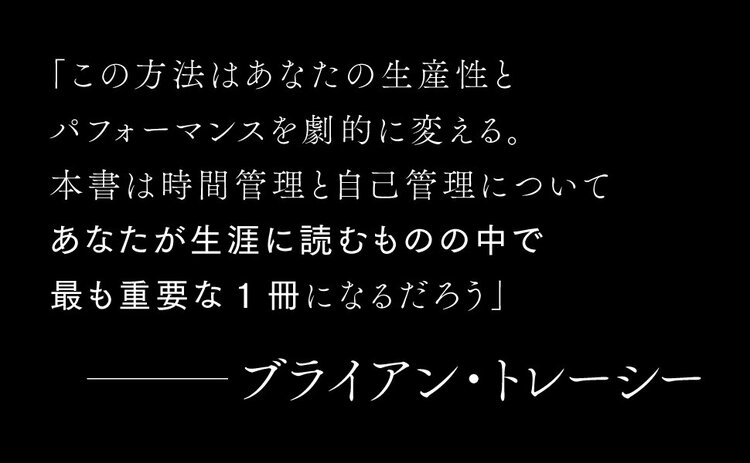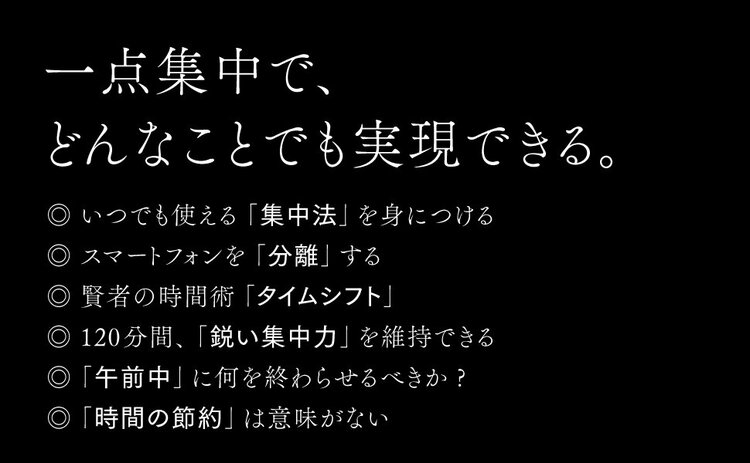SNS、ショート動画の無限スクロール、YouTube……。刺激にあふれる現代では、油断していると「人生の時間」がいつのまにかどんどん過ぎていってしまう。そんないま求められるのが「一点集中」の力だ。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』について、訳者の栗木さつき氏に話をうかがった。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
脳は「目新しいもの」が大好き
――『一点集中術』では、脳は同時に複数のことを処理できないということが繰り返し強調されています。たしかに私自身、ポッドキャストを聴きながらスマホを触ってメールやSNSを見たりすることがあるのですが、気がつくとその間のポッドキャストの内容は何にも頭に入っていません。
栗木さつき氏(以下、栗木):脳がちゃんとフォーカスを切り替えてくれているんですよね。何か1つのことをしているとき、ほかのタスクに集中することはできません。脳にとって「2つのタスクのあいだで『干渉』が生じる」からだと著者は説明しています。その意味では、環境として周囲に刺激があればあるほど集中は難しくなります。
――考えてみると、いまの若い人たちは受験勉強でも気が散るものだらけで大変ですよね。
栗木:はい、大変だろうなと思います。「人は目新しいものに注意を向けてしまう」とも書かれていますが、SNSやメールの通知なんかがくると、脳はそっちに飛びつきたくなるんですよね。昔はテレビくらいしかなかったのに、いまは集中を邪魔するものにあふれています。
また、マルチタスクが学習に深刻な悪影響を与えているという話も出てきます。以下はその部分の引用です。
ハーバード大学の研究によれば、注意を分散させていると、情報を記号化しにくくなる。すると記憶力が低下し、何も思いだせなくなる事態も生じる。
いわゆる「マルチタスク」行為は「認知処理能力を低下させ、より深い学習を妨げる」のだ。――『一点集中術』より
邪魔者から身を守る「フェンス」とは?
さらに、現代人は「四六時中、何の役にも立たない情報の砲撃を受けている」という指摘もありました。SNSを見ていると、自分が見たくもない情報や、知りたくもない人の悪意まで入ってきてしまい、ネガティブな感情が高まるという悪循環が生じてしまいます。見たくないものを遮断するのが難しくなっているように思います。
――そうした悪循環から逃れるには、何かしら自衛するしかないですよね。
栗木:そうですね。本の中では「フェンスを立てなさい」と表現されていますね。
だが私にも、そんな強さはない。目の前に、揚げたてあつあつのチーズソースがけフライドポテトを置かれたら、一つ残らず食べてしまうだろう。とはいえ、それが魔法のように目の前に出現しないかぎり、べつにフライドポテトなど食べなくても1日をすごすことはできる。(中略)
誘惑に打ち勝つのは、並大抵のことではない。だから、誘惑はつぼみのうちに摘みとってしまおう。「邪魔物」の侵入を防ぐために「フェンス」を設けるのだ。——同書より
「自分は大丈夫」「今日はダメだったけど明日は頑張れる」と根拠なく思って、誘惑の源泉を身のまわりに置きつづけてしまうのが誘惑に弱い人の特徴です。スマホだったら集中したいときは「隣の部屋に置く」だとか、スナックだったら「そもそも家に置かない」とか、誘惑にさらされないために物理的な障壁をつくることが必要です。
人間の意志は案外当てになりません。「誘惑に強い人」というのは、そんな現実をわきまえてしっかりと環境を整えられる人のことなんです。
(本記事は、デボラ・ザック著『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』の翻訳者インタビューです)