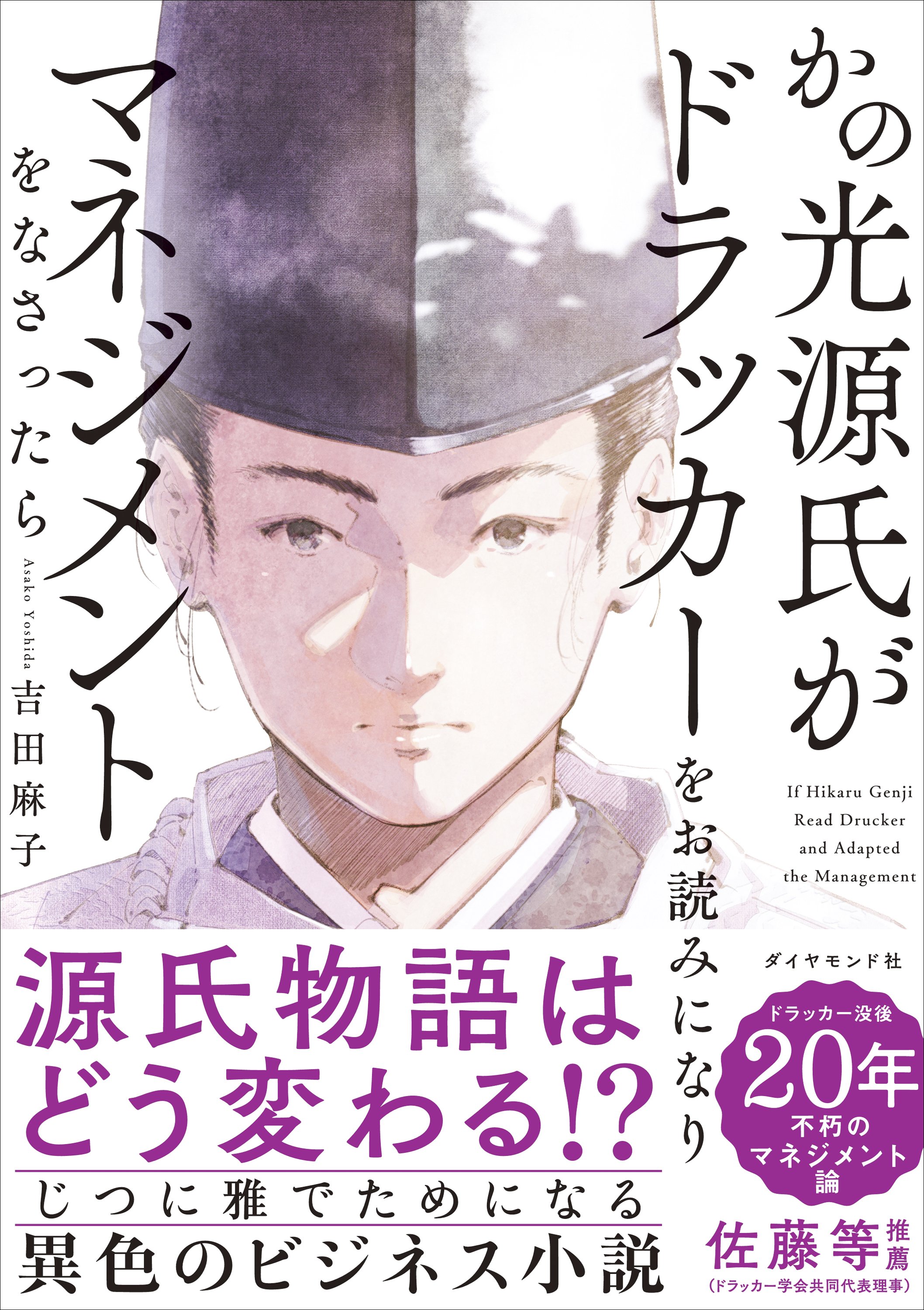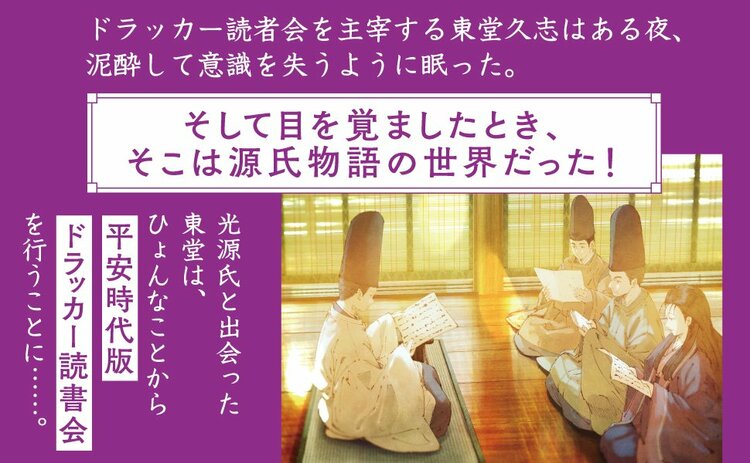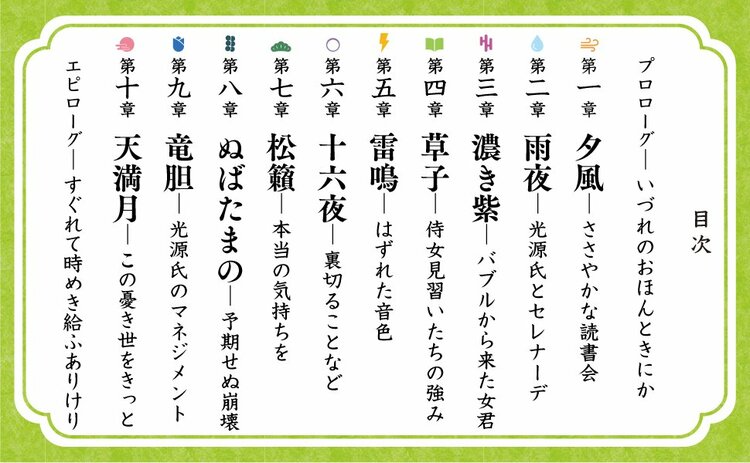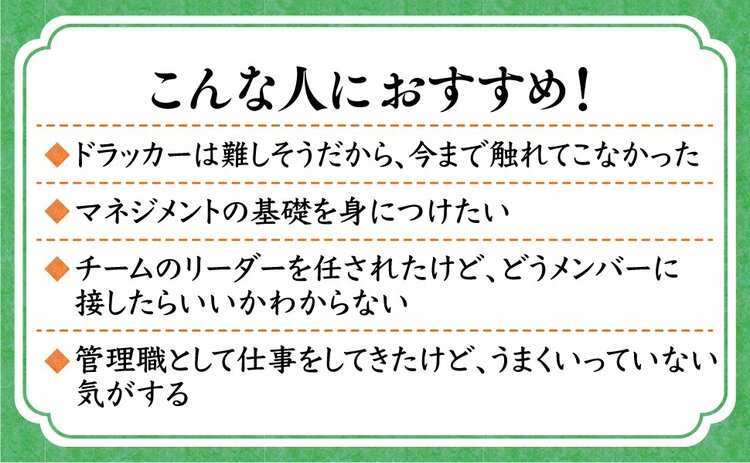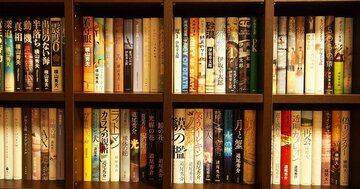このあとに「貢献に焦点を合わせるということは、責任をもって成果をあげるということである」という言葉が続きます。
つまり、組織のミッションは何であり、求める成果が明確になっているうえで、そのために何をなすかという視点に立って組織をマネジメントしていくことこそが、マネジャーの責任であるといえます。
年上の部下にどう向き合うか
――それでも年上の部下には接しにくいと感じる場合、どう考えたらよいでしょうか?
吉田:ドラッカーは『明日を支配するもの』で、
「自らの果たすべき貢献は何かという問いからスタートするとき、人は自由となる。責任をもつがゆえに自由となる」
といっています。
年上の部下がいることで肩身が狭く感じたり、自由度が低く感じる前に、そもそも権限をもって組織の成果に貢献すべく、メンバーのなすことを導いていくことが自由な状態であることを認識する――。
そのように考えると、眼前の風景が変わって見えるかもしれません。
人間的な尊敬の念を忘れてはならない
吉田:そうは言っても年上の部下に接するときには相手に人間的尊敬の念が払われていることもまた重要なことです。
ドラッカーは『マネジメント(上)』で「仕事のうえでの人間関係は尊敬に基礎を置かなければならない」ともいっています。
たとえばこちらの話す言葉が通じないような世代間のギャップなども生じるかもしれません。
ドラッカーは『マネジメント』の中で、ソクラテスの言葉「人と話すときは相手が経験的に知っている言葉、つまり大工と話すときは、大工の言葉を使え」を引用し、「コミュニケーションは受け手の言葉を使わなければ成立しない。受け手の経験に基づいた言葉を使わなければならない」としています。
年上の部下だからこそ知っている、豊かな経験と知識による可能性を引き出すことは組織の成果にとってとても有益なことになるでしょう。
大切なのは、年上であるかどうかではなく、ともに成果に貢献する仲間として尊敬と責任をもって接することといえるのではないでしょうか。