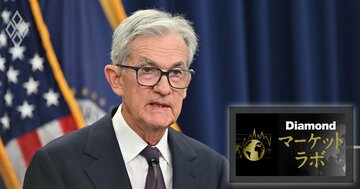Photo:Drew Angerer/gettyimages
Photo:Drew Angerer/gettyimages
パウエルFRB議長は9月の講演で株価の高水準に言及し、10月FOMCでの利下げは「データ次第」と述べた。7月会合では株価収益率(PER)や社債スプレッドの過熱に警戒が示され、9月には国際決済銀行(BIS)も、世界的なリスク・オン持続に懸念を表明。だがトランプ政権は大幅利下げを迫り、中央銀行の独立性を揺さぶっている。独立性が崩れた先に何が起こり得るのか。その一端はトルコの経験が物語り、日本銀行にとっても決して人ごとではない。(東短リサーチ代表取締役社長 加藤 出)
パウエル議長が語った「株価の過熱感」
BISレビューが示した懸念とは
「われわれ(FRB=連邦準備制度理事会)は特定の金融資産の価格水準にターゲットを持っていない」「しかし多くの尺度から見て、株価はかなり高く評価されている」
9月23日の講演会で株式市場に関する質問を受けたパウエルFRB議長は、そう答えた。
この発言には伏線がある。連邦公開市場委員会(FOMC)では、スタッフが四半期ごとに金融システムの状況を評価している。連邦準備法がFRBに課す使命は「雇用の最大化」と「物価の安定」の両立であり、株式など資産市場の過熱に直接対応することは原則ない。ただし、その二つの使命を実現する上で、金融システムの安定は間接的に重要な要素となる。
実際、7月のFOMCでは「株式市場の株価収益率(PER)が歴史的な上限に位置している。ハイ・イールド社債のスプレッド(米国債との金利差)は著しく縮小し、「歴史的に低い状態にある」との警戒感が示されていた。その後、米国株はさらに上昇しているだけに、パウエル議長が冒頭のようなコメントを発しても不思議はなかったといえる。
国際決済銀行(BIS)も9月15日に公表した四半期レビューで、世界的なリスク資産の過熱に対して、次のように懸念を表明した。