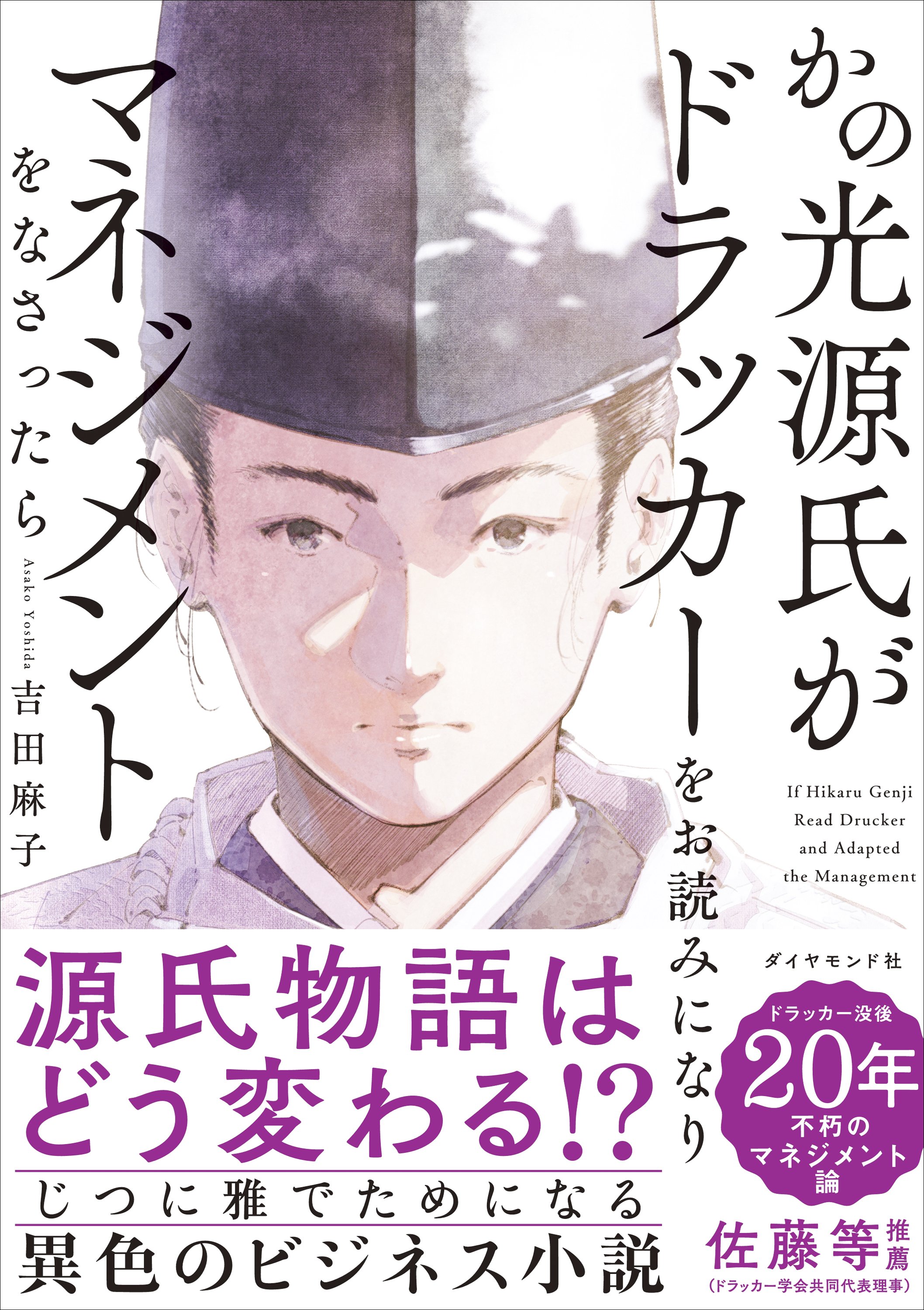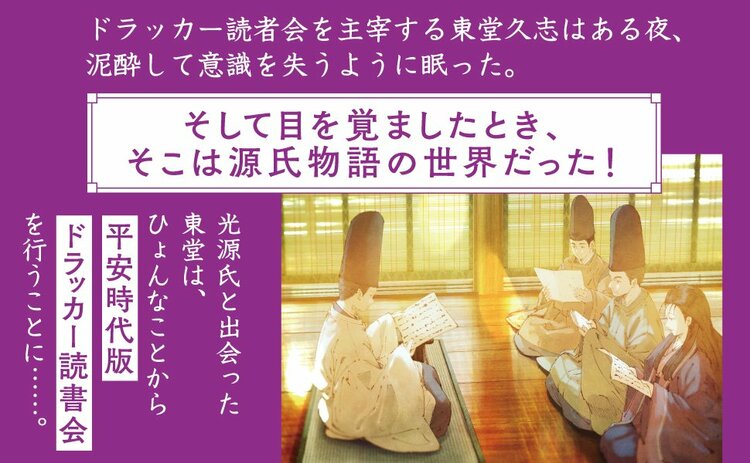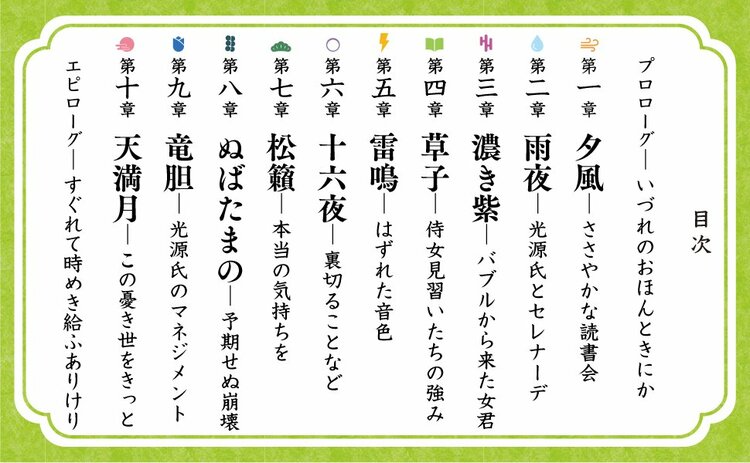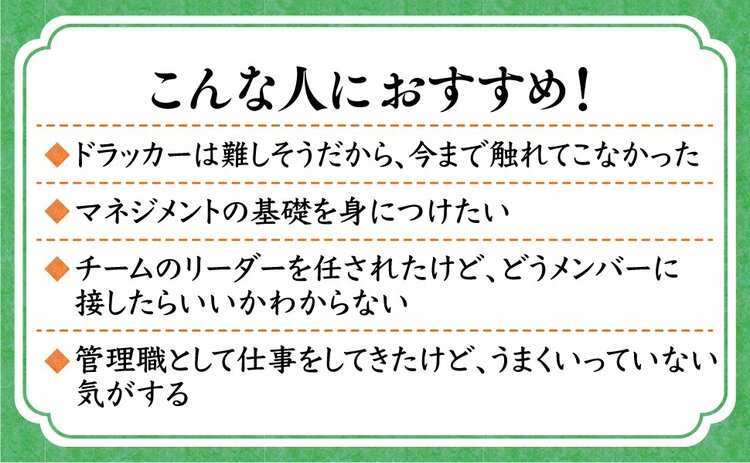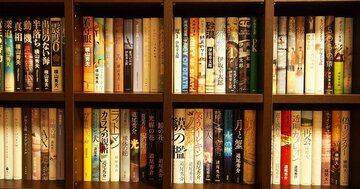成果をあげる五つの習慣的能力
吉田:以下、同書より引用します。
(1) 何に自分の時間がとられているかを知ることである。残されたわずかな時間を体系的に管理することである。
(2) 外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである。仕事ではなく成果に精力を向けることである。「期待されている成果は何か」からスタートすることである。
(3) 強みを基盤にすることである。自らの強み、上司、同僚、部下の強みの上に築くことである。それぞれの状況下における強みを中心に据えなければならない。弱みを基盤にしてはならない。すなわちできないことからスタートしてはならない。
(4) 優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中することである。優先順位を決めそれを守るよう自らを強制することである。最初に行うべきことを行うことである。二番手に回したことはまったく行ってはならない。さもなければ何事もなすことはできない。
(5) 成果をあげるよう意思決定を行うことである。決定とは、つまるところ手順の問題である。そして、成果をあげる決定は、合意ではなく異なる見解に基づいて行わなければならない。もちろん数多くの決定を手早く行うことは間違いである。必要なものは、ごくわずかの基本的な意思決定である。あれこれの戦術ではなく一つの正しい戦略である。
(2) 外の世界に対する貢献に焦点を合わせることである。仕事ではなく成果に精力を向けることである。「期待されている成果は何か」からスタートすることである。
(3) 強みを基盤にすることである。自らの強み、上司、同僚、部下の強みの上に築くことである。それぞれの状況下における強みを中心に据えなければならない。弱みを基盤にしてはならない。すなわちできないことからスタートしてはならない。
(4) 優れた仕事が際立った成果をあげる領域に力を集中することである。優先順位を決めそれを守るよう自らを強制することである。最初に行うべきことを行うことである。二番手に回したことはまったく行ってはならない。さもなければ何事もなすことはできない。
(5) 成果をあげるよう意思決定を行うことである。決定とは、つまるところ手順の問題である。そして、成果をあげる決定は、合意ではなく異なる見解に基づいて行わなければならない。もちろん数多くの決定を手早く行うことは間違いである。必要なものは、ごくわずかの基本的な意思決定である。あれこれの戦術ではなく一つの正しい戦略である。
これらがドラッカーのいう「成果をあげる5つの習慣的能力」であり、これらは反復によって修得できるわけです。
「できないこと」に焦点を合わせるのは“無責任”
吉田:ここで書かれていることはセルフマネジメントの内容であり、マネジャーは自分の部下に対して組織のマネジメントを行う必要がありますが、まずは「人の強みを生かす」ということそのものが、修得できる習慣的能力であり、他の4つと連動することによって考え方の土台をなすものであるということになります。
その上でドラッカーはこう言っているんです。
「上司は部下の仕事に責任をもつ。部下のキャリアを左右する。したがって、強みを生かすことは成果をあげるための必要条件であるだけでなく、倫理的な至上命令、権力と地位に伴う責任である。部下の弱みに焦点を合わせることは、間違っているばかりか無責任である」
リーダーは部下一人ひとりの強みを可能な限り見出して生かしていくという責任があり、彼らがその強みを通して物事をなすことができるようにしていくことが必要であるというのです。
人はどうしても「どうしてこんなことも出来ないんだ」「何回言ったら直すんだ」と弱みに意識を向けがちです。けれどもドラッカーは「強みに焦点を当てよ」と説きました。
この思考の習慣は、反復によって変えることができます。掛け算の九九を覚えたときのように、最初はぎこちなくても、繰り返すうちに自然に「この人の強みはどこだろう」と考えるようになるのです。
九九は最初は難しくても、繰り返すうちに自然と口から出てくるようになりますよね。
「強みを生かす」という習慣的能力も同じです。成果をあげるリーダーの大切な能力です。
ぜひ今日から、目の前の部下の強みに目を向けてみてください。