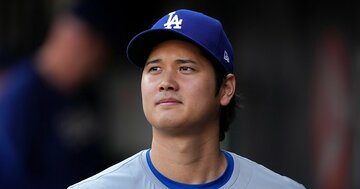当時、投手コーチだった伊藤智仁コーチは、投手陣の疲労軽減を最優先したローテーションを組みました。先発は中6日以上空けることが多く、リリーフの連投も少なくしました。
投手力が弱ければいい先発投手の間隔を詰めて起用したくなるし、リリーフであれば力のある投手を連投させたくなります。伊藤コーチの起用は、これまでの常識とは逆の発想と言っていいでしょう。
最初はただでさえ力の劣る投手陣を甘やかしているように見えました。
そこで同級生で仲のいい伊藤コーチに聞いてみると、「ウチのピッチャーは他のチームより力が劣るやろ。ただでさえ力が足りんのやから、間隔を空けて元気な状態で投げさせないといかんのや」と話していたのを鮮明に覚えています。
それでも個人的には力のない投手を甘やかしていたら、よくなるものもよくならないのでは?という疑問がありました。
しばらく様子を見ていたのですが、確かに元気いっぱいで投げる投手陣は、自分の力を十分に発揮します。もともとの能力が、疲労のせいで発揮できなかったのかもしれません。
私は半信半疑でしたが、伊藤コーチには最初からこのやり方でうまくいくという根拠があったようです。投手の元気がいいときのスピード、ボールの回転数や回転軸などを見て、悪くなる前の兆候を探したそうです。多くの投手は疲労が原因で、そうした数値が悪くなるそうです。
ホークアイ(編集部注/球場に設置した複数の高性能カメラでボールや選手の動きを捉え、これをデータ化するシステム。日本のプロ野球ではヤクルトスワローズが最初に採用し、2024年には全球団が導入を終えた)など最新機器で出せるデータの数値が大好きな伊藤コーチだからこそ、発見できたのでしょう。私自身もそうしたデータは大好きですが、改めてその重要性を認識しました。
1点差と3点差では
投げる疲労度は段違い
投手陣の立て直しに成功したのは伊藤コーチのお陰ですが、忘れてはいけないのが、優勝の根底には強力打線という土台があったことです。