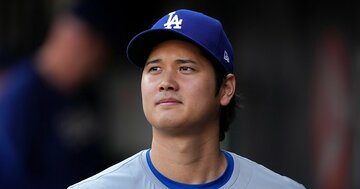持ち前の強力打線が長打力で大量得点を奪い、投手に余裕を与えます。投手陣の負担が減るから、元気な状態で投げさせられます。これが貧打でいつも接戦になれば、いくら伊藤コーチが疲労を考慮してもやり切れなかったかもしれません。
好循環で戦えるようになり、2年連続最下位のチームが、連覇を達成したのだと思います。
メジャーの投手起用も、疲労との向き合い方が重視されるようになっています。
先発、中継ぎ、抑えという分業制は、メジャーが先駆けです。中継ぎ投手は開幕当初は連投をせず、少し経ってから連投はさせますが、3連投などはシーズン終盤までほとんどやりません。
先発投手も開幕して2ヵ月ぐらいは、中6日か5日です。
シーズン中盤になって中4日になり、ポストシーズンでは中3日で投げる先発投手が出てくるといった感じです。
ここで注目したいのは、現在では球数やイニング数よりも、何点差で投げたかを疲労度として考えている点です。
同点や僅差の1点差ゲームと、3点差や5点差がついた試合では、投手の疲労度が違います。それを考慮して先発の間隔やリリーフの連投を決めるというやり方です。
明確に実践しているチームがどれぐらいあるかは分かりませんが、今後はどんどんマニュアル化が進んでいき、明確になってくると思います。
こうしたマニュアルは、比較的簡単に真似できます。ヤクルトの投手起用も、今では他球団が真似をしています。間隔を空けて先発させるのも、リリーフを3連投させないのも当たり前になっています。
こうなってくれば、試合序盤での大量得点は、さらに重要度が増すのではないでしょうか。
守備的なスタメンでは
試合展開に対応できない
「守備型」の選手だった私は、ヤクルトでのコーチ時代、意外に思われるかもしれませんが、「得点力」を重視した打線を組むのが好きでした。もちろん、所属するチームの特性によって変わりますが、その理由を説明します。