新幹線の「高速化」は運転面だけではなかった。国鉄は1950年以降の10年間で予約座席数が10倍に増加したことを受け、中央装置と窓口端末をオンラインで接続し、予約と発券を高速処理するMARSの開発に着手。1960年に試作機の実用試験を開始し、1964年に在来線で実用化。1965年10月1日に新幹線にも拡大した。
MARSの導入前、指定席予約は列車ごとの紙の台帳で管理しており、駅は電話で問い合わせて空き座席を確認し、手作業で発券していた。加えて、新幹線は要員が定数を下回るなど開業準備が不足しており、駅窓口は長蛇の列となって苦情が殺到した。それがMARS導入でスムーズに予約可能になった。
開業時に1日30本(「ひかり」14本、「こだま」16本)だった列車本数は、1965年10月に43本(「ひかり」20本、「こだま」23本)、同年11月に55本(「ひかり」26本、「こだま」29本)まで増便されたが、実現の背景にはMARSの存在があった。
また、開業時は「ひかり」「こだま」とも全列車全席指定席だったが、1965年10月1日から「こだま」に自由席を導入し、短・中距離利用者が気軽に乗車できるようになった。これもスピードアップの一環と言えるだろう。
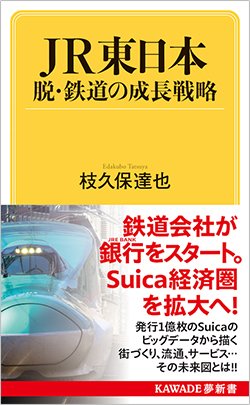 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
こうして本格運行を開始した東海道新幹線だが、高速運転の負荷は想定以上だった。開業10年を迎えた1974年頃から故障が急速に増えはじめたことから、同年12月から翌年3月にかけて午前中の列車を全面運休して「臨時総点検」を実施。結果を受けて1975年から1982年にかけて、車両更新、レール更新、路盤強化、電気設備強化など、運休を伴う「若返り工事」を推進した。
次なるスピードアップは1986年11月、国鉄最後のダイヤ改正で最高速度を時速220キロに引き上げ。東京~新大阪間の所要時間を最短2時間56分に短縮し、3時間切りを達成した。そして1992年3月、最短2時間30分で走破する時速270キロ運転(2015年に時速285キロに引き上げ)の「のぞみ」がデビューし、現在に至る。全ての礎は開業から1年間の苦難と苦労にあったのである。







