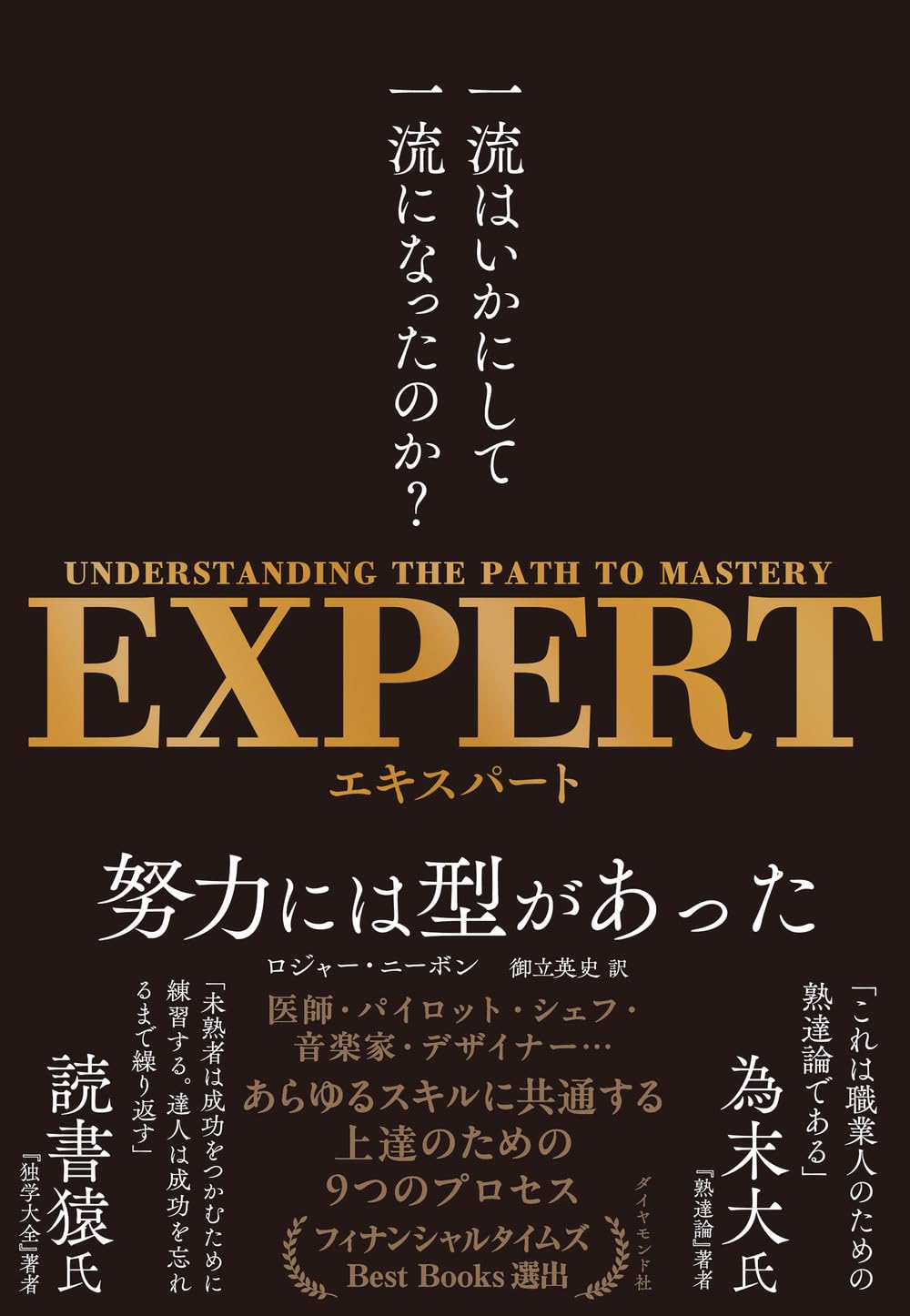新刊『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は、50代でも成長しつづける人の思考習慣を、『EXPERT』を元にお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「失敗」をどう捉えるか
多くの人は年齢を重ねるにつれ、新しい挑戦を避けがちになります。しかし、50代でもなお成長を続ける人たちは、失敗を「終わり」ではなく「学びの入り口」として扱っています。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』では次のように述べられています。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.219より
失敗を忌まわしいものと捉えるか、成長への糧と捉えるか。この違いが、50代以降のキャリアを大きく左右します。
レジリエンスという思考習慣
成長し続ける人に共通するのは「レジリエンス」を持っていることです。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.219より
レジリエンスは「立て直しを前提に挑戦できる思考法」です。たとえば、キャリア初期に間違った音を弾いたピアニストは恐怖心で舞台に立てなくなることがあります。しかし、そこから学び、次のステージへと進める人だけが、一流へと成長していきます。
成長する人の思考習慣とは
失敗の原因にはさまざまなものがあります。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.219より
つまり、「避けられる失敗」と「成長に必要な失敗」を区別し、後者を学びに変えることが重要です。
50代でも成長を続ける人は、無意識のうちに次のような思考習慣を持っています。
失敗を自己否定に直結させない:「自分は駄目だ」ではなく「やり方を変えれば次はできる」と考える。
失敗を経験値と捉える:同じミスを二度と繰り返さないために、具体的な改善策を導き出す。
立て直しを前提に挑戦する:準備・実行・修正というサイクルを当たり前のものにする。
「失敗力」が成長力になる
最後に本文の一節を引用します。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』p.220より
50代を迎えたからこそ、失敗から何を学ぶかが決定的に重要になります。失敗を怖れず、学びに変える。その習慣こそが、年齢を重ねても成長しつづける人の秘密なのです。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』を元に構成した記事です。)