水族館の相棒・漁師さんが
とんでもない生物を招くことも
しかし、皆さんご存じの通り、水族館には食用になるような有用魚種も展示されている。我々になじみのある生物は人気も高いため、普段食べているような魚の展示は必須だからだ。地元の海を忠実に再現した水槽を見れば、タイにヒラメにブリに、イセエビにアワビにサザエにタコに……思わず水槽の前でよだれが出そうだ。そんな美味そうな生物はどのようにして、水族館にやってくるのだろう?
その一つの答えとして、「漁師から買い付けている」というものがある。水族館のスタッフは往々にして、地元漁師とのつながりが強かったりするんだ。当然、漁師が漁獲した魚は鮮度もよく、傷も少ない傾向にある(そうじゃなきゃ、我々消費者が嫌がるからね)。だから、船で漁獲された後、生簀で生かされて陸まで運ばれて、いわゆる“活きのいい”状態で入手することが可能というわけだ。
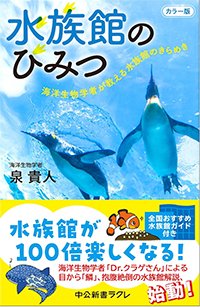 『カラー版―水族館のひみつ―海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(泉貴人、中央公論新社)
『カラー版―水族館のひみつ―海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(泉貴人、中央公論新社)
水族館によっては、漁師もしくは漁業協同組合(漁協)から購入した魚が展示のメインを張っていることもある。
そう、漁業権の制約があるなら、その大元から入手してしまえばいいということだ。図らずも食われずに水槽で生き永らえ、時に子孫を残すこともできるんだから、選ばれた魚にとってもラッキーということになるね。
そして時には、漁業がとんでもない生物を招くことも。日本の水族館で展示される、世界最大の魚類と言えば?そう、ジンベエザメだ。実は奴もワシントン条約の対象であり、絶滅危惧種になっているので、海で銛で突いてくるわけにはいかない。
じゃ、どうやって入手する?という話なのだが、その答えの一つが定置網。海に広く網を張って魚が入ってくるのを待つ漁法なのだが、いかんせん網が迷路のように広いので、ジンベエザメが迷い込むことがあるんだよね。そんな個体を保護して水槽に収容している水族館もある。
あの巨躯(きょく)を誇る人気者は、実は迷子の子猫ちゃんだったのである。







