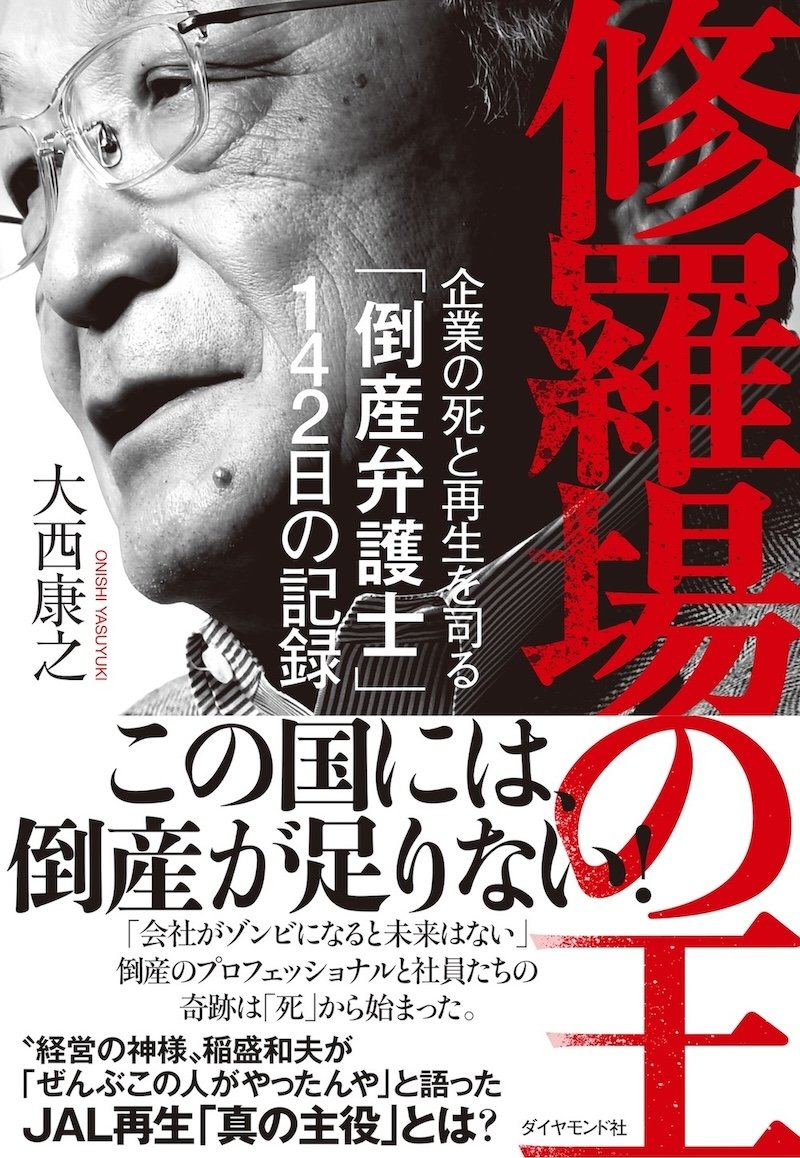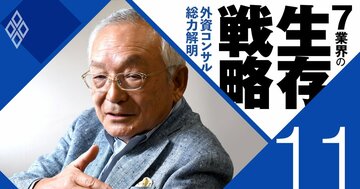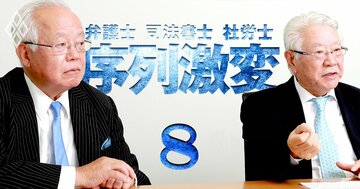今から15年前、日本航空(JAL)は倒産した。負債総額は事業会社として戦後最大の2兆3200億円。だが、わずか2年8ヶ月後には過去最速で再上場を果たす。「稲盛和夫という名経営者による奇跡」として語られるこの再生劇だが、その稲盛をして「全部この人がやったんや」と言わしめた男がいた。
日本を代表する倒産弁護士・瀬戸英雄――数多くの企業破綻を管財人として指揮してきた彼は、JALに「会社更生法」という劇薬を処方。既得権益にまみれ、ゾンビ化しつつあった巨大企業の宿痾を断ち切り、復活への道を拓いた。
倒産という修羅場を取り仕切る「倒産弁護士」とは一体どのような存在なのか。赤裸々な瀬戸の証言と関係者への膨大な取材に基づいてJALの倒産劇を描いた『修羅場の王──企業の死と再生を司る「倒産弁護士」142日の記録』から解説しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
企業倒産における神とも言える存在
倒産弁護士・瀬戸英雄は、1948年に静岡県の熱海市で生まれ、神奈川県の小田原市で育った。祖父は戦時中、伊豆のみかんを集荷して満州(現・中国東北部)に送る商売で財を成した。父親は国鉄マンだったが肋膜炎を患って会社を辞め、地元で青果店や食堂を営んだ。
瀬戸が子供の頃、父親の店は若い衆を使うほどに繁盛し、みんなが「英雄ちゃん、英雄ちゃん」と可愛がってくれた。学校から戻ればランドセルを放り投げて外に飛び出す野球少年で、仲間を従えるガキ大将だった。
高校は地元の名門、小田原高校に進むが、これといってやりたいこともない。
3年生になっても進路が定まらず「どうしたものか」と思案しているとき、遠縁の人に「英雄くん、日本でいちばんむずかしい試験は何だと思う」と聞かれた。
返答に困っている瀬戸を見て、その人は言った。
「司法試験だよ。自分の背丈ほどの本を読み、それでも一握りしか受からない。東大に入るより難しいんだ」
「それは面白い」
持ち前の負けん気が頭をもたげた。だが、それまでモダンジャズや映画、小説に夢中だった早熟な高校生は「猛勉強するのは今ではなく、22歳になってからでいい」と勝手にモラトリアムを決め込み、とりあえず法政大学の法学部に入った。
1976年、瀬戸は4回目のチャレンジで司法試験に合格する。この頃、瀬戸は自分の運命を変える一冊の本に出会う。『会社再建の記──わが「助っ人」人生に悔いなし』。著者は早川種三。
早川は、日本のスチールサッシの草分けで、戦時中には空母の防火シャッターなどを作り、戦闘機「雷電」の製造にも参加した「東京建鉄」を経営不振から救ったことを機に企業再建請負人となる。その後は、「日本特殊鋼」(現・大同特殊鋼)や「興人」などの破綻に際して管財人となり「会社再建の神様」と呼ばれた男である。
企業が会社更生法の適用を申請して事実上倒産したとき、裁判所に任命されるのが管財人だ。会社更生法第72条にあるとおり、会社は一部の債権者の抜け駆けを防ぐため、即時にすべての支払いを禁じられ、残った資産と人員を使ってどう会社を再建するかは管財人に一任される。
「倒産」という企業社会の修羅場にあっては、大銀行も、手形を割り引いた暴力団も、労働組合も、管財人には歯向かえない。法律によって全権を与えられた管財人は神にも似た存在だ。
「管財人こそ男の仕事じゃないか」
司法試験は通ったものの、どんな弁護士になるか今ひとつはっきりしなかった瀬戸の目標が、早川の自伝を読んだことで定まった。瀬戸は司法修習生時代、会社更生、会計学、心理学を選択し、「倒産弁護士」としての歩みを始めた。
数々の倒産事案で経験を積んだ瀬戸は、97年にヤオハンジャパン(現・マックスバリュ東海)の倒産で管財人代理の筆頭になる。その後、日本最大のゴルフ場運営会社だった日東興業(現・アコーディアAH01)、さらには第一ホテル、マイカル、大和生命保険(現・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険)、SFCG(旧・商工ファンド)など大型倒産事件を次々と手がけ、「倒産ムラに瀬戸あり」と認められるようになっていった。
「法的整理の鬼」と「私的整理の伝道師」
倒産企業の管財人を任される「倒産弁護士」は、法曹界でも特異な存在だ。ふつう、弁護士は事務所で依頼主の話を聞き、法廷で弁論するのが仕事だ。だが倒産弁護士は債務会社に飛び込み、債権に群がる金融機関や取引先、地位にしがみつく経営陣、人員削減に抵抗する労働組合などを相手に大立ち回りをする。瀬戸は「男の仕事」というが、見ようによっては義理と人情の世界で筋を通す任侠映画の高倉健のような存在だ。
利害関係が複雑に入り組む倒産の修羅場で、会社に関わるすべてのステークホルダー(利害関係者)を「まあ、これなら仕方ないか」と納得させる更生計画を作り、それを実現するには、高い経営センスと強烈な人心掌握術が求められる。上場企業の一つや二つ、経営できる度量がなければ務まらない。
最難関と言われる司法試験を突破して、弁護士資格を得た人々の多くは、大企業をクライアントに持つ大手法律事務所の渉外弁護士になり、スマートに頭脳で稼ぐことを目指す。アメリカの人気ドラマ「SUITS/スーツ」の世界を思い浮かべるといい。
日本でも「西村あさひ法律事務所」、「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」、「森・濱田松本法律事務所」「長島・大野・常松法律事務所」の四大法律事務所で勤務してアソシエイトからパートナーへと駆け上がるのが弁護士の花形コースとみられている。
一方、体を張って倒産事件を扱う弁護士たちのフィールドは、全く異質な世界であり、「倒産ムラ」と呼ばれる。
倒産ムラの最長老は清水直弁護士。第14期司法修習生で1962年に弁護士業をスタートさせ、消波ブロックの「技研興業」、化学繊維の「興人」、「東京佐川急便」など数々の倒産事件を扱った。「会社更生法、企業再生に清水あり」と言われる大家である。
清水を長老とすれば、村長に当たるのが15期の高木新二郎、23期の松嶋英機だった。それに続くのが31期の瀬戸である。
高木は米欧の倒産法研究の第一人者で、産業再生機構の再生委員長として「カネボウ」、「ダイエー」等の事業再生を手がけた。松嶋は「山一證券」、「そごう」(現・そごう・西武)、「ハウステンボス」などの管財人や会社更生申立代理人を務めた倒産のプロだが、800人を超える弁護士を抱える「西村あさひ法律事務所」の経営者でもあった。一匹狼タイプの高木や瀬戸とはタイプを異にする。
高木と瀬戸は一回り以上、歳が違うが、親分肌の二人の周りには倒産弁護士を志す若手弁護士が集まり、大型倒産を扱う時は「瀬戸組」「高木組」と呼ばれるチームで倒産会社に乗り込むことが多かった。
倒産ムラで一目置かれる存在になった高木と瀬戸。二人の弁護士は流派を大いに異にする。瀬戸は日本の会社更生法の改正や民事再生法の制定に深く関わり、あくまで倒産法を武器に闘う「法的整理の鬼」。高木は、米国で発達した新しい再建手法を積極的に取り入れ、法律に縛られない「私的整理の伝道師」だ。
二人の違いはまだある。高木が「理念の人」であるのに対し、瀬戸はあくまで「実務の人」である。高木は理念に燃える「革命家」であり、たとえ荒野であっても正しいと思った道を突き進む。瀬戸の武器はその卓越した実務能力と人心掌握術にある。すべてのステークホルダーが押し黙ってしまうような「落とし所」を見つけ出し、「ようござんすね」と納得させる。数字の裏付けと胆力が可能にする技だ。
この二人の倒産弁護士は、2010年、空前絶後の2兆3200億円の債務を背負い破綻したJALの再建をめぐって対峙することになる。
(この記事は『修羅場の王』から一部を抜粋・編集して構成したものです)