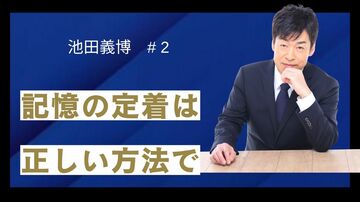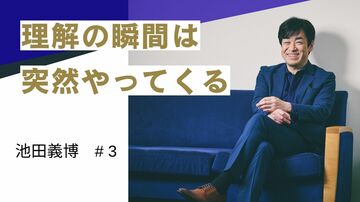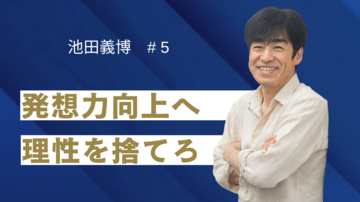断片的な知識をネットワーク化する
枠組みを意識して読書すると、知識は単なる断片ではなくネットワークとして結びつきます。新しい知識が入ってきたときも既存の知識とつながり、理解や応用の幅が広がります。
フレームワークは整理のための器にとどまりません。理解を深め、記憶を定着させ、さらに応用を可能にするための情報ネットワークなのです。
プライミング効果で知識の土台をつくる
たとえば前日の夜にハンバーガーの特集を見て「おいしそうだ」と感じたとします。翌日、無意識のうちにランチでハンバーガーを選んでいたということはないでしょうか。これは、先行情報が後の行動に影響を与える「プライミング効果」の典型例です。
読書でも同じことが起こります。本を読む前に目次を眺めたり、「はじめに」を読んだりして、自分なりに内容を想像することで脳に先行情報を与えます。厳密に正しい想像でなくても構いません。想像すること自体が土台となり、その後の学習効率を大きく高めてくれるのです。
一読目はざっくりと眺めるだけでいい
土台を作ったら、最初の読書ではフレームをつくることに専念します。細部まで精読するのではなく、要点を拾いながら眺めるように読み進めます。
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
本の中には重要な箇所が太字で示されていたり、章末に要点がまとめられていたりします。そうした部分を優先して拾っていけば効率的にフレームを構築できます。もし特に興味をひかれる部分があれば、少し読み込んでも構いませんが、基本は全体像の枠組みをつくることが優先です。
こうして一度目を読み終えると、大まかなフレームワークが完成します。その後に再読すれば、スピードも理解度も記憶の定着度も格段に向上します。