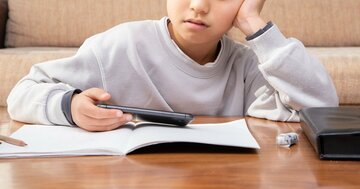LEDライトがチカチカし始めると、「お母さんが帰れと言ってるぞ!」と子どもが理解して、すんなり帰ってくる子どもが増えたのです。
子どもに考えさせるのではなく、聴覚や視覚での支援を考えましょう。
 同書より転載
同書より転載
ADHDの子どもは引き出しに
「仕切り」があると片付けやすい
学習机の引き出しをのぞいて見ると、文房具やプリントなどでぐちゃぐちゃになっていることがあります。
発達障害の子どもは、引き出しのなかをどうやって片付けたらいいのか見通しが立ちにくいのです。
そのため、引き出しのなかに仕切りを付けて、保護者が一緒に片付けましょう。
そして、整理整頓された引き出し内の写真を撮り、それを見本とします。その写真を見れば、どこに何を置けばいいのかを視覚的にわかるようにしておきます。
ADHDの子どもは、引き出しに仕切りがあると、片付けやすく感じます。
しかも、見本の写真があり、どう整理すればいいのか一目でわかるようになれば、効率的に片付けられます。
視覚刺激のほうが優位な彼らは、仕切りとは相性がよいはずです。引き出しが細かく仕切ってあれば、物を一度に放り込むこともなくなります。
ASDの子どもは、引き出し内にある物一つひとつが持つ背景を、保護者が子どもに確認しながら、一緒に片付けていきます。
保護者は、「ああ、これは大事なんだね。じゃあ大事なものはこっちに入れようか」など、子どものエピソードを聞きながら整理していきます。
「このなかに捨てていいものはある?捨てていいものを選択しようか」などと、引き出しのなかの余分な物を、本人の確認を取りながら捨てていきましょう。
 同書より転載
同書より転載