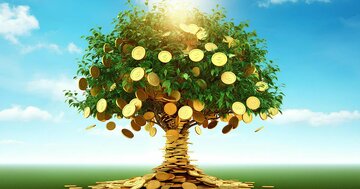写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
最適な資産配分は人それぞれ
さて今回のテーマは、「投資をしたい」顧客と向き合ったとき、金融機関の資産運用営業担当者としてどのようなアドバイスをすべきかである。
投資理論では、最も効率的な資産組み合わせの有効フロンティア曲線と、個人の効用(満足度)関数の無差別曲線との接点で、その人の最適ポートフォリオが決定されると習ったはずだ。
しかし、店頭に訪れる顧客にこの内容を字面どおり話した場合に「では、どうすれば良いのか」と聞かれるだろう。あなたは説明できるだろうか。
有効フロンティア曲線は、投資可能な資産をさまざまに組み合わせた時に生じるリターンデータのうち、同じリターンを最小限のリスクで達成する組み合わせをつないで描くことができる。計算は可能だが、投資対象になる資産クラスデータの継続的購入が必要で、顧客個人が簡単に算出できるものではない。加えて難しいのが効用関数の無差別曲線だ。理屈では分かるが、効用は主観的であり数値として測れないから、グラフで表現する無差別曲線も観念的なものになってしまう。
そこで金融機関は、ロボアドバイザーなどツールを使って顧客のリスク許容度を代替的に導く努力をしている。顧客の年齢や投資経験、資産額等の指標など多様な質問への回答を解析し、「あなたならこんなリスクが取れるはず」と回答するためだ。
こうして、有効フロンティアとリスク許容度との接点がその人にとっての「最適」資産配分となるのだが、この回答は「合理的な経済人」には最適であっても、誰にでもそうとは限らない。大した資産もなく金融知識もあまりないのにリスクの高い投資ばかりを好む人もいれば、金融知識も資力も十分だが元本保証の商品以外、怖くて投資できない人もいる。だから、合理的な人のリスク許容度を全員に当てはめるのは無理なのだ。
人間の心理的な偏り(バイアス)が投資行動にどのように影響するかを研究する行動ファイナンスでは、こうした行動を「過信バイアス」「損失回避性」「現状維持バイアス」と呼ぶ。こうしたバイアスは、投資家が非合理的に判断し、不利益を被る原因になるとされる。