心理的に追い詰め
部下にストレスを与える上司の特徴
今回の沢田さんの状況は、刑事事件の冤罪(えんざい)が起きる状況に近いと考えられます。法心理学に詳しい浜田寿美男氏(奈良女子大学名誉教授)によると、容疑者が犯行の覚えがないにもかかわらず、罪を認める嘘の自白(虚偽自白)で冤罪になるケースがあるそうです。この虚偽自白は、誰もが案外容易に陥っていく自然の心理だということです。
取り調べで一定の圧力をかけられて虚偽自白するケースでは、事件に関係ない事柄についてまで責めたてられ、容疑者は罪悪感を募らすことになります。理不尽な取り調べだとわかっていても、自分の処遇が相手に握られていることで、容疑者は取り調べ官に敵対することができない心理状態に陥るそうです。
また、取り調べ中に「もしかしたら本当に自分が犯人かもしれない」と自分を疑いはじめて自白すること(強制――自己同化型)もあるそうです。
筆者は沢田さんから相談を受けましたが、そのときは役員室の清掃担当から外されて、落ち込んでいました。虚偽自白の話などをしたうえで、役員とは力関係の差が歴然としているので、記憶が曖昧になったり、自分にはミスがないのに謝罪してしまったりしても仕方がないことだと説明しました。
そして、役員の前でそのような反応をみせてしまったことは、沢田さんの弱さゆえではないことを伝えると、少しホッとした様子でした。
もしB役員のような上司を持ってしまった場合は、コンプレックスを刺激しないようにしながらも、基本的に毅然とした態度で接する必要があります。秘書を何時間も立たせた状態で愚痴や不満を言うのは、パワーハラスメントに該当する疑いがあります。
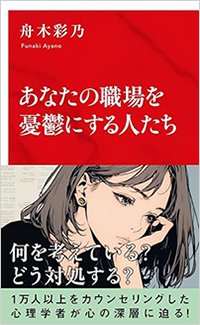 舟木彩乃『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(インターナショナル新書)
舟木彩乃『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(インターナショナル新書)
勇気がいることかもしれませんが、そのような状況に置かれたときは、「恐れ入りますが……」と言って、いったんその場所から離れるようにしましょう。その場所にとどまっていると、さらに悪い状況に陥り、いつの間にか心までその状況に巻き込まれていきます。
このような上司に対して普段から気をつけることは、なにごとに関しても基本的には2人以上で対応し、メールなど記録に残すことです。施錠の確認についても、たとえば必ず複数の人間で一緒にチェックしたり、社員証などで施錠してその記録が残るシステムに切り替えてもらったりすることを、会社側とも相談するべきでしょう。
そもそも、このような問題が頻繁に起こるようであれば、清掃の外部委託をすることで社員の心理的負担が減りますし、防犯カメラを設置することも検討すべきかもしれません。







