「結論の飛躍」や「過度の一般化」のような非適応的な認知をすることは、“つらい気持ち”を生み出すため、うつ状態になりやすくなります。そういう認知をする人は、自尊心の低さなどにより、自分の不完全な部分にばかりフォーカスしている可能性があるからです。
矢野さんほどではなくても、この非適応的な認知をしてしまう人は少なくありません。特に、心身ともに疲れているときなどは、わかっていながらも適応的な認知ができなかったりするものです。
まずは自分の認知パターンに
気づくことから
大切なことは、歪んだ認知になっていないかを点検し、それに気づくことです。非適応的な認知を、その根拠などを丁寧に検証しながら適応的な認知に変えていく習慣をつけることで、徐々にものごとを客観的に判断できるようになるでしょう。
矢野さんの話を聴いたあと、筆者は人事担当者とも話しました。結論から言えば、企画営業部は今年度の新人の本配属については、矢野さん1人を人事部に推薦してきたそうです。
企画営業部の上司は、客観的に2人の新人の様子を観察したうえでマーケティング面での強化を考えているため、矢野さんを選んだということでした。人事担当者は、企画営業部と矢野さんの意向が合致していることから、彼女をそのまま本配属とするつもりだったそうです。
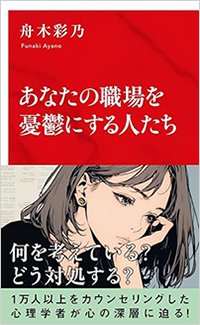 『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(舟木彩乃)
『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(舟木彩乃)
しかし、Hさんは企画営業部への希望が相当強く、人事担当者は何度も彼女との面談の機会を設けていて(矢野さんを陥れるようなエピソードも多数あった)、まだ迷ってはいるようです。
本稿の執筆時点では、企画営業部に本配属になるのは、矢野さんになりそうですが、彼女はまだそのことを知りません。とはいえ、今回のことをいろいろと整理して考えて、もっと自分に自信を持ちたいと強く思っているそうです。
筆者は、矢野さんに認知のことなどについて説明し、彼女にはまず、自分の認知パターンに気づくことから始めてもらうことにしました。自分の歪んだ認知のパターンを自覚すると、次第に、似たような場面に遭遇したときの認知を、現実的な認知(適正な捉え方)に修正できるようになっていきます。
現在、矢野さんはネガティブな感情で落ち込みそうになったとき、非適応的な認知になっていないか、自分で自分の感情を点検できるようになろうとしています。「過度の一般化」のメカニズムを知ってからは、Hさんの言動も、それほど気にしなくてよいことがわかったということです。







