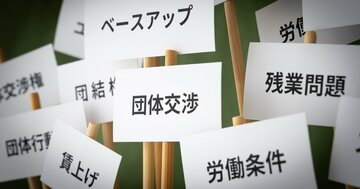河野:この実質賃金を左右する要因は「生産性」や「交易条件」、「労働分配率」などいくつかありますが、よく引き合いに出されるのが生産性ですね。
生産性が低い欧州の
実質賃金は上昇トレンド
唐鎌:この生産性というフレーズが、いつも曲者だと思います。
河野:生産性とは「産出量」を「労働投入量」で割ったものです。産出量を「働いた人の人数」で割ったものが「1人当たりの生産性」です。産出量を「投入した総労働時間で割ったもの」が「時間当たりの生産性」です。
おおざっぱに言えば「いかに効率よく産出しているか」ということです。賃上げについて議論すると、企業の経営者は、よく「生産性を向上させなければ、賃金を上げられない」と言います。
唐鎌:生産性が上がれば、企業の儲けが増えるので、賃金の伸び悩みを解消しやすくなることは一応、間違いではありませんよね。しかし、そもそも日本の生産性は、イメージされるほど低いのでしょうか。大前提となるこの点を確認させてください。
河野:日本の生産性は低迷が続いているのかというと、実はそれほど悪くはありません。日本における時間当たりの生産性の推移を見ると、1998年から足元までで30%ほど改善しています。ヨーロッパの経済大国であるドイツやフランスと比べると、生産性の改善は、実は日本のほうが上なのです。
唐鎌:OECD統計を通じた国際比較を基に、私も常にその違和感を抱いていました。日本の生産性はすでに世界でも上位層にあるのに「生産性を上げれば日本の問題を解決できる」と言われても、響きません。
「ここから生産性を上げることは悪いことではないものの、本当に問題なのはそこではないのでは?」と言いたくなります。
生産性と実質賃金が
両方とも高いのはアメリカくらい
河野:もし「日本は生産性が低迷しているから実質賃金が低迷している」という主張が正しいなら、日本より生産性の改善が劣るヨーロッパの実質賃金は、さらに低迷しているはずです。ところが、実際にはそうなっていません。