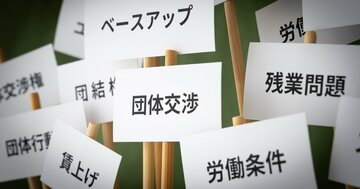河野:その通りで、生産性を重視しすぎることは生産的でないばかりか、かえって働く人々の賃金を押し下げる側面もあります。
唐鎌:しかし、「企業が儲けても、従業員の賃金を上げない」という状況が、特定の企業だけで起きているのなら、まだ理解できます。現実は、ほとんどの日本企業が同じような対応を続けてきました。これはなぜなのでしょうか。
乱暴な言い方をすれば、たくさん収益が出たとき、労働者ではなく、自分たち(企業)で“ぶんどっている”といった構図になっているかと思います。これは日本特有のカルチャーみたいなものと考えるべきでしょうか。
河野:私はカルチャーというより、1つのノルム――歴史的経験を通じて社会的に形作られる習慣――のようなものだと思います。
唐鎌:なるほど、ノルムですか。近年の日銀も多用するフレーズですね。
日本企業の守りの姿勢が
経済の停滞を生み出した
河野:社会の多くの人や企業が従う習慣や規範、いわゆるノルムは、歴史的な出来事が積み重なることで形成されていきます。たとえば、日本では1990年代末に金融危機が起き、その影響が落ち着いたかと思えば、2000年代末にはリーマンショックが起こり、輸出産業の売上が大きく落ち込みました。
1990年代末にはメインバンク制も崩壊しているので、繰り返される経済危機の経験から、日本企業は長期雇用制を守るためにも「たとえ利益が出ても、それを社内に蓄え、次に訪れるかもしれない危機に備える」という行動を取るようになり、これが産業界の規範になりました。
実際、過去四半世紀を振り返ると、国内で果敢にリスクを取り、投資を進めた経営者ほど、経済危機の際には赤字の責任を問われて退任に追い込まれてきました。
そして、いくつもの危機を経て現在の財界を見渡すと、リスクを取らなかった人たちが生き残っているようにも思われます。
唐鎌:なるほど。日本企業の「守りの姿勢」には、そうした歴史的背景が色濃く反映されているわけですね。