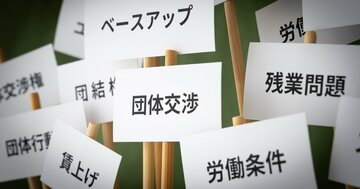河野:私は以前から「儲かってもため込むばかりで、賃上げにも国内投資にも消極的な大企業こそが、日本の長期停滞の元凶」と指摘してきました。
そんな中、2020年春、コロナ危機が始まった直後にお会いした何人かの財界人から「河野さんの言うことを聞かなくてよかったよ」と言われました。ムッとして真意を尋ねてみると、儲かってもお金を内部にため込み、賃上げも抑え、リスクも取らなかったおかげで、今回のコロナ禍で売上が激減しても、雇用リストラや倒産の危機を避けられたというのです。
つまり、儲かってもため込み、賃上げも国内投資も抑えることが、完全な成功体験となっているわけです。コロナ禍でその成功体験がさらに強化され、その結果、賃金や投資を抑え、利益を蓄えようとする傾向に拍車がかかっているのです。
そのことを警告するために執筆したのが、2022年に上梓した『成長の臨界』(慶應義塾大学出版会)だったのです。
コロナ危機を経験した結果
現預金の溜め込に拍車がかかった
唐鎌:多くの日本企業は「何かあったときのために」と、内部留保を積み上げてきたと思いますが、それがコロナ危機で正当化されてしまったのかもしれないですね。
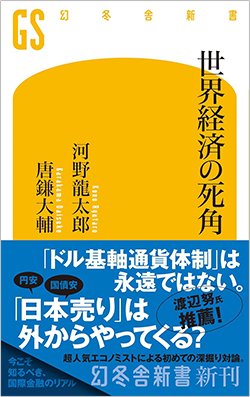 『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
ちなみに日本、アメリカ、ユーロ圏の企業部門(非金融法人)が抱える現預金について、名目GDP比で比較すると、2024年12月末時点でアメリカが約6%、ユーロ圏が約25%であるのに対し、日本は約60%です。
各社ごとに個別事情はあるとはいえ、マクロの数字を見る限り、ある程度のベア(編集部注/基本給を上げること)が進むのが自然に思えます。いずれにせよ、河野さんが長らく指摘されてきた通り、日本企業の抱えるノルムが成長を阻害した部分はあったように思います。
河野:そうなのです。先ほどもお話ししたように、2013年に300兆円だった利益剰余金は、2023年には倍の600兆円で、2023年は前年対比で50兆円も膨らんでいます。
近年の加速は、予想された通りではあるのですが、私の大企業経営者に対する警告は、まったく効果がなかったとも言えます(笑)。