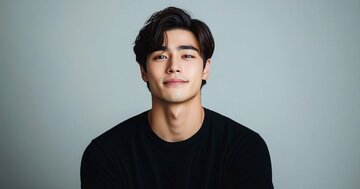AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“企画の穴”を埋める「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、企画を具体的にまとめたいときにおすすめなのが、技法その25「6W3H」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈アイデアを出したスレッドに続ける、もしくはアイデアを記入する〉
先にあげたアイデアを具体的なプランに発展させるために、6W3Hのすべての要素を具体的に述べてください。6W3Hの各要素は以下です。
What(何を):アイデアの内容や目的を明確にする。
Why(なぜ):アイデアの背景や理由、価値を明確にする。
Who(誰が):アイデアの対象者や関係者を明確にする。
Whom(誰と):アイデアの協力者やパートナーを明確にする。
Where(どこで):アイデアの場所や範囲を明確にする。
When(いつ):アイデアのタイミングや期間を明確にする。
How(どうやって):アイデアの方法や手段を明確にする。
How much(いくらで):アイデアのコストや収益を明確にする。
How many(どれだけ):アイデアの数量や規模を明確にする。
プレゼンテーションや会議提出の際、いきなり頭から資料の作り込みを始めてしまうと、行き詰まってしまいますよね。その作業に入る前にアイデアを「6W3H」で整理しておけば、あとはそれぞれの要素を深掘りして広げていくだけで済みます。すべての企画の土台に、この「6W3H」があるのです。
そうは言っても、全部で9項目もあります。パッと浮かんだだけのアイデアを、そこまで細分化、具体化していく作業は簡単ではありません。
そんなときに使ってほしいのが、足りていない要素をAIの力を借りて肉付けする技法「6W3H」です。投げたアイデアに対して、AIが9つの要素を具体的に言語化してくれます。
「化粧品ビジネス」の新しいアイデアを具体化してみよう
では、実践してみましょう。
一見したところ具体的な点まで考えられているように見えるアイデアでも、この技法を使うと「抜け」に気づけます。その上で、補強もしてくれる。まずはこんな例で、その力を試してみましょう。
〈旅行先化粧品提供サービス。旅行者が化粧品を持ち運ぶ手間を省き、目的地のホテルにあらかじめ必要なモノ(指定した日数分、その地の環境に合わせた化粧品セット)を配送するサービス。プチプラコスメなどを中心に比較的リーズナブルな料金で展開〉
先にあげたアイデアを具体的なプランに発展させるために、6W3Hのすべての要素を具体的に述べてください。6W3Hの各要素は以下です。
What(何を):アイデアの内容や目的を明確にする。
Why(なぜ):アイデアの背景や理由、価値を明確にする。
Who(誰が):アイデアの対象者や関係者を明確にする。
Whom(誰と):アイデアの協力者やパートナーを明確にする。
Where(どこで):アイデアの場所や範囲を明確にする。
When(いつ):アイデアのタイミングや期間を明確にする。
How(どうやって):アイデアの方法や手段を明確にする。
How much(いくらで):アイデアのコストや収益を明確にする。
How many(どれだけ):アイデアの数量や規模を明確にする。
なんとなく具体化されていそうなアイデアですが、どこに漏れがあるのでしょうか。耳で聞いただけで6W3Hに整理するのは至難の業です。AIはどのように整理し、言語化するのでしょう。