このポストを教えてくれた編集者は、「読書」の冷遇ぶりに「そりゃ、町から本屋が消えてマツキヨやココカラファインばかりになるわけです 笑」というメッセを添えてきたが、筆者としては「YouTube」と「ネット」だけを「知識」でくくっていることのほうが、ジワジワ来た。
インターネットのフィルターバブルをもっとも理解しているのは10代
興味深いデータがある。博報堂 メディア環境研究所が2023年に行った調査によると、インターネットのフィルターバブル(頻繁に「いいね」をしたり、長時間視聴したコンテンツに関連した情報が優先的に表示されること)を理解している人の割合は、10代が52.1%と全世代を通じて突出して高かった。20代は26.6%、30~40代で21.9%、50~60代で20.3%なので、ぶっちぎりである。また、「SNSやネットでは自分の見たい情報ばかり流れてきて情報がかたよる可能性がある」という質問にも、ほぼ同様の傾向が見られた。
要するに、大人より子どものほうが、ネットやSNSの情報は玉石混交であると認識しているのだ。
子どもたちはインターネットを完全に信じていない。それでいて使いこなしている。使いこなせていないのは大人のほうだ。これが、大人のスマホ使用を制限すべきだと感じる理由である。
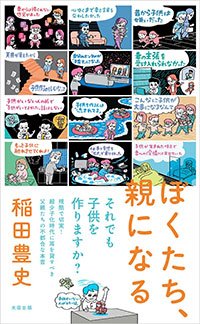 稲田豊史『ぼくたち、親になる』(太田出版)
稲田豊史『ぼくたち、親になる』(太田出版)
付け加えるなら、シニア層にはスマホだけでなく、パソコンのネット接続時間にも上限を設けたほうがいい。定年退職後に暇を持て余したシニアが日がな一日YouTube漬けとなり、あっと言う間に陰謀論者やレイシストに仕上がっていく悲劇が後を絶たない。インターネットを使いこなせていないどころか、インターネットに使われている。
高橋名人は、2020年に行われたウェブメディアのインタビューで、かつて「ゲームは1日1時間」と言った理由を「子どもたちはテレビゲーム以外から学ぶべきこともたくさんあるから」と語った。大人になったかつての子どもたちは、彼の言葉をこう読み替えるべきであろう。
「スマホは1日2時間。大人たちはYouTube以外から学ぶべきこともたくさんあるから」







