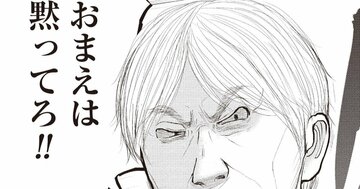『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
さまざまなメディアで取り上げられた押川剛の衝撃のノンフィクションを鬼才・鈴木マサカズの力で完全漫画化!コミックバンチKai(新潮社)で連載されている『「子供を殺してください」という親たち』(原作/押川剛、作画/鈴木マサカズ)のケース4「親を許さない子供たち・前編」から、押川氏が漫画に描けなかった登場人物たちのエピソードを紹介する。(株式会社トキワ精神保健事務所所長 押川 剛)
父親が財布を握っている家庭は母親が追い詰められがち
トキワ精神保健事務所の「精神障害者移送サービス」にはさまざまな相談が舞い込む。今回の依頼者は10年以上もひきこもる息子・田辺卓也(仮名)の家族だ。
卓也はひきこもりといっても外出することもあり、うつ病の診断を受けて精神科に定期通院もしている。問題は、本人がほぼ一日中、母親を拘束していることにあった。
ちなみに長期ひきこもりの相談では、私の経験上、父親の存在がないことが多い。ひきこもる子どもの世話に始まり、暴言や暴力、金銭の無心など、「負」のすべてを母親が受け止めている。相談先へ赴くのも母親か、場合によってはきょうだいが請け負う。
今回のケースでも、私の事務所への問い合わせから面談、契約に至るまで、父親不在で行われた。
私が父親の姿を初めて目にしたのは、視察調査で向かった野球場だった。父親は問題の種である息子と一緒に野球観戦をしていたのだが、息子を気にかける様子は一切なかった。
息子が隣にいるにもかかわらず、フィールドから片時も目を離さず、野球に夢中になっていたのは「無関心」だからだ。何の関心もないからこそ、息子に目をやることもなく、こぶしを振り上げ、唾を飛ばし、応援歌を歌える。
母親だけが一人、息子の言動を気にしてピリピリと張りつめている。その姿が痛ましかった。
そもそも野球観戦の予定を聞いたときに私は、「この息子は、親に反発して暴言や暴力さえあるのに、なぜ一緒に野球観戦に行けるのだろう」と疑問に思った。しかし実際の光景を見て、答えがわかった。息子は父親にすがっているのだ。特に父親の経済力に。
この家庭は、父親が稼ぎ、母親は専業主婦として従う、一昔前の家族モデルを体現するような家庭だった。しかも財布のひもを握っているのは父親だ。
私の仕事に限っていえば、父親が財布のひもを握っている家庭ほど、依頼に至らないことが多い。なぜなら困っているのは常に母親で、父親は直接の被害を受けていないからだ。正確にいえば、被害を受けなくてすむシステムを自ら作り上げている。
一方で母親は、大金を払ってでも依頼したい。そこには「子どもだけでなく自分も助けてほしい」という切実な思いがある。でも父親は、金を払うくらいなら、「母親が面倒をみればいいじゃないか」と考える。
「家のことも子育ても全部お前に任せてきただろう。金の心配もさせていないじゃないか。だから家庭の問題はすべて、お前のせい」というような絶対的な価値観があるから、空恐ろしいほど無関心でいられる。
このような家庭では、子どもにとっても中心は母親であり、あらゆる攻撃もまた、母親に向かう。父親は金を握る存在であるとわかっているからこそ、よほどのことがない限り手は出さない。
今回のケースでは、母親が疲弊し、本人の要求や攻撃が父親に向かい始めたことで、ようやく依頼になった。「息子のことは、第三者に託すしかない」という決断をするまでに、10年の時間を要したのだ。
詳細は次回述べるが、父親は社会的地位のある人物で、仕事においては大きな決断もしてきた。でも家のことは、何一つ決断しなかった。
私への依頼は金を払うというのもあって判断も鈍るのだろう。家庭内の、しかもネガティブな問題には金を払いたくない――。これは問題を長期化させ、肥大化させてしまう家庭に共通する考え方でもある。
現代社会の裏側に潜む家族と社会の闇をえぐり、その先に光を当てる。マンガの続きは「ニュースな漫画」でチェック!
 『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
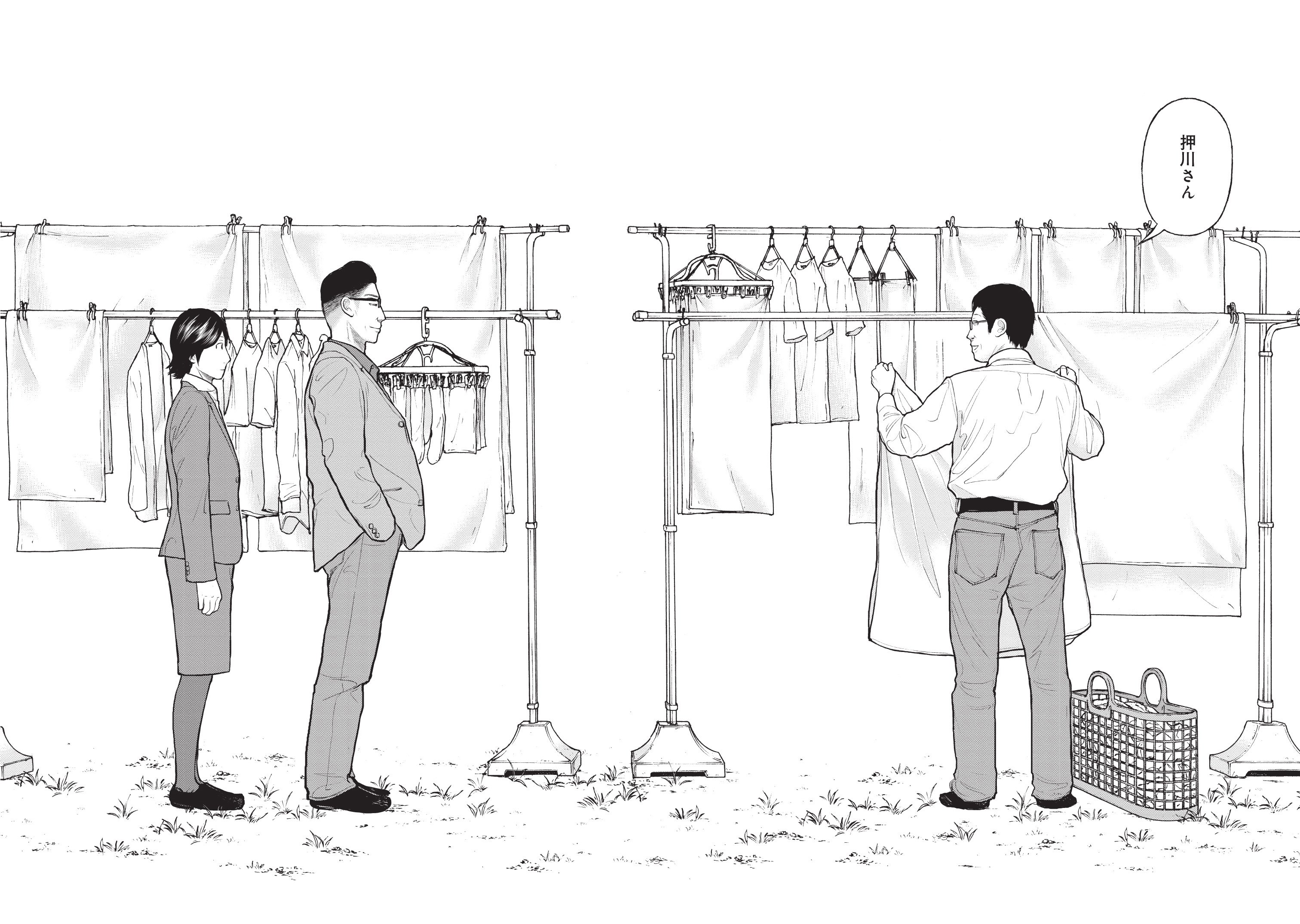 『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社
『「子供を殺してください」という親たち』原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ/新潮社