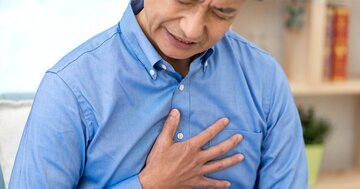異常がなければ
2~5年に1回くらいの頻度でOK
また逆に、一度受けて異常がなければ毎年受ける必要はありません。心臓血管病のリスクの高さにもよりますが、2〜5年に1回くらいで十分でしょう。
循環器ドックの血圧脈波検査を受けて血管年齢が実際の年齢より高かったり、血管が詰まっている様子を目にすれば、ショックを受けるかもしれません。散々怖いことも述べましたが、実は「大動脈」はそんなに簡単には詰まりません。
血管にとって大切なことは大きく三つあり、一つ目は冒頭紹介したように「魚」を含め良い油を摂取すること、二つ目は禁煙。喫煙はさまざまな作用で血管を傷め、動脈硬化を進めます。世界の大規模研究では、喫煙は心筋梗塞や脳血管疾患を3倍も増やし、致命的心血管病の原因といわれているのです。
積極的に運動をする人は
心血管病を引き起こしにくい
そして三つ目として、実は運動が非常に重要です。これまで診てきた患者さんの中で肥満気味で、悪玉コレステロールや血圧が高く、血管の内腔が狭くなっている、つまり動脈硬化が進んでいる人でも積極的に運動をしている人は意外と心血管病を引き起こしません。
人は動かないと末梢血管の循環が悪くなり、血栓やプラーク(血管の内膜が厚くなり、中にこぶのように“出っ張ったもの”)ができやすい状態になります。
長距離飛行や災害時の避難所生活で生じる「エコノミークラス症候群」も、動かないことが大本の原因です。環境変化やストレス、睡眠障害などにより交感神経が活性化され、血液が固まりやすくなったところに、動かないことで下肢の静脈にできた血栓が飛び、肺の動脈に詰まってしまうのです。
避難所だけでなく、整形外科の手術後や車中泊なども危険です。車中泊をした人の3割以上に、足の静脈に血栓が出来たという報告もあります。
ですから健康な人も目安として、毎日30分以上の歩行をすると血栓の予防になるでしょう。
十分な運動をすれば心拍数が増えて血液の流れが良くなり、血管を広げる一酸化窒素(NO)や血栓を溶解する成分(tPA)も放出されます。ヨーロッパ心臓病学会では、1日30分、1週間に5日以上は有酸素運動をすること、そのなかでも1日はテニスやジョギングなどのスポーツを取り入れることが推奨されています。
スポーツの秋、検査結果が良くても悪くても体を積極的に動かしましょう。
◆◆◆
>>【第1回】「「体」に表れる突然死の兆候、50代を過ぎたら特に危険!」はこちら
疾患による突然死は毎年約8万人程度ともいわれ、実は働き盛りの世代の発症が非常に多いといいます。体に表れる兆候や兆しを確認する方法について東丸貴信医師に聞きました。