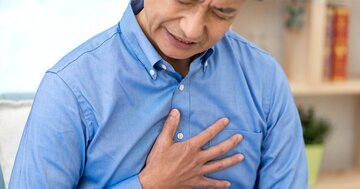写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
突然死を防ぐためにどんな検査を受ければいいのか。長年、平成横浜病院で総合健診センター長を務めてきた東丸貴信医師が「50代になったら一度は受けてほしい」と勧める検査とは?ジャーナリストの笹井恵里子さんが聞きました。(東邦大学名誉教授 東丸貴信、聞き手/ジャーナリスト 笹井恵里子)
50代から急増する血管にできる“こぶ”
胸部大動脈瘤が破裂すれば致死率90%
前回は「体」に表れる突然死の兆候をお伝えしました。
突然死のうち、脳卒中や大動脈瘤(りゅう)破裂、急性心筋梗塞など心血管疾患が半数を占め、近年働き盛りの世代の発症が多いです。ストレスや食べすぎ、飲みすぎ、運動不足などで動脈硬化が早く進み、心血管疾患を引き起こしやすくなってしまうのですね。
動脈硬化は、若い時よりも年を取ってからのほうが進行速度は速く、女性の場合は閉経によって女性ホルモンが減少すると一気に進みます。そして動脈硬化の成れの果てでもある血管にできるこぶ(瘤)は、50代から急増するので注意が必要です。
瘤が胸部の大動脈にできて大きくなり、胸部大動脈瘤として破裂すれば、致死率は90%といわれます。このリスクがわかる検査を紹介する前に、大動脈疾患のリスクを下げる食べものをご紹介しましょう。
魚をほとんど食べないと
大動脈解離で死亡するリスクが2.5倍高い
国立がん研究センターは2018年、〈魚をほとんど食べないことが大動脈疾患(大動脈解離・大動脈瘤)による死亡リスクを増加させること〉を世界で初めて明らかにしました(※)。
日本の八つの大規模研究から36万人以上を統合した解析を行い、日本人における魚摂取頻度と大動脈疾患関連を検討したところ、魚を週1回から2回食べる群と比べ、ほとんど食べない群では、大動脈解離で死亡するリスクが2.5倍高くなっていたのです。
研究では、魚の摂取が極端に少なくならないことが大動脈疾患の死亡を予防するために重要だと考察しています。また魚の高摂取は心筋梗塞のリスクを低下させることもわかっています。
(※)https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2018/1015_02/index.html