バルツァーは田端~池袋間の計画を聞きつけて、市内縦貫鉄道が完成した暁には完全な環状運転を実施することで、郊外の低廉な住宅から鉄道通勤が可能になり、欧米大都市のように郊外人口が大幅に増加すると述べている。
市内縦貫鉄道は1896年に測量、1899年に用地買収を開始し、1900年に着工したが、不景気や日露戦争の影響で工事はなかなか進まず、ようやく1910年に新橋~呉服橋(東京駅の北側にあった仮駅)間が開業した。
山手線は前年の1909年に電車運転を開始しており、上野~新宿~新橋間を64分、15分間隔で運転した。これにより山手線沿線の住宅開発が進み、バルツァーが予見した郊外化が実現した。
1914年の東京駅開業を経て、1919年に中央線が東京まで延伸し、山手線は神田から中央線経由で中野まで乗り入れる「の之字運転」を開始した。そして、関東大震災を挟んで1925年11月、神田~上野間の高架線が完成し、山手線という円はつながった。東京以南の高架線がレンガ造りなのに対し、東京以北が鉄筋コンクリート造りなのは、10数年で建設技術が飛躍的に進歩したことを示している。
ここまで「山手線」の名称は旅客案内上の路線名として用いてきた。しかし厳密には、路線区分としての山手線は田端~新宿~品川間を指し、田端~東京間は東北本線、東京~品川間は東海道本線である。つまり、環状運転は3路線の直通列車という扱いだ。
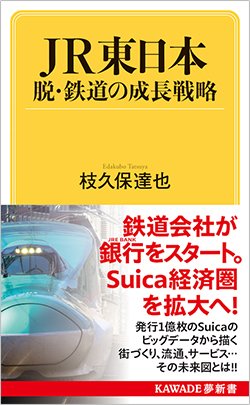 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
先に放射線と環状線について整理したが、これをふまえれば田端~新宿~品川間は環状線、それ以外は放射線ということになる。改めて図2を見てみると、山手線は旧東京市区域の西側を迂回し、上野~品川間は南北に貫いている。
首都圏第二の環状線である武蔵野線は東京都心を完全に迂回しているのに対し、山手線は東側をカバーせず都心に乗り入れているため、池袋から上野・東京方面、渋谷から新橋・東京方面に移動可能だ。つまり、環状線でありながら都心直通の放射線であることが山手線の最大の特徴なのだ。
この結果、1920年代に現在の東急東横線、目黒線、池上線など、渋谷、目黒、五反田をターミナルとする私鉄が相次いで開業し、沿線の住宅化が進んだことで東京都市圏が劇的に拡大した。こうして山手線の環状運転が現在の東京を作り上げたのである。
そして、池袋、新宿、渋谷が副都心となり、新宿は新都心となった。今や上野~品川間のみを都心と考える人はいないだろう。山手線は都心そのものとなったのである。次の100年は日本にとって、東京にとって厳しい時代になるだろうが、その時に山手線はどのような役割を果たしているのだろうか。
鈴木優一郎『近代日本の大都市形成』岩田書院 2004年
鹿島建設ウェブサイト「鹿島の軌跡 第47回 東京市街線-明治期に作られた煉瓦造の高架橋」







