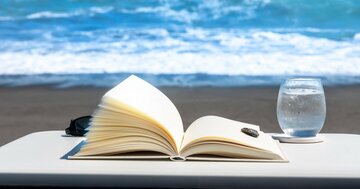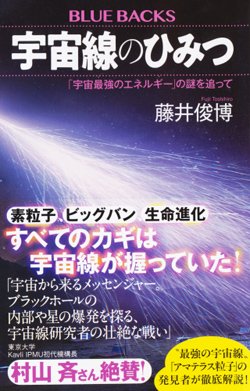 『宇宙線のひみつ』(藤井俊博著、ブルーバックス、税込1320円)
『宇宙線のひみつ』(藤井俊博著、ブルーバックス、税込1320円)
そんな宇宙線研究の分野で、2021年に日本人研究者が「世紀の大発見」をして注目を集めた。観測史上最高クラスのエネルギーをもつ宇宙線の検出に成功し、「アマテラス粒子」と名付けたのが、本書の著者、藤井准教授なのだ。
本書では、アマテラス粒子発見までの経緯が詳しく語られており、読み物としても面白い。藤井准教授は、米国ユタ州の砂漠地帯で行われていた9カ国/地域の国際共同研究「テレスコープアレイ実験」に参加しており、現時点での「宇宙最強粒子」は、その過程で発見された。
アマテラス粒子は「244エクサ電子ボルト」(エクサは100京)という、とてつもないエネルギーを有する。1グラム集めただけで地球が壊れるほどだという。
ただし、このような「激高エネルギー宇宙線」は、1平方キロメートルあたり、100年に1個しか地球に到来しない「激レア」な粒子だ。藤井准教授の発見がどれほど貴重なものか、これだけでもわかるだろう。
火山、ピラミッドからビルまで
巨大構造物を「透視」する
宇宙線研究は、あくまで宇宙の謎を解き明かす「基礎研究」なのだが、宇宙線が実用に役立つケースがいくつかある。その一つが「ミュオグラフィ」だ。
宇宙線が地球に到来し、大気に触れることで生成される物質に「ミューオン」がある。このミューオンの量を調べることで、火山やピラミッド、古墳やビルといった巨大な構造物の内部を「透視」できる。
この技術がミュオグラフィと呼ばれるもので、火山の内部のマグマの位置や、河川堤防の劣化状態などを調べるのに使える。
宇宙線の研究には、ロマンが感じられる。好奇心を働かせながら、広大な宇宙から、さまざまなヒントを探してみていただきたい。