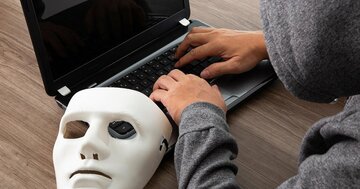仕事や勉強に集中しなければならないとき、いつのまにかほかのことを考えていたり、過去の出来事の後悔や将来の不安が止められなくなったりすることはないだろうか。これがマインドワンダリング(mind wandering:心があちこちさまようこと)だが、最近は「ぐるぐる思考」と呼ばれるようだ(精神医学では「反芻=はんすう=思考」)。思考が同じところをぐるぐるして、そこから出られなくなってしまうのだ。
行動心理学に基づいたビジネス書、自己啓発書を書いてきたニック・トレントンは、『STOP OVERTHINKING 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』(児島修訳/ダイヤモンド社)で、「『考える』ことは、問題を解決するための行為である。けれども、12の『考えすぎる』と逆に問題が生まれてしまう」として、「考え過ぎが問題になるケース(ぐるぐる思考)」をあげている。
(1) 次から次へと湧いてくる考えに気を取られる。
(2) 「考えている自分」について考えている。
(3) 自分の考えを無理にコントロールしたり、あやつろうとしたりする。
(4) 次々と浮かんでくる考えについて悩み、そのことが嫌だと感じる。「どうしてこんなことを考えてしまうのか」と思う。
(5) 考えること自体を、心の不自然な働きだと感じてしまう。
(6) 自分の考えをしょっちゅう疑い、分析し、評価している。
(7) 困った状態になったとき、自分のせいだと思う。
(8) 自分の考えを常に理解し、心の中を掘り下げたいと思っている。
(9) 決断が苦手で、自分の選択を後悔しがちである。
(10) 心配事や悩みの種がたくさんある。
(11) 「自分は物事をネガティブに考えがちだ」と自覚している。
(12) どうすることもできない過去の出来事を何度も思い出してしまう。
たぶんあなたにも、いくつか該当するものがあるだろう。そんな「ぐるぐる思考」から抜け出すには、どうすればいいのだろうか。
 Photo/wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
Photo/wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
DMNは記憶(過去の体験)をもとにした連想活動
従来の脳科学では、ぼんやりしているときや、難しい課題を行なっていないときは、脳があまり活動していないと考えられてきた。だが2010年代にfMRI(機能的磁気共鳴画像法)で脳の活動をリアルタイムで観察できるようになると、この常識は大きく書き換えられることになる。休息時間中の被験者の脳はきわめて活発に活動していたのだ。
それに加えて、このとき活動している脳の領域は、被験者がなんらかの課題(タスク)を行なっているときの領域とは異なることもわかった。脳がなにもしていないとき、すなわちデフォルト状態にあるときに活動しているこのネットワークは、DMN(Default Mode Network:デフォルトモードネットワーク)と名づけられた。
DMNは内側前頭前皮質、後帯状皮質、角回を中心に、多くの領域が関与する大規模なネットワークだ。わたしたちは、起きている時間の30~47%はマインドワンダリングにとらわれ、大量のエネルギーを消費している。
認知神経科学者のモシェ・バーは、『マインドワンダリング さまよう心が育む創造性』(横澤一彦訳/勁草書房)で、DMNは記憶(過去の体験)をもとにした連想活動だと述べている。コンピュータのプログラムでいうならIF…THEN…の条件分岐で、IFで条件を指定し、THENで命令を実行させる。脳は巨大なシミュレーションマシンなのだ。
DMNが進化のなかで発達してきたのは、過去の体験を現在の状況にあてはめて、最善の対処法を見出すためだ。そのためには、過去の不快な体験や恐怖を記憶している必要がある。
旧石器時代にアフリカのサバンナを歩いていたら、草むらが揺れたとしよう。すると、かつて草むらにライオンが潜んでいて、あやうく逃げ延びた体験を思い出す。この記憶と現在の状況を連想でつなげることで、急いで草むらから遠ざかるという正しい判断ができる。
脳の機能がさらに高度化すると、この連想を過去や未来に延長できるようになる。過去の体験をシミュレーションし直すことは「後悔(もしあのときこうしていれば、こんなヒドいことにならなかっただろう)」、未来の体験のシミュレーションは「不安(もしいまこうすれば、将来にヒドいことが起きるにちがいない)」と呼ばれる。DMNの「ぐるぐる思考」とは、後悔や不安のネガティブなシミュレーションから抜け出すことができなくなることだ。
だがその一方で、DMNの活動は創造力(クリエイティビティ)の源泉でもある。アイデアは、本来なら無関係なある要素と別の要素を、連想によって結びつけることから生まれるのだ(詩はその典型だろう)。
だがこれは、ネガティブなマインドワンダリング(ぐるぐる思考)が悪いもので、ポジティブな連想がよいものという単純な話ではない。過剰な思考の反芻はうつ病の症状だが、適度なシミュレーションは人生を堅実に過ごすために必要だろう。過去の体験を活かすことができなければ、いきあたりばったりの破滅的な人生を送るしかない。その一方で、過剰な連想は統合失調症の予測因子になる。
興味深いのは、DMNの活動が「わたし」という意識(自己意識)や、他者の心の理解に関係していることだ。
自己意識は、「異なる状況で自分はどうするだろうか」というシミュレーションからつくられる。「好きなひとに告白したら~」「入学試験で失敗したら~」「あの会社に就職できたら~」など、DMNは無数のIF…THEN…のプログラムを走らせている。そして、「こんなとき自分はこうするだろう」という連想(シミュレーション)から、「自分とは何者なのか」という一定のイメージがつくられる。――トレントンの「考え過ぎ」の12のケースは、すべて自分についてのものだった。
すると次に、このシミュレーションが他者の心を理解するときに利用される。恥ずかしい思いをしたときに顔が真っ赤になった体験をしていれば、相手の顔が赤くなったとき、「恥ずかしい」と感じていると判断できるようになる。これは「心の理論(ToM:Theory of Mind)と呼ばれる。わたしたちは、自分の心の状態を相手にあてはめることでしか他者を理解することができないのだ。
DMNの活動にはじめて気づいたのは、おそらくは古代インド人で、仏教ではネガティブな反芻思考を「煩悩」として、瞑想(めいそう)によってこれをコントロールしようとする。モシェ・バーも「ぐるぐる思考」にはマインドフルネス瞑想が効果的だと述べている。