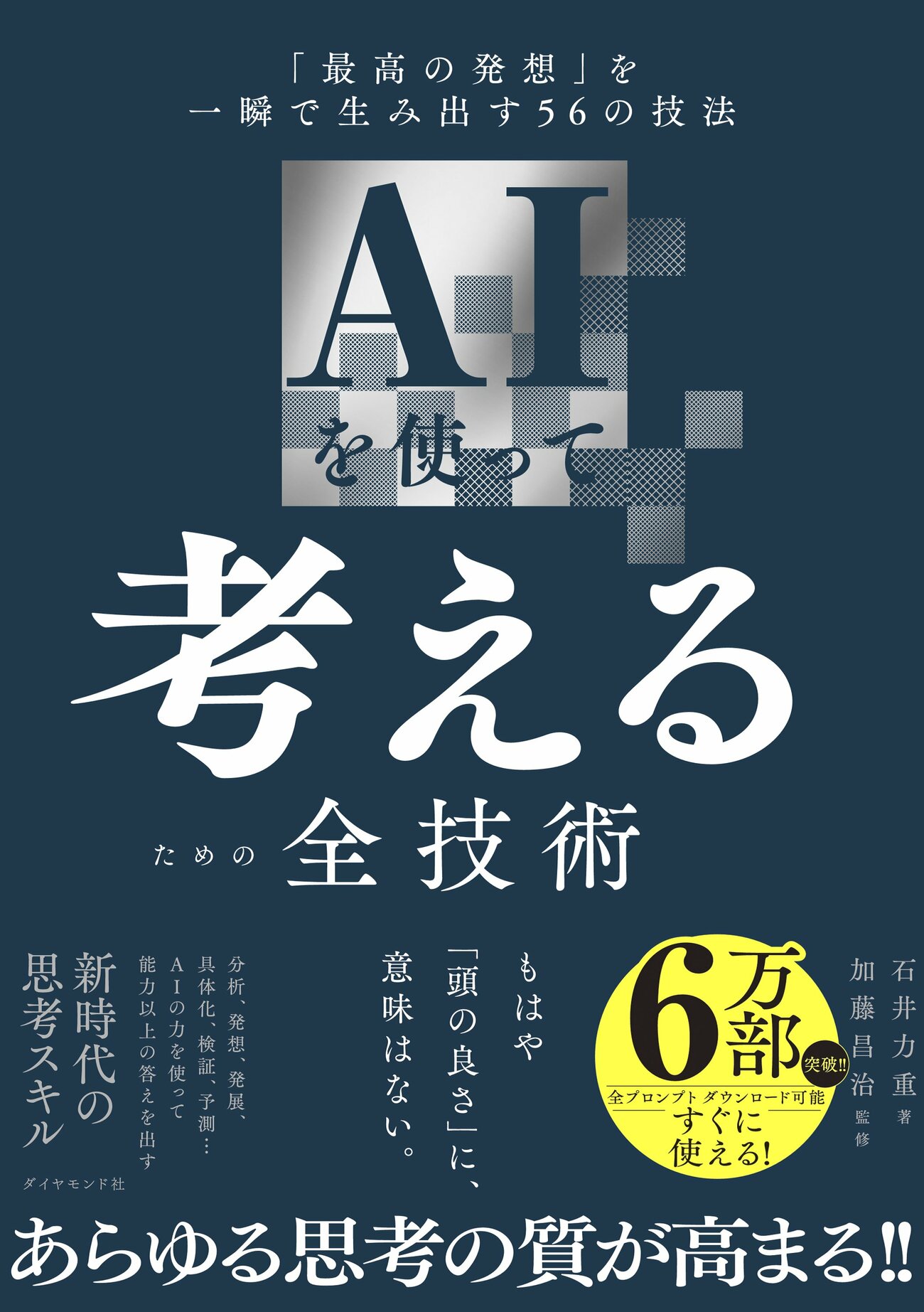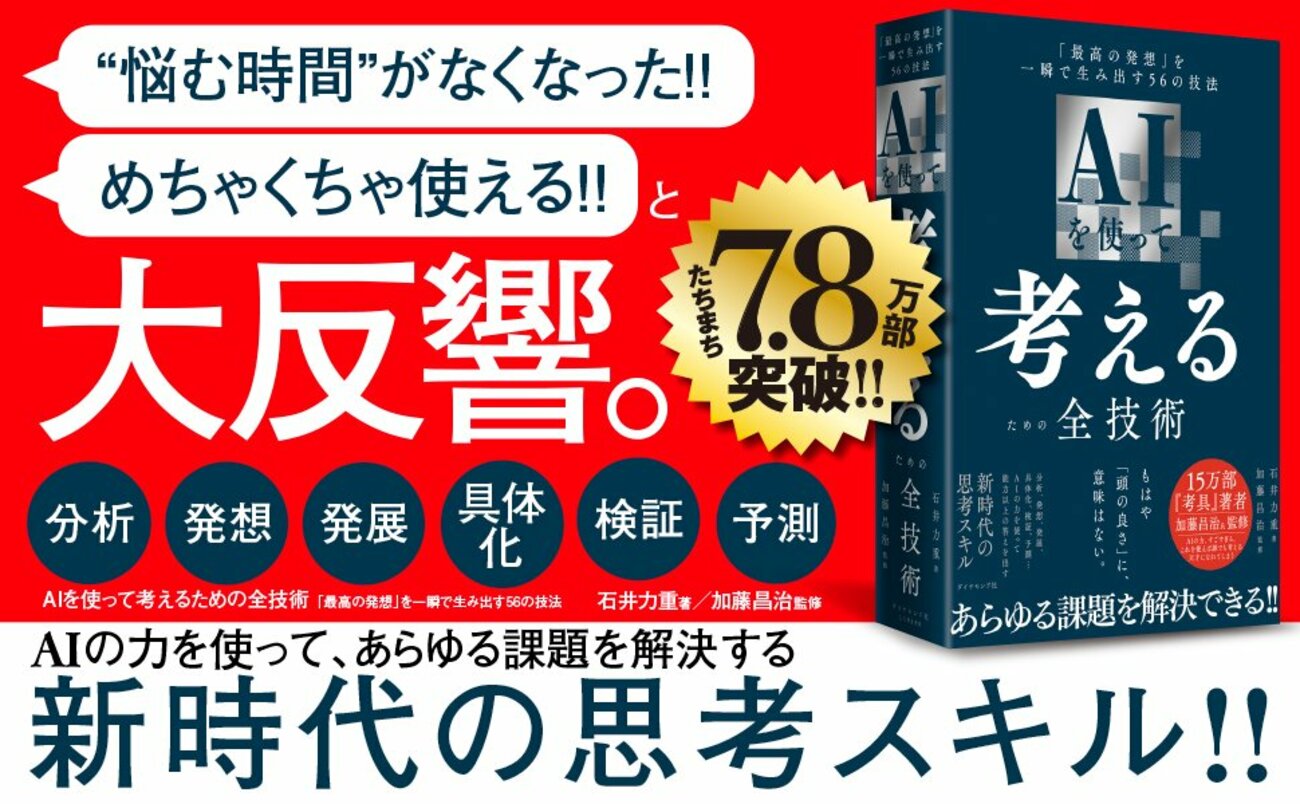AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「頭のいい人」のAIの使い方
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
たとえば、将来的にも通用するアイデアや問題解決策を考えたいときにも、AIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどです。
では、どう聞けばいいのか。それをご紹介していきます。
「未来予測」はもはや民主化された
どんな業種や業態であっても、広い意味での「未来予想」とは無縁ではいられません。
とくにメーカーやプロダクト開発において、新商品の開発サイクルが年々早まってきているのは否定しようのない事実です。
よって将来にわたって有用であるアイデアを考えるには、確度の高い未来予測が欠かせません。
アイデア発想が得意な人は、情報に敏感で、定点観測ポイントを持っていたり、その他にも何本かのアンテナを立てていたりします。
しかし、まだ慣れていない初心者にしてみれば、未来予測のための情報を得るにはどこにアンテナを立てればいいのかさえわからない。
やみくもに、あるいは手当たりしだい……では効率が悪すぎます。
AIを誰もがフリーに使えるようになった今の時代、状況は大きく変わりました。
記事や調査結果などを探し、読み込み、関連付けて示唆を得る……この一連の作業が、AIを使えばほんの数分で終わってしまうのですから衝撃です。
未来予想において、AIを使わないなんてことは考えられなくなりつつあります。
ただしAIは本質的に「未来予測」を拒む
ところが、です。
AIは基本的に「未来予測」を避けたがります。
AIに内在しているガイドラインには「してはいけない行為」が組み込まれているようで、ある種の生成指示に対して実行を拒みがちです。そのひとつに「未来について尋ねる質問に答えること」がある模様。
実際、単純に「未来を予想して」と聞いても、消極的な回答になってしまうことが少なくありません。
AIとはいえ未来予測は誤りが多くなる可能性が高いためか、回答にシャープさが失われがちでした。
不確実な話題であっても「きっぱり回答する」ところがAIの特徴ですが、未来に関する質問にきっぱり回答してしまうとユーザーに誤認を広げてしまうリスクがあるとAI開発陣は考えて、回答を拒む壁をあえて用意しているのでしょうか。
未来予想のヒントをつかむ技法「最近の傾向」
こうしたAIの傾向なども見ながら、それでもAIを使って確度の高い未来予想をしたいという人のために、いくつかの方法を開発しました。
そのひとつが技法その54「最近の傾向」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈課題や目的を記入〉
この問題の解決に関する最新トレンドは何ですか?
役に立つ回答を出力してくれる聞き方をあれこれ試してみた結果、「この問題の解決に関する最新トレンドは何ですか?」というプロンプトに行き着いています。
この技法を使えば、新製品や新サービスの開発に影響を与える、社会環境やビジネス環境の変化を簡単に把握できます。
「最新って、すでに存在していることで、未来じゃないですよね?」とよく聞かれます。
厳密に定義すれば、おっしゃるとおり。
ですがAIが保有している情報における「最新」は、世の中の一般的な、言い換えるとリアルなビジネスシーンにとっては少し先の未来を示していることが多いのです。
私が手がけるコンサルティングの現場では、近未来の予想として充分に機能しています。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています)