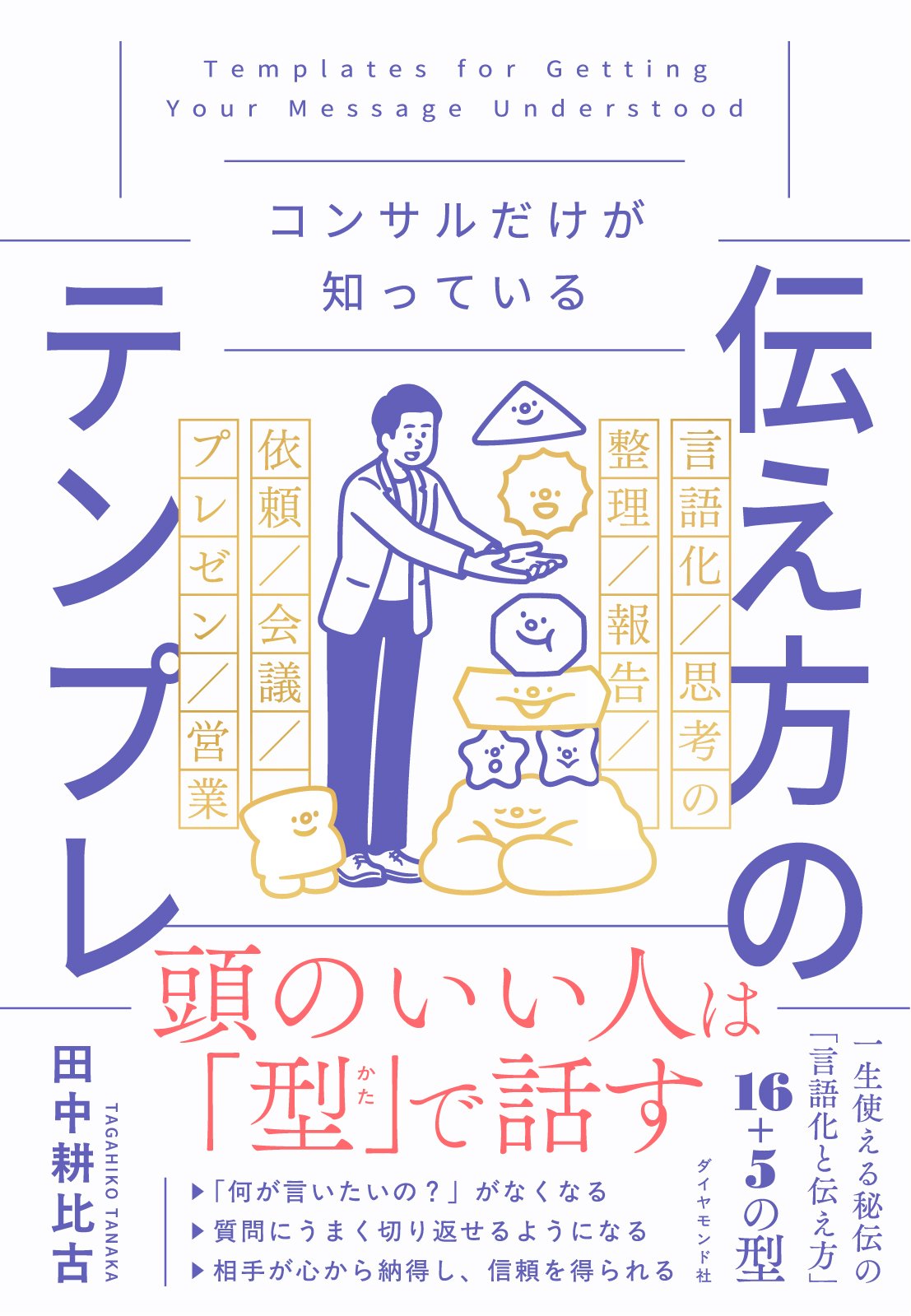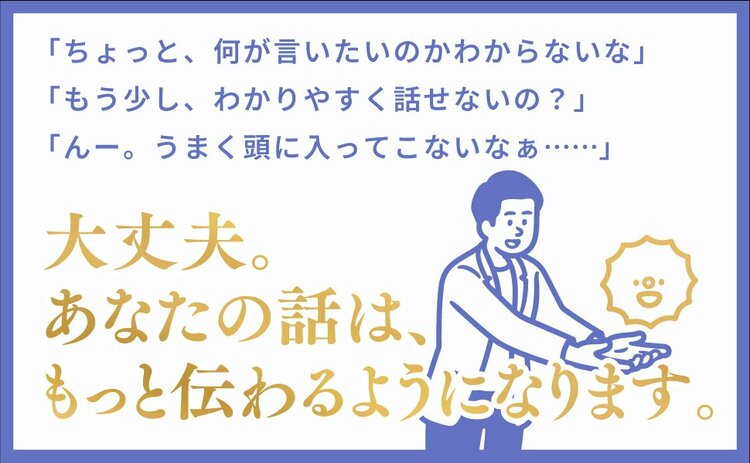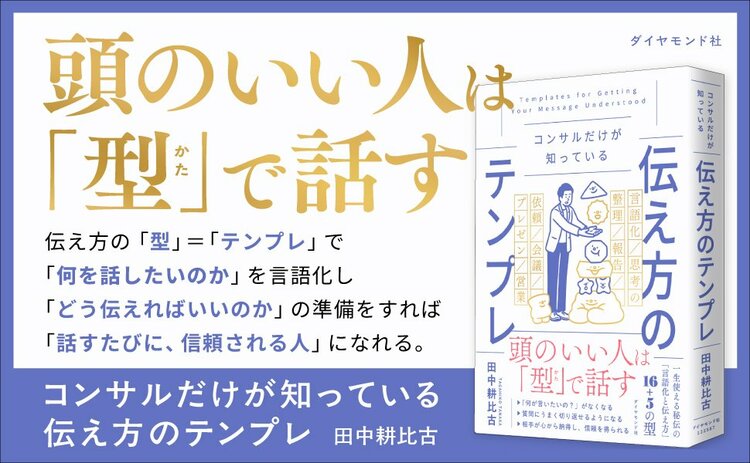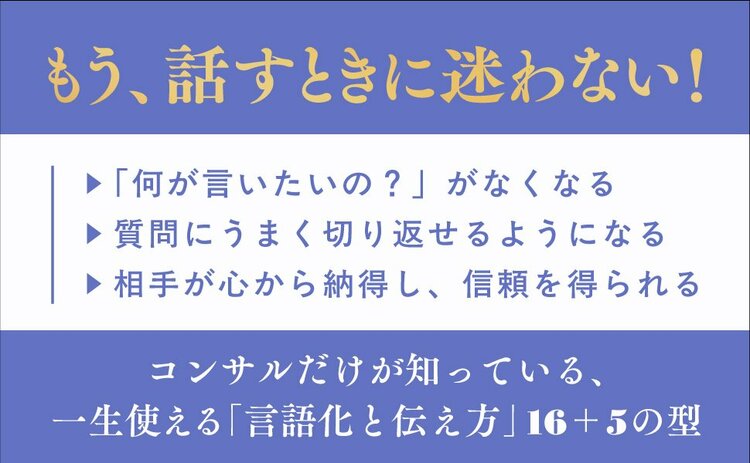転職は決まった。問題は「どう伝えるか」。角を立てず意思を示し、引き留めに流されず、日程と引き継ぎは現実的に――上司の信頼も未来の縁も守りたい。退職を伝える一言の用意は、できていますか?
『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏に、具体的な解決策を教えてもらいました。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)
 Adobe Photo Stock
Adobe Photo Stock
社会人としての礼儀をもって退職を伝える
転職が決まった。新たなキャリアを歩むという素晴らしいお話なのですが、これまでお世話になった社内の上司や先輩に、どのように伝えるべきかは極めて難しいテーマです。
理想は、相手の気分を害さずに、こちらの意思をはっきり示し、理解してもらうことです。
まずは面談のアポイントは「相談」という名目で取りつけます。
何の相談か聞かれた場合には、「キャリア相談」としておけば、相手も話を聞きやすいでしょう。
面談が始まったら、冒頭で結論を伝えます。「実は、退職しようと考えております」「退職させていただこうと思っています」と明確に伝えます。
この際に、「転職を検討しています」「キャリアに悩んでいます」といった曖昧な表現を用いると、相手は“転職を取りやめて、自社に残る可能性がある”と判断し、引き留め・慰留を目指した話をしてきてしまう可能性が高まります。
(もちろん、本当にどうすべきか悩んでいる場合は相談にのってもらうっても良いでしょう。)
他方で、「退職を決めました」といった表現で強く断定すると「相談だったのではなかったのか」とだまし討ちのように受け取られる恐れがありますので、「考えています/思っています」というくらいのトーンで固い意思を丁寧に示すのが適切です。
転職理由は、前向きなものを伝えます。
歩みたいキャリア像があり、その実現のために次のステップへ進みたい、という伝え方が基本です。
現職に対する不満や改善すべきところなどは、伝えなくてよい場合は控えるのが無難です。
相手から、「どうしても言ってほしい・教えて欲しい」と求められた場合でも、あくまでも「自分には合わなかった点として、◯◯や××があった」という程度の表現に留めておくと、余計な火種を生まずに済みます。
「相談」という体裁は、相手を味方にしやすい枠組みでもあります。会社は変わるのは致し方ないとしたうえで、人生・仕事の先輩である上司に、自分のキャリアを一緒に考えてもらえる状態をつくれれば最高です。
なお、退職の条件面では、譲らない方がいいです。
とくに退職日は、大きく動かさない方針を貫いてください。転職先の受け入れ対応に直結するためです。
ただし、社会人としての礼は欠かしません。
「2週間後に辞めます」「有休が十分あるので明日からは出社しません」といった急な通告は避けたほうがよいでしょう。いくら、法令上の権利として認められているとはいえ、人間関係は良好に保つに越したことはありません。(もちろん、ハラスメントなどの特別な事情がある場合は、その限りではありませんが)
自分の担当業務の重要度に照らして、十分な引き継ぎ期間と有休消化期間を織り込み、「退職日の目安」を提示します。
その目安からの譲歩は、せいぜい1~2週間にとどめるのが現実的です。
引き継ぎは、担当業務を一覧化して、進行中のものについては進捗状況・リスク・対応策を文書化し、引継ぎ先と期限を明確にします。引継ぎ先については、自分が想定している相手と異なる人や部署を指定されることもあると思いますので、そうした指示に従ってリストを最新化すると良いでしょう。方針が決まれば、後は、粛々と引継ぎを行うのみです。
最後に、これは非常に大切なことなのですが、退職後も元の職場と取引や転職の巡り合わせで関わる可能性は十分にあります。
現在の上司や同僚と、取引先として再開することも多々あります。あるいは、相手も同様に転職した結果、また同じ会社で働く可能性もあります。
だからこそ、後ろ足で砂をかけるような振る舞いをしてはいけません。
相手を尊重しながら自らの意思を明確に伝え、現実的な引き継ぎ計画を示すことが、円満な離任と今後のキャリアでの信頼につながります。
※本稿は一般的な観点からお伝えしています。実際の退職の日程・手続きは、就業規則や雇用契約、会社の指示に沿ってご確認ください。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏への取材をもとに作成しました)