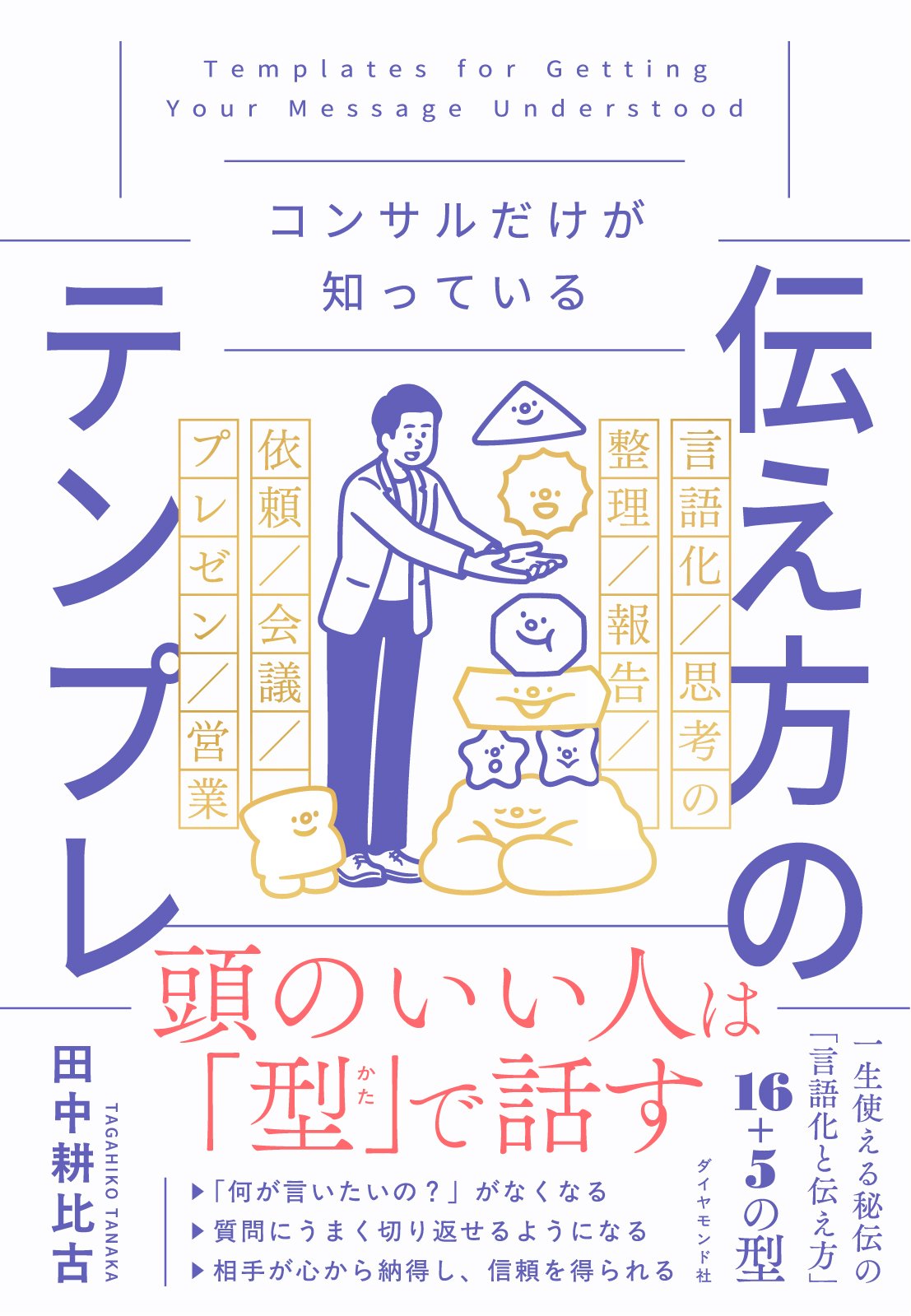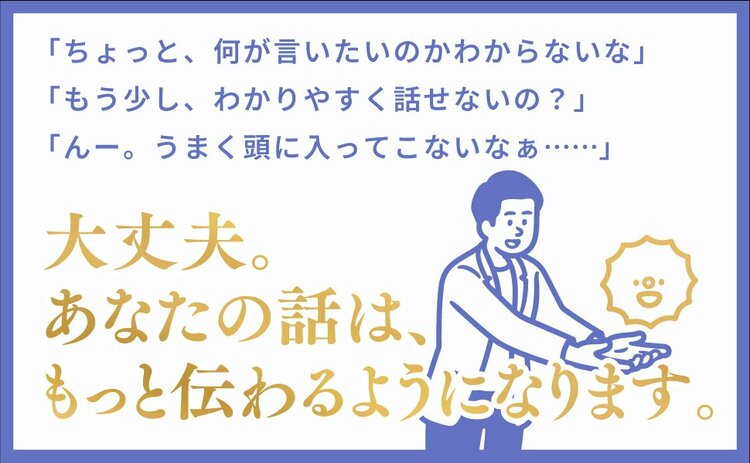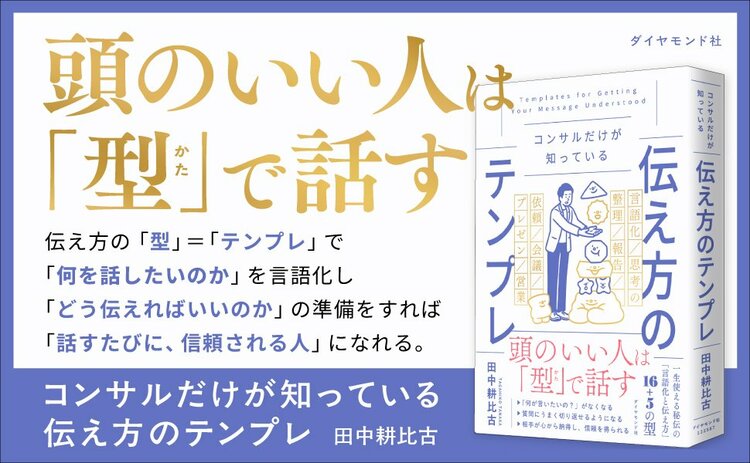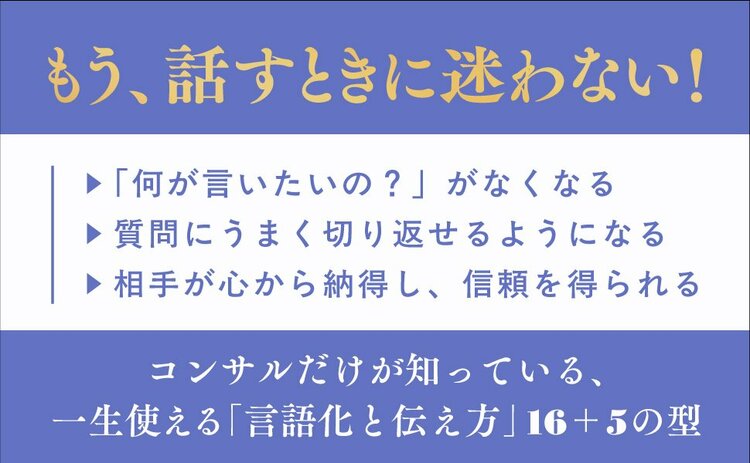「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
頭の中のことを「そのまま話す」
いくら頭のいい人でも、考えたことをそのまま話し出してしまうと「何を言っているのかわからない」と思われることはよくあります。
そうならないために、頭の中を整理してから話す必要があります。そのとき使えるのが「時系列テンプレ」です。
「時系列テンプレ」は、思考や説明を“時間の流れ”に乗せて整理するための型です。
具体的には、
ステップ①:起点を決める
ステップ②:時系列で並べる
ステップ③:主観的にたどる
ステップ④:抜け・飛びを確認する
という4ステップで考えていきます。
このステップを踏むだけで、頭の中の“ぐちゃぐちゃ”が“説明可能な構造”に変わります。
ステップ①:起点を決める
まず、考える範囲を定めます。
例えば「出社してから退勤するまで」「会議が始まってから終わるまで」というふうに、考える範囲を定義していくわけです。範囲ですので「はじまり」と「おわり」がありますが、その中でも、特に「はじまり」をクリアにすることが大切です。
ステップ②:時系列で並べる
続いて、時間の流れに沿って物事を並べていきます。
「順番に」「流れに沿って」思考を引き出すことで、そこで行われる行動や判断、あるいは感情などを、自然に“線でつなぐ”ようにとらえることができます。
ステップ③:主観的にたどる
その際に、「自分はどうしたか(どうするか)」という主観をベースに考えていくようにします。過去の自分の実体験に照らし合わせて考えていくことにより、記憶を「流れ」として再生することができます。
また、流れに沿っていくことで、どういうことを考えた(考える)か、あるいは、どういうことを感じた(感じる)か、といった行動の裏側にある思考や感情についても、想像することができます。
ステップ④:抜け・飛びを確認する
最後に、洗い出した情報を見て「これとこれのあいだに何か抜けてないか?」という問いかけを行います。流れに沿って再チェックをかけることで、思考の“空白”を埋めるわけです。
例えば、あるお客さんに向けた提案資料をつくる、という場合であれば、「資料をつくる」とか「訪問する」とか、「見積もりをつくる」などというふうにバラバラと思い出していても、うまくはいきません。
そこで、「時系列テンプレ」を使います。
まず、ステップ①:「起点」の設定です。「前回の打ち合わせ」を起点とすることにしましょう。
続いて、ステップ②・③:「時系列で」「主観的に」考えていきます。
この際に、過去の経験に照らし合わせて思い出してみると、やるべきことが洗い出しやすくなります。
この時点で、ほとんど漏れなく洗い出されているのが理想なのですが、最初のうちはやはり漏れも出てきます。
そこで、ステップ④:「抜け・飛び」の確認です。
このステップを踏まえることで、先方の予算に合わせた商品を選ぶ際には「社内イントラで最新価格を確認」しておく必要があるとか、見積もりをつくった後で「稟議システムで見積もり申請」を行わなければならないとか、提案書をつくったら顧客訪問の前に必ず「上司に確認してもらう」とか、そういうことが漏れていると気づくかもしれません。
こうした抜け・飛びが、仕事のスケジュールに影響を及ぼす場合があります。
今回の例でいえば、「稟議の待ち時間」「上司の確認時間」は、社内ルールや、上司の多忙さなどによって数日程度の待ちが発生するリスクがあります。
そうしたものが見つかった場合は、全体の作業計画を前倒しにするか、納期を後ろ倒しする必要が出てきます。
また、自分だけでは確認するのが不安な場合は、ステップ④を、上司や先輩に手伝ってもらうという方法もおすすめです。
時系列で情報が整理されていることで、先輩たちの頭の整理にもつながり、彼らの頭の中にある情報を引き出しやすくなります。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)