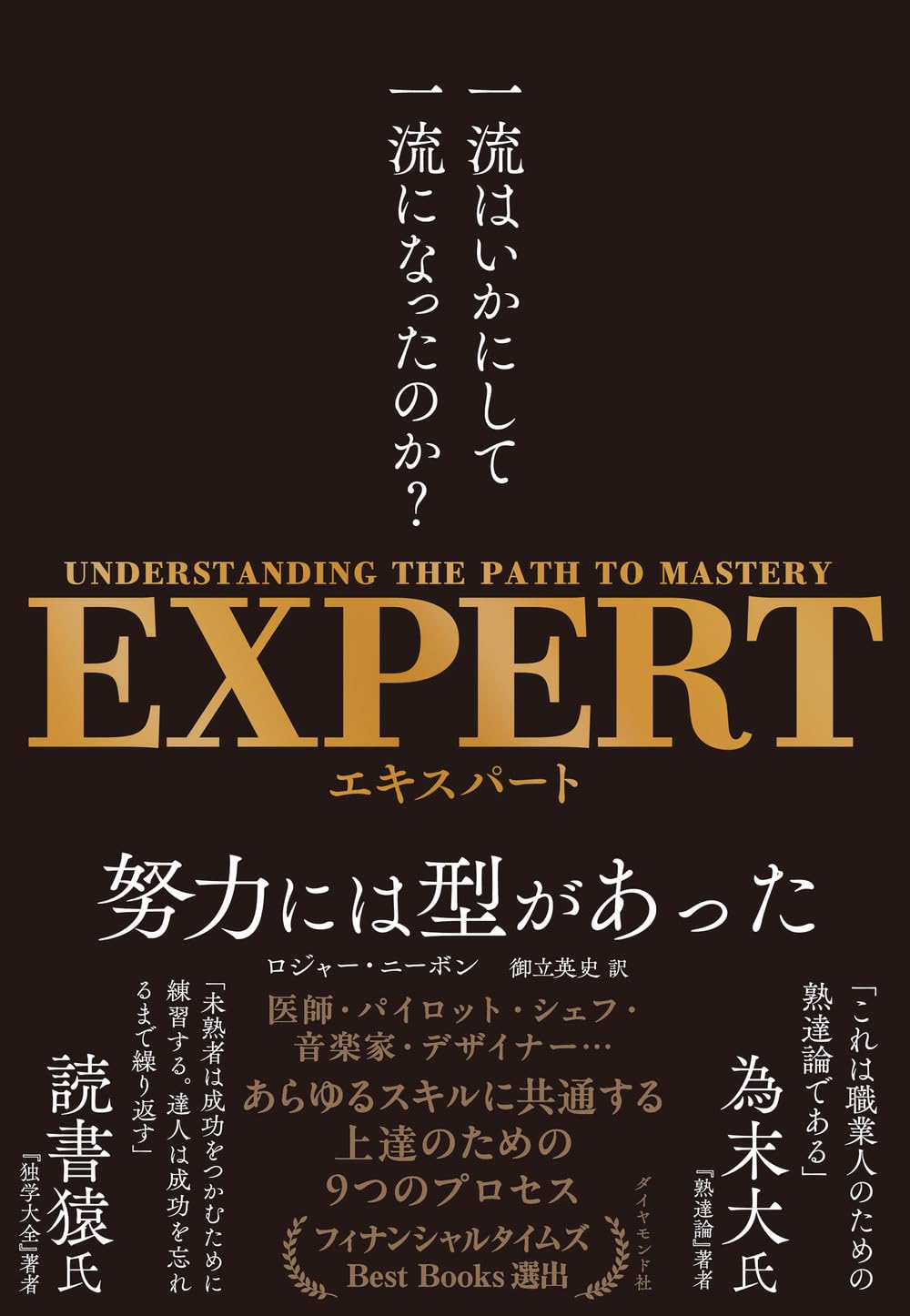『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は「圧倒的に仕事が速い人」の習慣について『EXPERT』の内容を元にお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
仕事が速い人の上達プロセス
「仕事が速い人」と聞くと、天性のセンスや生まれ持った才能があるのだろうと思われがちです。しかし実際には、圧倒的に成果を出す人は、特別な才能よりも仕事が速くなるまでの「上達のプロセス」に違いがあります。
専門性とパフォーマンスの研究で世界的に知られるスウェーデンの心理学者、K・アンダース・エリクソン氏は、こうした「卓越性の正体」を生涯にわたり研究しました。
彼は音楽、チェス、外科手術、スポーツなど、さまざまな分野のトップパフォーマーを調べ、その共通点を導き出しました。その研究はマルコム・グラッドウェル氏などによって広まり、「一万時間の法則」として知られるようになります。
しかし、多くの人が誤解していることがあります。エリクソンが言っているのは、「一万時間やれば誰でもエキスパートになれる」という話ではありません。
彼が本当に伝えたかったのは、「少なくとも一万時間はかけなければ熟達は望めないが、それだけやっても自動的に上手くなるわけではない」という厳しい現実です。
仕事が速い人ほど「普通の練習」をしない
エリクソンが繰り返し指摘したのは、多くの人が途中で到達してしまう“習熟の限界線”です。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』より
仕事でも、車の運転でも、語学でも、一定レベルまでいけば誰でも「そこそこ」できます。しかし、この「そこそこ」のレベルに到達したあと、同じ作業を漫然と繰り返しても、それ以上の成長は起きにくいのです。
仕事が速い人、つまり、仕事ができる人は、この限界にぶつかったあとに、さらに上達するためのアプローチを取ります。
圧倒的に仕事が速い人の習慣
では、さらに上達するためのアプローチとして、圧倒的に仕事が速い人はどんなことをしているのでしょうか。実は、圧倒的に仕事が速い人の4つの習慣があります。
① 毎日“どこを改善するか”を決める
トップパフォーマーは、今日の「改善ポイント」を言語化します。メールの速さなのか、会議のファシリテーションなのか、資料の作りこみなのか。伸ばしたいことを絞り、言語化しているのです。
② うまくいかないところほど細かく観察する
エリクソンの研究では、エキスパートは「失敗の原因を極めて細かく見る」習性があると指摘されています。
仕事が速い人は、躓いた瞬間にどうして躓いたのかを熟考します。
③ 上手い人のやり方を徹底的に分析する
「真似る」は最強の練習です。上司・同僚の中で速い人の思考プロセスを観察し、“差分”を見つけます。
④ フィードバックの頻度が圧倒的に多い
「練習はエキスパートからのフィードバックを受けながら行わなくてはならない」とエリクソンは述べています。仕事が速い人は、担当した仕事が完了する前に必ず他者の視点を入れます。その分だけ改善サイクルが速く、質も上がります。
この4つを意識するだけで、仕事の上達スピードは劇的に変わります。そして、上達した結果として「仕事が速い人」になっていくのです。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』を元にした記事です。)