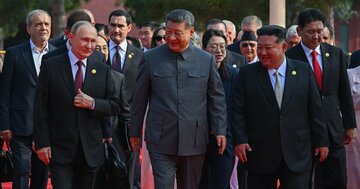「改革と粛正」から
「忠誠と監視」への転換
この過程で、習近平の統治は「改革と粛正」から「忠誠と監視」へと転換した。能力より忠誠、制度より個人への依存が強まり、個人独裁が固定化していった。
中央軍事委の人数を補充せず4人体制にとどめているのも、少人数のほうが統制しやすいからという理由だろう。習主席からすれば、「誰も信じられない」以上、意思決定の輪を極力小さくして、自らの監督の届く範囲に権限を集中させたほうがいいと判断したのだろう。
こうして形成された「習一強体制」は、外から見ると強権的な独裁体制であり、内側から見ると、習主席の不信が支える防御構造でできている。
習主席は、人を信頼することをやめ、監視機構、思想教育、AI検閲などのシステムに信頼を寄せるようになっていく。党内外に張り巡らされた監視網や自己検証制度は、その不安の裏返しだろう。
毛沢東とは異なる
習主席の独裁
毛沢東の独裁は、革命の最大功労者としてのカリスマ性と、彼が考える「毛沢東思想」というイデオロギーに支えられていた。毛氏は「思想」で人々を動員し、個人崇拝を通じて権力を維持した。
「毛沢東回帰」ともいわれる習主席の独裁は、それとは異なるところがある。習主席はもともと親しみやすさで人気になったのであり、カリスマ性は薄い。そのために、恐怖と監視を強化することで体制を維持せざるをえない。
毛沢東時代には「毛語録」が国民を統制する象徴だったが、習近平時代にはAI検閲とデジタル監視がその役割を担っている。これは、イデオロギー型独裁からテクノロジー型独裁への転換であり、中国の統治モデルの質的変化を示している。
権力集中の正当化のために
制度化された「習近平思想」
習近平は、権力集中を正当化するために「思想」を制度化する。2017年の党大会で「習近平思想」が党規約に明記され、毛沢東に連なる権威づけがなされた。
私には、習近平思想が国家スローガンというより、党員と国民に義務づけられた学習課題のように見える。
実際、党幹部のための研修では、習近平思想の理解度が昇進の評価基準に組み込まれており、学校教育でも教科書に習近平の言葉が掲載され、若年層への浸透が進んでいる。
また、中国共産党中央宣伝部が2019年に公開したスマホアプリ「学習強国」では、党員は毎日スコアを競いながら習近平思想を学ぶ仕組みが整えられている。このアプリは教育ツールであるとともに、行動データを収集する監視装置になっている。
この思想教育には、忠誠心の強化とともに、そこでこぼれ落ちる者への監視が付加されている。毛沢東の「思想による動員」が難しいので、習主席は「教育+デジタル監視」という形を使ったのだと考えられる。
「中華民族の偉大な復興」を掲げる習近平思想は、台湾統一や対米強硬姿勢に駆り立てるイデオロギー的基盤である。これは国内における人民の不安を外部に転嫁し、強硬路線を愛国と結びつけることで、権力の正当性を維持する「装置」に昇華している。
習主席の集団指導から独裁への変遷を見ていくと、習主席が目指した「腐敗なき中国共産党独裁」がそもそも達成不可能なのではないかと考えざるをえない。中国共産党の一党独裁体制が変わらない限り、中国政治の汚職体質も、強権政治による個人の自由の圧迫もなくならないのではないだろうか。