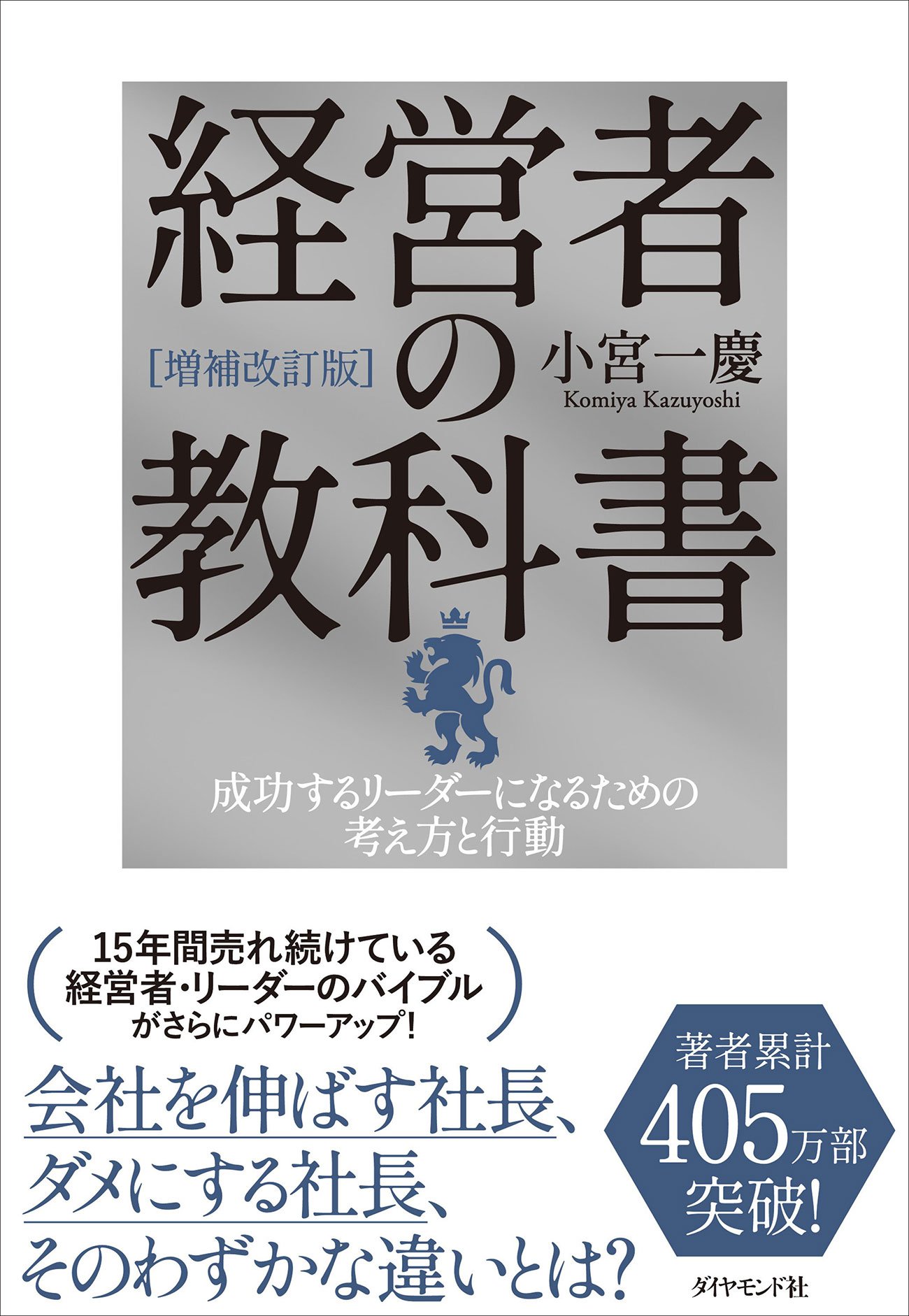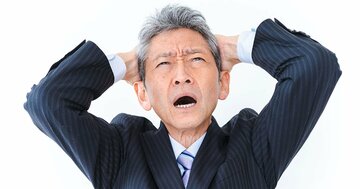会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か? 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』(ダイヤモンド社)は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
絶対に当たるビジネスなど存在しない
本当に良い会社を作れば、結果的に儲かります。
しかし、その儲けを全て貯め込んだり、経営者が懐に入れるのではなくて、将来のために使わなければなりません。
経営者にとって大事なことは、今やっている目の前のオペレーションをどうしようと考えることもその一つですが、それはある程度は部下に任せられます。
でも、部下が絶対に肩代わりしてくれない経営者の仕事もあるのです。
それは、5年後、10年後にこの会社をどうしようかという方向づけを考えることです。もし、そんなことまで考えてくれる部下がいたら、かなり貴重な存在ですが、そうそういるものではありません。ですから他の誰が考えてくれなくても、とにかく経営者は考えなければならないのです。
未来のために何をすべきか。それを考えるとき、忘れてはいけないのは、「絶対に当たるビジネスなど存在しない」ということです。それが分かったうえで、儲けなどで得た資金を将来のために投資する必要があるのです。
経営者がやるべき三つのこと
ピーター・ドラッカー先生は、経営者がやるべき事として次の三つを挙げています。
第一に、「既存の事業の業績向上」。つまり、今の事業をもっと深掘りしようということです。そのためには「徹底」や「継続」が必要です。これがなければ、他のことをやっても成功しません。それによって儲けて得たキャッシュを、「他社との違い」をより鮮明にするところに投資するのです。
先に、少し触れたウェディングボックスさんは、キャッシュ・フローに余裕が出たときに、振袖のカタログにきゃりーぱみゅぱみゅを使いました。お客さまには大好評でした。儲けて得たお金をどう「差別化」に使えるかが大切です。
次に、ドラッカー先生は「機会の追求」を言います。今あることを一歩進めた新しい商品を作ったり、既存商品の延長線上にあるような商品を作ったり、地域的な拡大をするなどを意味します。
その後に「新規事業」。文字通り、全く新しい事業を始めることを指します。この際、自社の強みを活かせる分野に進出するのです。市場があるからという理由だけで進出すると失敗する確率は高いものです。
高齢者がどんどん増える中、2000年に公的な介護保険が施行されました。その際、数多くの企業が介護業界に参入しましたが、結局、在宅介護の業界で勝ち残っているのは、それより以前から介護事業を行っていたニチイ学館やセントケアなどです。強みを活かせないところが、市場だけを目当てに参入してもなかなかうまくいかないのです。
ドラッカー先生はこの三つを、この順番で行うべきであるとしたのです。
この順番に難しくなるからですが、いずれにしても、現事業で「自社の強み」を活かしながら、「徹底」ができて、ベストパフォーマンスを出しているかが、「機会の追求」や「新規事業」を成功させるための大きなポイントです。
まずは、今の事業を深掘りするために
できることはないかを考える
「今のままでいい」という考え方は間違っていますが、だからといって新しいことを必ず始めなければいけないかというと、そうではない。
まずは、今の事業を深掘りするためにできることはないかを考えることが必要です(「徹底」については、次で詳しく説明します)。
ビジネスとは、「市場における他社との競争」と定義されます。市場と他社とを見て、外部環境を分析してみれば、もっとやれることは必ずあるはずなのです。
一方、市場のない分野では勝てません。電気自動車や燃料電池車がさらに普及すれば、ガソリン需要が大きく減ります。ガソリンスタンドのあり方も変わります。自動車部品では、ミッションや排気系は縮小せざるを得ません。自動運転車ができれば、タクシーの運転手は減るでしょうし、車の所有率も下がるでしょう。市場の将来を見極めることが必要です。
逆に、市場が十分にあれば、強みを強化すれば、ライバルに勝てる要素は何かしら必ずあります。
それをどうやっていくかを考えるのが経営者の仕事です。
(本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです)
株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO
10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。
1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM&Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。
94年5月からは日本福祉サービス(現セントケア・ホールディング)企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。
著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』(以上、ダイヤモンド社)、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』(以上、東洋経済新報社)、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何?」という人のための投資指標の教科書』(以上、PHP研究所)等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。