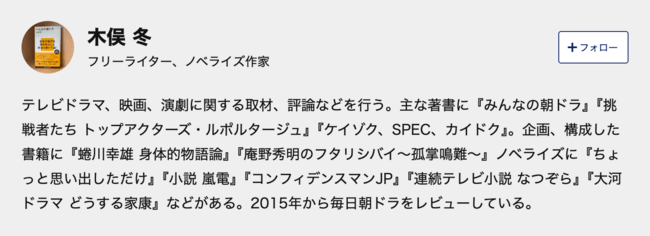がんばれ銀二郎
その頃、松野家ではふたりを心配している。
「さすがにほぐれちょりますでしょう。前は夫婦だったんですから」とフミ(池脇千鶴)。
3人は銀二郎とトキがよりを戻したら、自分たちも東京に行くことになるがどうしようかと思案している。「もし面倒を見てもらうことになりましたら」と面倒を見てもらうのが当然と思っているのだ。まあ、銀二郎自身が家族の面倒を見ることができるようになったと言ったからだが。
「ダメでした」
銀二郎が錦織とイライザに言う。
トキとヘブンは怪談がたりが終わっても、怪談について話が止まらなくて、銀二郎はその輪に入れなかった。もうこの状況がまずいだろう。でも、イライザは「(ヘブンは)昔からこう」と銀二郎よりは落ち着いている。
ヘブンは自分の好きなことになると夢中になる。でも人を好きになれない、臆病な人だとイライザは理解していた。たぶん、銀二郎に握手しなかったのもそのせいと、あのときは思ったのだろう。
そんなイライザも、やっぱり動揺していた。
「変わったわ、あの人」
いつもどこでも定住する気がなく人づきあいもしてこなかったヘブンが、すっかりこの土地に溶け込んでいると感じたのだ。トキに見せる表情が違うのだろう。
イライザの英語がわからない銀二郎だが、なんだか彼女の言っている意味がわかった気がしていた。
銀二郎もトキが4年前とはどこか変わってしまったことに気づいたようだ。さぞ、心が寒かろう。
そのあと、2組は別行動。
トキと銀二郎は夕暮れの湖の岸を散歩する。
「すごかったなあと思って。彼の熱というか。あがに怪談に食いつく異人。まるで彼が大亀だったが」
と言う銀二郎にきゃははとトキは笑う。言いえて妙で、昔の人たちは異国人を鬼として物語を書いてきたかもしれないからだ。
「毎晩毎晩遅いときは丑三つ時までなんべんもなんべんもせがんで聞たがって」とうれしそうにヘブンを語るトキ。「布団」というワードをなみ(さとうほなみ)に誤解されたり、布団を抱きしめ思い出し笑いして家族に誤解されたりしてきた。
「毎晩毎晩ふたりきりで夜中までなんべんもせがんで」も下ネタと誤解されても仕方ない。朝からみだらな想像をさせないでーと訴えても、想像するほうがいやらしいと言われてしまいそうだけれど。このへん、脚本家ふじきみつ彦のしれっとしたうまさ。意図的なのか意図的じゃないのか境界があいまいな妙味がある。
トキは純粋に怪談の話をしているだけでしかもヘブンに聞かせたのが銀二郎のとっておきの『鳥取の布団』なのだと報告したいのに、「けど」と銀二郎は力んで遮る。
「東京の怪談もすごいよ」
ああもう銀二郎が不憫(ふびん)でならない。いつか一緒に聞きにいこうと約束したから『怪談牡丹燈籠(ぼたんどうろう)』をまだ聞いていないと言うのだ。
「一緒に聞きに行こう東京で」
「東京で?」
「おトキちゃんとやり直したい」
うつくしい夕暮れの湖に、やけに大きな波の音が聞こえる。
明日が年内最後になる。トキと銀二郎とヘブンの顛末(てんまつ)を見たいような見たくないような。