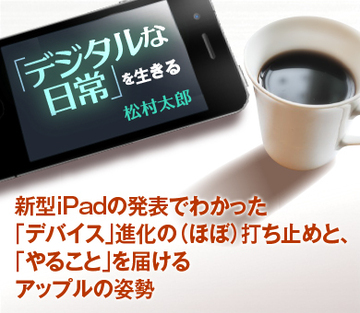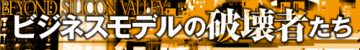前回に引き続き、タブレットに関するテーマを扱う。教育やビジネスの現場にタブレットを導入するとどうなるか、という話を取材することが多かった2013年だった。スマートフォンに比べればまだまだ本格的な普及とはなっていないかもしれないが、家庭にタブレットがやってくるとデジタルライフを一変させるには十分な手軽さと機能を備えている。パソコンを中心としたデジタルやネット活用からの変化を見てきた。
今回は、iPadを全校生徒・教員に導入した三重県松阪市立三雲中学校を取材した。総務省の「フューチャースクール」としてICT教育を実証する過程で見えてきたことは、いったい何だろうか?
プレゼンのうまさよりも
学んだことの共有を重視
 「音」の伝わり方をiPadで学ぶ学生 Photo by Taro Matsumura
「音」の伝わり方をiPadで学ぶ学生 Photo by Taro Matsumura
ある火曜日の午前、三雲中学校の授業を拝見することができた。生徒は朝当番がロッカーの鍵を開けて自分のiPadを取り出し、1日の授業で利用する。学校内には無線LANが張り巡らされ、教育で使うコンテンツなどへのアクセスが可能だ。全員のiPadには青いカバーが付けられており、先生の話を聞くときにはタブレットを机の上で裏返す、というルールがあったことも印象的だった。
まず参観したのは理科の授業だ。中学1年生の授業で「音」について学ぶ。生徒たちは手元のiPadで音の波形を表示できるアプリを使って、先生が吹くアルトリコーダーの音を拾い、音の強弱、高低による違いを可視化し、班ごとにまとめて発表する、という流れだった。
生徒は各自のiPadで波形の特徴を観察し、班で相談して、代表者のiPadからワークシートに記入する。すると9つあるクラスの班から黒板の脇にあるデジタルテレビに回答が集まり、1班ずつその説明を発表するという流れだった。
次に見たのは家庭科の授業。前回の授業でiPadで写真などを撮りながら木工の作業工程を記録し、それを短いプレゼンにまとめて発表するスタイルだった。プレゼンを上手に行ったり、スライドをきれいに作成することが目的ではなく、行った作業を確認したり、気づいたことを共有することが目的。プレゼン後の先生によるコメントも、木工やプレゼンでの作業分担やキチンと要点が記録されていたか、わかりやすかったか、といった点が中心だった。
 家庭科では、木工作業の過程を撮影して、それをスライドにして発表する授業を行う Photo by T.M.
家庭科では、木工作業の過程を撮影して、それをスライドにして発表する授業を行う Photo by T.M.