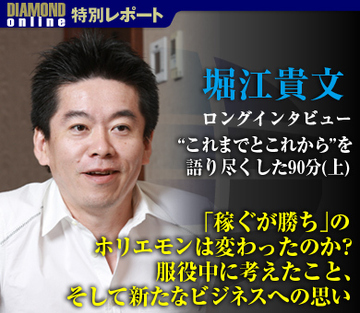堀江貴文さんの『ゼロ』に大きな感銘を受け、いまでは若い学生たちに薦めているという蜷川実花さん。見えないところでの努力を重ね、ここまで懸命に働いてきた2人の目には、最近の若い世代が自信を失っているように映るといいます。そして2人の口から出てきた言葉は、まさに『ゼロ』のサブタイトルである「なにもない自分に小さなイチを足していく」ことの重要性でした。(写真:平岩紗希)
結果を見ないから
想像を超えられる
堀江 ところで蜷川さんって、いまや写真家と映画監督の二足のわらじ状態ですけど、写真と映像(ムービー)って、やっぱり違うものですか?
蜷川 ぜんぜん違いますよ。
堀江 具体的に、どういう違いなんでしょう?
 蜷川実花(にながわ・みか)
蜷川実花(にながわ・みか)鮮烈な色彩感覚でいま最も注目を集める写真家・映画監督。木村伊兵衛写真賞ほか数々を受賞。映像作品も多く手がける。2007年、映画『さくらん』監督。2008年、個展「蜷川実花展」が全国の美術館を巡回し、のべ18万人を動員。2010年、Rizzoli N.Y.から写真集「MIKA NINAGAWA」を出版、世界各国で話題となる。2012年7月には監督映画『ヘルタースケルター』が公開され大ヒットを記録。2013年春、上海・外灘に内装プロデュースを手掛けたカフェ&バー「Shanghai Rose」がオープン。蜷川実花の世界を気軽に表現できる無料カメラアプリ「cameran」もリリース中。
蜷川 映像のときって私がカメラを回すわけじゃないから、全部言葉で説明しないといけないんです。「あそこのお尻がかわいいんで、もうちょっと寄ってください」とか「あのスカートがひらひらっとする瞬間がいいんで、もう少し風を当ててください」とか、言語化する論理的な能力が必要になる。
でも、写真って感情と機械がすっごいダイレクトにつながってるので、言葉はなにも要らないんです。カッコイイと思って撮れば、カッコよく写る。ものすごく感情的なんです。
堀江 なるほどねえ。
蜷川 もちろん、写真についても努力はしましたよ。堀江くんの『ゼロ』じゃないけど、すっごい努力した。でも本人はそれを努力と思わないじゃない?
堀江 ハマる、ってことですよね。
蜷川 そう、ハマってるだけだから。別に朝から晩まで現像室にいても、それが当たり前だし楽しいですしね。駆け出しのころは出版社をたくさん回って、足蹴にされて、どんだけ回っても写真集が出ないとか。そういうのも苦労じゃないっていうか、当たり前だと思ってました。
堀江 僕らの世代って、フィルムからデジタルに変わった世代じゃないですか。蜷川さん、そこの切り替えはすぐにできたんですか?
蜷川 いや、けっこう大変でしたよ。最後の最後までフィルムで粘ったし、いまでもフィルム使うことあるし。
堀江 ええっ? そうなの?
蜷川 うん。色が派手だから「デジタルでしょ?」って言われるんですけど、断然フィルム。やっぱりカメラが物理的に変わると写るものも変わるんですよ。
堀江 それは画素数とかそういうことじゃなくって?
蜷川 違う違う。たとえば、顔よりも大きなカメラをかまえて「撮りまーす!」とか言われると、多少は萎縮するじゃないですか。でも、ケータイで「撮るよー」ってかまえられても緊張しないでしょ?
堀江 ああー、そうか。なるほどね。
蜷川 そういうレベルで、たとえばデジカメだとシャッター音も軽くてむかつくし。
堀江 シャッター音とかカスタマイズできないの? なんかそういうサウンドつければいいじゃないですか。
蜷川 そういう問題じゃないんですよ。あとデジタルだと、その場で結果が見られますよね? それで「よし、これでいいや」と思ったらおしまいなんです。フィルムの場合は、どう写ってるかわからないからけっこうたくさん撮るんですよ。そうすると、自分が想定したのよりおもしろいところに行くパターンが多くって。
堀江 なるほどねー。写真家にとっても意外性があるのか。
蜷川 結果が見えないからこそ、想像以上のものが撮れるという。だからデジタルに慣れるのは、かなり時間がかかりました。ここ数年ですよ。
恵まれた環境に生まれる人なんていない](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/8/360wm/img_a88bf79bf6fb3b91f19a2c7300e955ec115497.jpg)