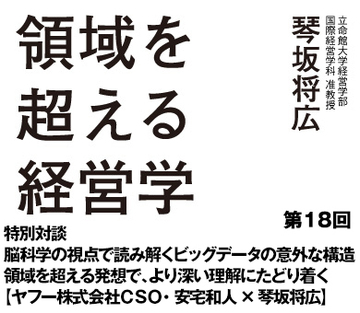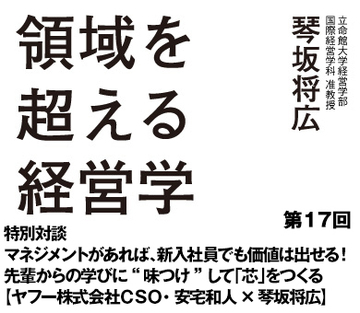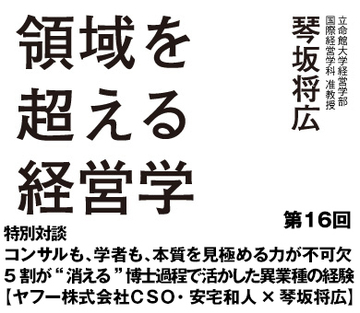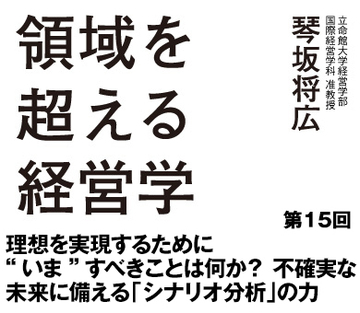経営学の実態は「本質主義」と「構築主義」の中間に
こうした複雑性を持つがゆえに、経営学の研究は、自然科学とは異なる要素も持つようになります。
もちろん、科学的手法で積み上げられた「客観的事実に基づく共通理解」を、自然科学と同じように作り上げていく努力は日夜、至る所で行われています。しかし同時に、研究者間での相互の研究交流や、議論の中から、「個々人の認識の共有たる共通理解」が生まれているのも事実です。
これは本質主義(Essentialism)と構築主義(constructivism)という両極の議論である、とも捉えることができます。そして、その両者が、広義の経営学の世界には併存しているのです。これは、自然科学とは大きく異なる点なのではないでしょうか。
すなわち、個々の事例に左右されない普遍的で恒常的な本質、法則性が存在すると信じるのであれば、自然科学とまったく同じ方向性で研究手法を磨き上げていけば、社会科学としての経営学も、いつかは自然科学の他領域のような厳密性を持つに至ると信じることができます。
一方で、個々の事例には個々の事例にしか存在しない特殊性があり、そうした特殊性により、その物事の本質が定まると考えるのであれば、自然科学とまったく同じ方向性で研究手法を磨き上げていくことが、必ずしも意味のある答えにつながらないと主張することできます。
どちらが正しいかはわかりません。しかしおそらく、その実態は、この両極の中間地点にあるのでしょう。
であるならば、「経営という行為と、それを行う組織と個人」を対象として探求する経営学は、自然科学の研究が持つ厳密性を実現するために手法を磨きこむと同時に、ただそれを真似るのではなく、人間の社会的行動を探究するという特殊性に則した、独自の考え方と手法を構築していく必要があると、私は考えています。
その独自の考え方と手法を探し求める行為の途上にあるがために、経営学、さらにはそれを包み込む社会科学には、互いに相容れない哲学を背景とした方法論と主張が混在するのでしょう。